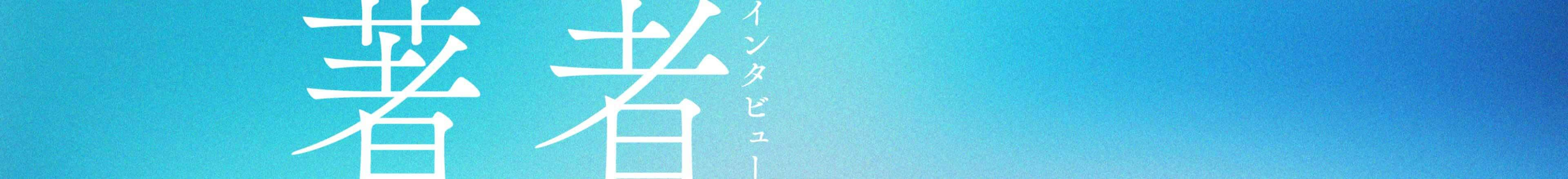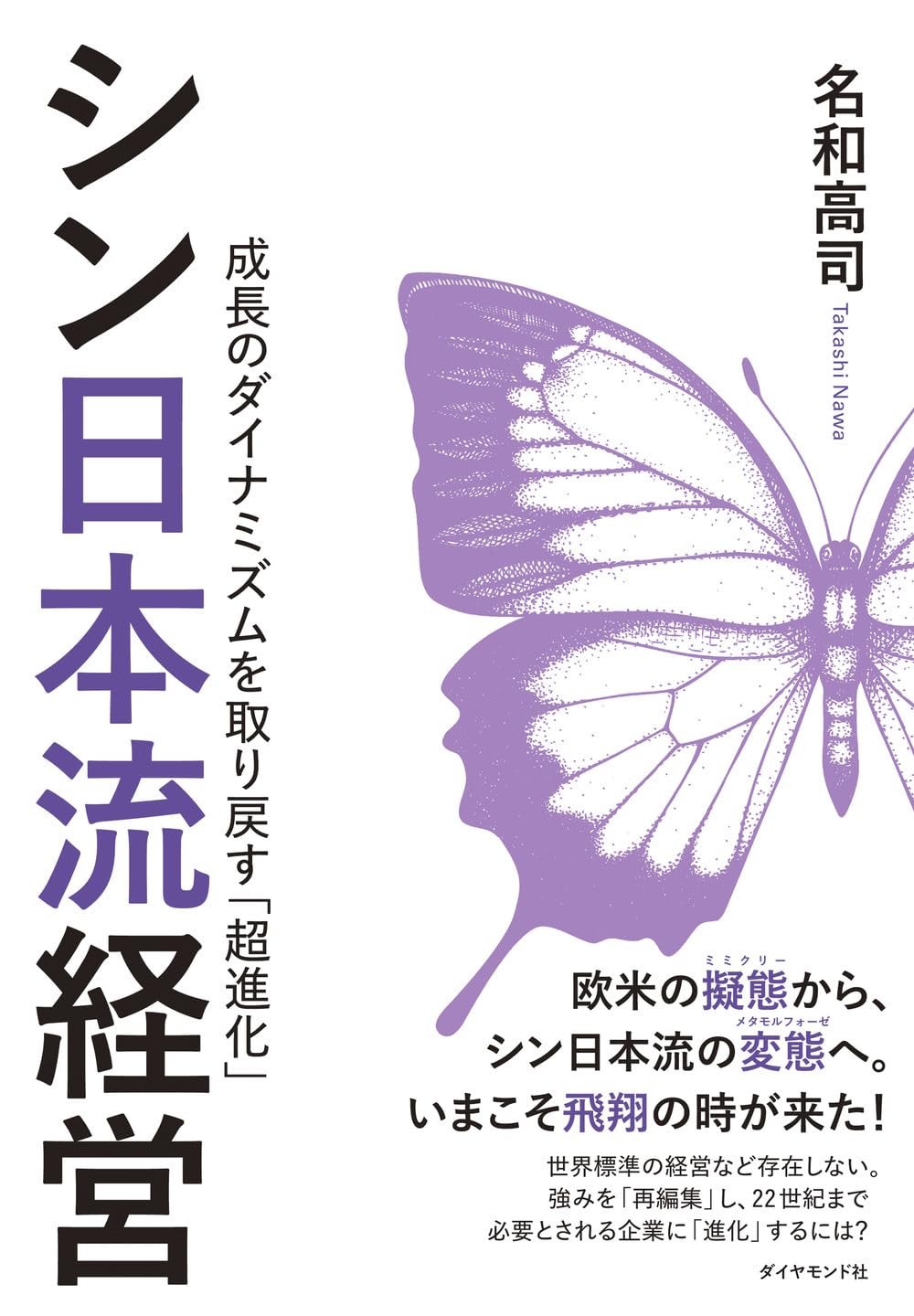出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間、バブル崩壊に伴い急速に競争力を失った日本企業。その失敗の本質について、京都先端科学大学教授・一橋ビジネススクール客員教授の名和高司氏は「擬態(カモフラージュ)病に陥っていた」と分析する。日本企業が病にかかった原因はどこにあり、真の復活を果たすためには何が必要なのか。2025年2月、書籍『シン日本流経営――成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』(ダイヤモンド社)を出版した名和氏に話を聞いた。
バブル崩壊を機に日本企業が陥った「カモフラージュ病」
──著書『シン日本流経営――成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』では、多くの日本企業が平成・令和の時代において競争力を低下させ続けている原因について分析しています。その失敗の本質はどこにあるのでしょうか。
名和高司氏(以下敬称略) 戦後著しい成長を遂げた日本ですが、1990年頃をピークに成長が頭打ちとなり、自信喪失に陥った日本企業の多くはそれまでの日本流経営を「昭和型」と切り捨てるようになります。そして、アメリカ流の経営を「グローバルスタンダード」「世界標準」などとして追い求めるようになりました。
私はこの世界標準という言葉に違和感を覚えています。なぜなら、そもそも世界標準など存在しないからです。成長を続けている各国の企業は、いずれもアメリカ流、イギリス流、ドイツ流、シンガポール流と、それぞれ独自の経営モデルに磨きをかけています。
それにもかかわらず、なぜかアメリカ流を世界標準と呼び、マスコミもそのように発信し、多くの日本企業はアメリカ流経営を採り入れるようになります。こうした理論先行型の経営論は一見スマートですが、実践知を重視する日本企業の現場に実装されることはありませんでした。
「平成の失敗」は、日本流の現場の強みを軽視し、最新理論で武装したはずの経営が迷走を繰り返したことにあると考えています。