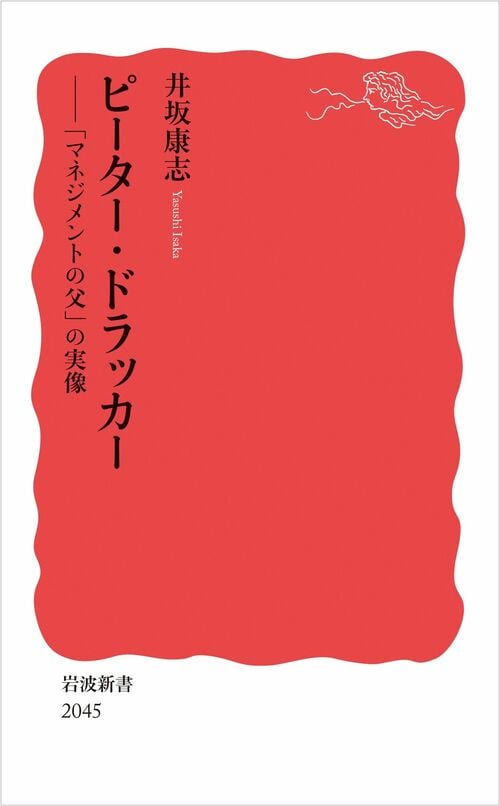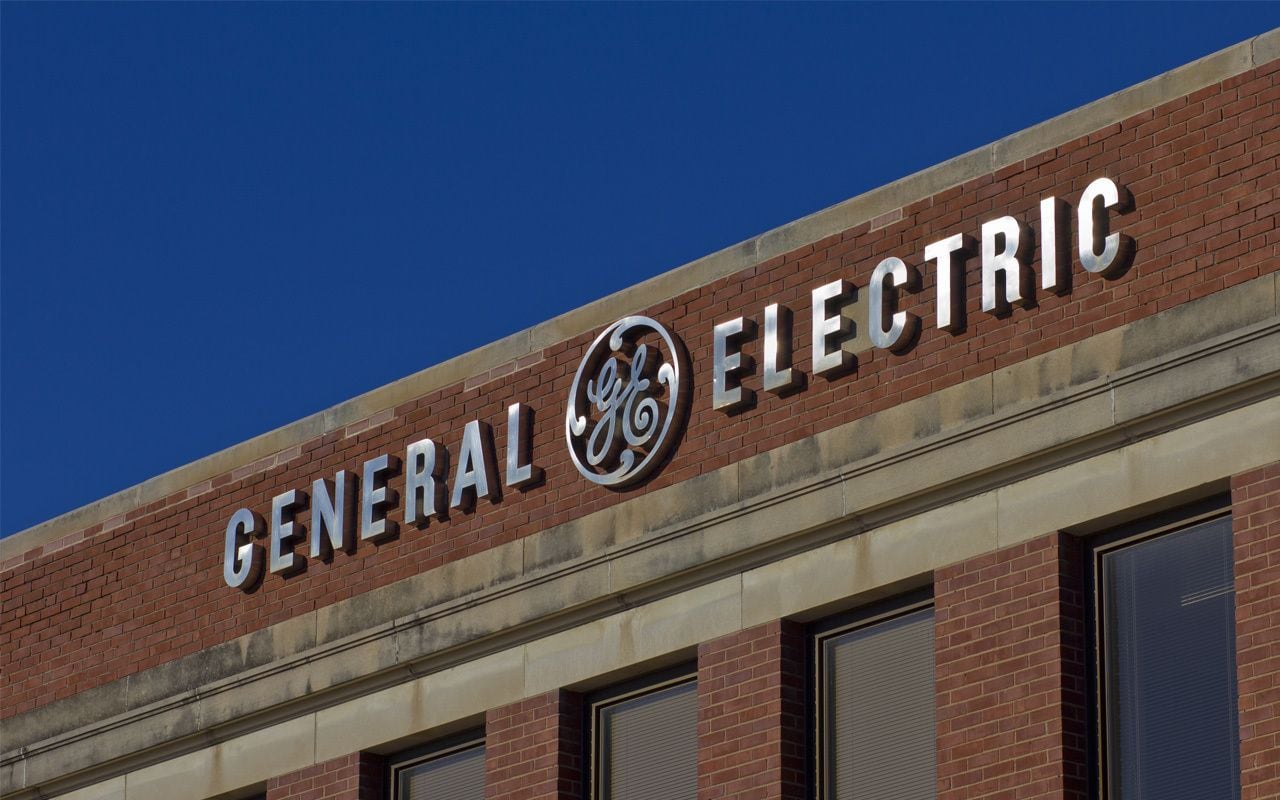 ドラッカーが『現代の経営』を書く上で、GEのコンサルタントを務めた経験がヒントになった。
ドラッカーが『現代の経営』を書く上で、GEのコンサルタントを務めた経験がヒントになった。Jonathan Weiss/Shutterstock.com
「マネジメントの父」と呼ばれ、日本では1956年発行の『現代の経営』以来、数々のベストセラーを生んだピーター・ドラッカー。日本の産業界に多大な影響を与えたと言われる一方、その人物像が語られることは少ない。本稿では『ピーター・ドラッカー ――「マネジメントの父」の実像』(井坂康志著/岩波新書)から内容の一部を抜粋・再編集。没後20年となる現在も熱心な読者が絶えないドラッカーの人生と哲学、代表的な著書が生まれた背景を紹介する。
ニューヨーク大学で教鞭を執る傍ら、経営コンサルタントとして実績を重ね、代表的著作『現代の経営』をまとめたドラッカーが1950年代に残した功績とは?
GEクロトンヴィル研修所
「報酬を得てクライアントを叱るインサルタント(侮辱者)」とドラッカーは好んで自称し、「高い報酬をもらって人を侮辱している」と語っていた。
コンサルタントとは、経営者が自分自身について行う説明に影響されることなく、まったくクールな態度で聴くことができなければならない。相手の熱情に感化されたり、同調したりすると、彼が本当になすべきことを見失う。対話の中で、なすべきことを率直に指摘することは、時に相手のプライドを打ち砕く。善意があればこそ、相手の意向に忖度(そんたく)することなく、率直に耳に痛いことも直言しなければならない。「インサルタント」とは逆説的にその職業倫理の表明とも解釈できる。
ドラッカーは、徹底して経営の傍らに立ち続けた傍観者、アウトサイダーであって、経営経験は持たなかった。大組織の一員になることは彼にとって退屈で、適性も能力もないと自覚していたためである。また、リストラの仕事は気質に合わずすべて断った。彼なりに身につけた作法がそれだった。
1954年、マネジメントの代表的著作『現代の経営』が刊行されている。詳しくは次項で取りあげるが、コンサルティング経験に反省を加えつつ、同時に技法や考え方を練り上げることで編まれた著作である。ゼネラル・エレクトリック(GE)のコンサルタントと幹部教育支援開始の時期にあたり、そうした活動もこの著作にインスピレーションをもたらした。