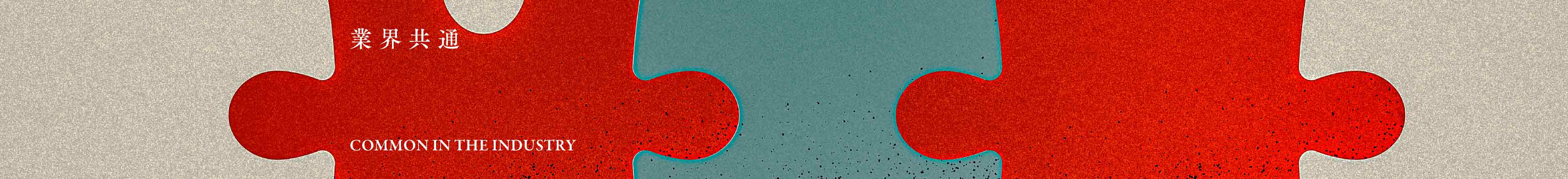リクルート 事業統括室 Vice Presidentの三木久生氏(撮影:宮崎訓幸)
リクルート 事業統括室 Vice Presidentの三木久生氏(撮影:宮崎訓幸)
リクルート入社以来、一貫して経営管理部門に所属し、同社のFP&A(ファイナンシャルプランニング&アナリシス)の組織化に尽力してきた三木久生氏。VUCAと呼ばれる変化が激しい時代に経営管理のプロフェッショナルとしてのキャリアを重ね、FP&Aの重要性を社内外に発信する。三木氏が追い求めてきたFP&A組織の在り方、人材像を聞いた。
バブル崩壊で鍛えられた経営管理の現場業務
――三木さんは、リクルート内でFP&Aというポジションの確立に尽力されてきました。入社したときから、管理会計、経営管理には関心があったのですか。
 三木 久生/リクルート 事業統括室 Vice President
三木 久生/リクルート 事業統括室 Vice President1989年、リクルートに新卒で入社、中途採用情報誌の計数管理を担当後、全社レベルの事業管理を担当。経理・財務の勤務経験はなく、一貫してFP&A(Financial Planning & Analysis)として、経営計画の策定および目標達成に向けた業績管理PDCAサイクルの基盤構築・運用実践に携わる。また、事業と全社スタッフのパイプ役として、構造改革・内部統制体制構築・上場準備・グループ再編等、様々なプロジェクトに関わる。
三木久生氏(以下・敬称略) 特に関心があったわけではなく、最初に配属された部署が事業部のスタッフ部門だったというだけです。当社では「統括」と呼ばれていて、その業務はいわゆる「なんでも屋」のような役割でした。人事部は人事、経理部は経理の仕事をするわけですが、統括はそれ以外のことを担当していました。
その1つに、営業の今期目標を設定する仕事も含まれていました。計画を立てるからには、各部門の通期計画はどうなっているのか、また、現在戦略的にどこに力を入れているのかといった情報を集めなければいけません。部門がやろうとしていることを知った上で、どうやって営業の目標に落とすのかを考えました。あとはコスト管理ですが、これは帳票を見て予算と実績を対比して最終的に損益計算書(P/L)を作るという作業がスタートでした。
当社を含め、多くの会社がそうであるように、上で決めた数字を現場に目標として落として、それを実行させる方式を採用していました。私が配属された統括部門の役割は、その目標を現場に説明することでした。そのため、現場の課長、部長職からは常に「目標が高すぎる」と叱られていて、ある意味で社内の憎まれ役でもありました。
それでも、私が入社したころはバブルの絶頂期でもあり、目標は上振れすることが当たり前に思われていたことも事実です。会社の業績が伸びている時は、管理も比較的、楽な状態でした。
それが、2~3年後に一変することになります。バブルが崩壊し、当時展開していた不動産事業や貸付事業が焦げ付き、リクルート本社は最大で1兆数千億円という莫大な額の負債を抱えました。
これは、金利負担だけで年間500~600億円にも上る数字です。金利分だけでも返済しないといけないので、それだけの営業利益が必要でしたが、バブル崩壊以降のデフレで売り上げは下降傾向です。それにもかかわらず、経営層からのッセージは、「売り上げが半分になっても、利益は維持してほしい」という大変厳しいものでした。
その無理難題を「お願いします」と現場に言って回るわけですから、当然「何を考えているんだ」と猛反発に遭うわけです。しかし、私たちの仕事は経営陣の考えを、数字を示しながら粘り強く伝え、現場に実行してもらうことです。どの部門に説明に行っても最初は取り合ってもらえませんでしたが、事実を示しながら「会社を倒産させないために、どうやって利益を出していくか」を粘り強く説明し、納得してもらいました。
借金返済の見込みがたった2000年代に入ってから、リクルートは全社的にグローバル展開とガバナンス変更など、再び攻めていくための態勢を整えていきました。ただし、業績管理については、売り上げではなく利益を最重要のKPIに置く文化が定着していました。