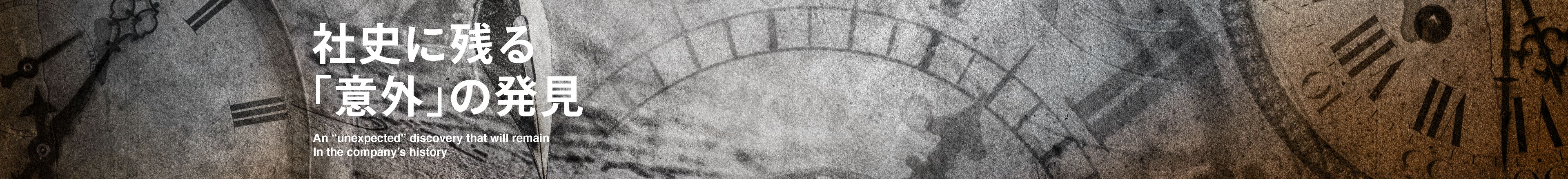「社史は面白くない」?
 大屋晋三(出典:「帝人の歩み」)
大屋晋三(出典:「帝人の歩み」)
帝人が50周年記念に刊行した『帝人の歩み』を読んでみてほしい。大屋晋三が社長のとき、ジャーナリストの福島克之(かつゆき)に資料収集から編集企画、執筆にいたるまで全権を託したもので、全11巻。1968年5月から1977年6月まで9年かけて刊行した。個人が集めた情報にもとづいて執筆したものなので、「社史」ではなく「企業史」というべきものではあるが、 序文に大屋社長が「わが社の姿をありのままに、飾らず偽らず隠さず、そのまま率直に描き出したい」と書いている。その言葉通り、全編を通して、逐一、誰がどう言った、それにどう反論したと、具体的な人の名前まで明記してある。例えば、1945年の社長交代をめぐるやりとり。社長候補は、常務だった大屋晋三。これに対して、社長を辞すると決めた久村清太(くむら・せいた)は別の人を考えていたが、周囲の人に意中の後任について聞いてまわったところ、普段温厚な経理部長はその名前を聞いて驚き、「当然、大屋常務が昇格すべきです。社長の意中の候補では社内は治まりますまい」と、真っ向からこれに反対した。久村は「君までが反対するのでは駄目だね」と言ったなどと書いてある。経営陣の意見対立をこれほど率直・詳細に明かした社史は珍しい。社長の大屋のことも、必ずしも褒めているわけではない。「大屋は、いわゆる“非常時型”といった人間で、社業が順調な時にはそれほどでもないが、何かことがある時には、必ずその鋭鋒を現すのが常であった」とか、「大屋の性格に反発していた久村の目には、大屋の飛躍的な行動、端的にいうならばその“離れ業”が危険なものに思われ、大屋と一緒ではやってゆけない。出てきて大屋に注意してくれ」と別の人に頼んだりしている。
編纂者・福島は「この久村と大屋の両名の間が円滑でなかったことは、旧陸軍で上原勇作と宇垣一成の仲がしっくりいかなかったのにも似ている。わが社の場合でも、久村と大屋の間が円満に調節されなかったところに、戦後の斜陽化の一つの根源がある」と、当時を総括している。大屋は強烈かつ個性的な経営者で「和気あいあいなんかで経営なんかできるか」という名言を残しているほどだが、そういう社長だからこそ、こういうものが出たのだろう。
「社史は、分厚く、重く、読む気がしない」?
確かに、昔の社史はページ数が多く重厚なものが目立った。例えば、『山一證券史』(1958年。「60年史」、B5判・1346ページ)、『兵庫相互銀行50年史』(1962年、B5判・1639ページ)、『麻生百年史』(麻生セメント、1975年、B5判・1563ページ)など、1000ページを優に超すものが少なくなかったし、大部分の社史が2.5kg前後と、百科事典より重かった。これまでに出た社史で一番重いのは、新日本製鐵(現・日本製鉄)が八幡製鐵と富士製鐵合併から10年後に出した『炎とともに』(1981年)だろう。『八幡製鐵株式會社史』(961p)、『富士製鐵株式會社史』(934p)、『新日本製鐵株式会社十年史』(671p)の3冊セットで総ページ数2566ペ-ジ、総重量は7.5kgで、社員が関係先に寄贈するために持ち歩くことも困難だったという。
しかし、その後、社史のページ数は少なくなり、用紙も薄いものを使うなど、ボリュームを圧縮しており、2000年に私が1980年代以降に刊行された社史のページ数を詳細に調べたところ、平均270ページ程度と、普通の本と変らなかった。装丁も明るく、スッキリしたデザインのものが目立つ。これは“周年記念の引き出物”ではなく、“読んでもらうことを主眼にした”ことの証しといえよう。
とはいえ、薄ければいいというわけでもない。なぜなら、会社の歴史(特に、重要な経営判断など)を詳しく分かりやすく伝えようとすれば、多くの字数、ページ数が必要だからだ。
社史の悪口を言っている人、社史にネガティブな印象・評価を持っている人は、社史を読んだこともない人である。実際、社史を読んでみると、「こんなことあり得ない!」と思わず叫びたくなるような意外な話、「ホー、そんな見方があったのか」という興味深いエピソードがいっぱいある。現在まで続く有名企業の社史には、ユニークなものが多数存在する。創業者のアイデアのひらめき、独特の観察力や着眼点、ニッチ分野や未開拓分野を見つける力、的確に将来の社会を思い描き、それに向かって突き進む姿、運命を決めた決断etc.・・・。先人がやってきたことに深く感じ入り、また、驚かされる。小さな家内工業的会社が今日の大企業に発展した理由、現代に通じる経営手法などが、自然に伝わってくる。
社史には経済小説顔負けの面白さがある。しかも、経営理論や仮定の話ではなく、経営陣はどういう経営戦略を取り、環境変化にどう対応したか、社員たちはどうしたかなど、その会社で実際にあったことを具体的に書いている。同じ会社・同じ歴史は1つもない。汲めども尽きぬ面白さ、そして、経営の生きた教科書――それが「社史」だ。
現在まで続く有名企業の履歴書にはユニークなものが多数存在する。社史研究家である村橋勝子が多くの社史を読んで発見した、創業者や事業、戦略の意外なルーツを取り上げるシリーズ。
- フォード社の最先端工場を目の前に自信喪失 造船会社が歩んだ「いすゞ自動車」を生むまでの波乱の道
- 富士フイルム、国産化へのいばらの道 世界最強フィルムメーカー・米コダックとの「因縁の70年」を振り返って
- 「雨漏り発生」「人気先行、買い気難航」…積水ハウスのプレハブ住宅販売、苦難の歩みが社史で赤裸々に語られる理由
- 大和ハウス工業の創業者、石橋信夫に「鉄パイプで建物をつくる」発想をもたらしたのは“台風”だった
- フォード社の最先端工場を目の前に自信喪失 造船会社が歩んだ「いすゞ自動車」を生むまでの波乱の道
- 富士フイルム、国産化へのいばらの道 世界最強フィルムメーカー・米コダックとの「因縁の70年」を振り返って
- 「旭硝子」として創業したAGC、三菱グループなのに社名に「三菱」を冠しなかったのはなぜか
- 非三菱グループの三菱鉛筆、知られざる“素性”と商標抹殺寸前にまで追い込まれた過去
- 蒙古民族はなぜたくましいのか? 「カルピス」生みの親が遭遇したモンゴルでの衝撃から“初恋の味”ができるまで
- 大和ハウス工業の創業者、石橋信夫に「鉄パイプで建物をつくる」発想をもたらしたのは“台風”だった
- 「旭硝子」として創業したAGC、三菱グループなのに社名に「三菱」を冠しなかったのはなぜか
- 非三菱グループの三菱鉛筆、知られざる“素性”と商標抹殺寸前にまで追い込まれた過去
- 知られざる社名の由来…なぜ薩摩で創業ではないのに「島津製作所」で、相馬さんが創業者なのに「中村屋」なのか?
- 創立記念日は「三越に商品が並んだ日」、江崎グリコ創業者・江崎利一のグリコーゲン事業化物語
- “段ボール”の名付け親、レンゴー創業者・井上貞治郎の「きんとま哲学」はなぜ生まれたのか?
- 有毒植物視される“難敵”トマトにカゴメ創業者・蟹江一太郎はどう立ち向かったのか
フォローしたコンテンツは、マイページから簡単に確認できるようになります。