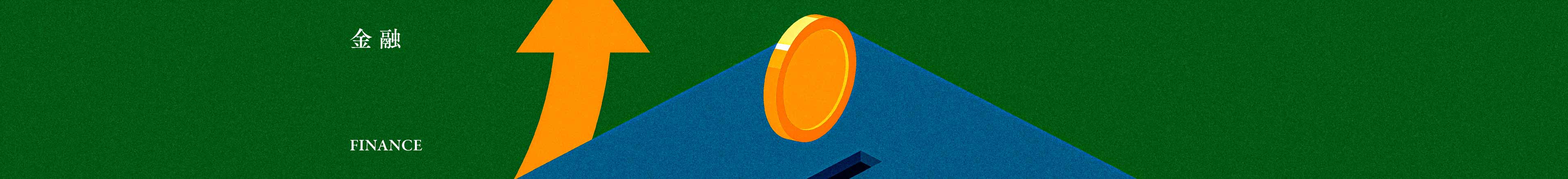野村ホールディングス 執行役員 ジェネラル・カウンセル兼コンプライアンス担当 弁護士・ニューヨーク州弁護士の森貴子氏(撮影:今祥雄)
野村ホールディングス 執行役員 ジェネラル・カウンセル兼コンプライアンス担当 弁護士・ニューヨーク州弁護士の森貴子氏(撮影:今祥雄)
グローバル化やデジタル化の波は企業の法務部門にも押し寄せ、これまで以上の知識や機能が求められるようになった。日本では弁護士資格のないスタッフが法務部に所属しているという企業も多いが、専門家以外のスタッフも含めて「強い法務部門」をつくるにはどうすればよいのか。米国勤務を経て現在は野村グループのジェネラル・カウンセル(最高法務責任者)を務め、自身も弁護士とニューヨーク州弁護士の資格を所持する森貴子氏に話を聞いた。
法律家が身近な存在、米国で受けたカルチャーショック
──森さんは米国と日本での勤務経験がありますが、それぞれの国で企業法務と法律家を取り巻く環境の違いはありますか?
 森 貴子/野村ホールディングス 執行役員 ジェネラル・カウンセル兼コンプライアンス担当 弁護士・ニューヨーク州弁護士
森 貴子/野村ホールディングス 執行役員 ジェネラル・カウンセル兼コンプライアンス担当 弁護士・ニューヨーク州弁護士1999年弁護士として法律事務所に入所。米国への留学を経て、2011年野村證券のトランザクション・リーガル部に入社。2015年よりニューヨークオフィス勤務、2019年より野村證券取引法務部長を経験する。2021年より現職。
森貴子氏(以下敬省略) 違いはあります。日本でも近年は企業内弁護士が増加傾向にあるものの、企業の法務部門には弁護士資格を持たない社員も多く所属し活躍をしています。
一方、米国の企業では、インハウスローヤー(法律事務所以外の一般企業や組織に所属して働く弁護士)の存在は当たり前で、企業の中にそれぞれの分野ごとに専門弁護士がいるほど法律家が身近な存在です。私も初めて米国留学したときは環境の違いにカルチャーショックを受けました。ただ、おかげで企業内弁護士という働き方もあるのだと気づかされ、自分もビジネスの世界でグローバルに法律の仕事がしたいと思うきっかけになりました。
仕事は「幅広く」の日本、専門分野を「深く」の米国
──日本と米国では企業法務で働く人の仕事内容も異なるのでしょうか。
森 日本の企業法務では、例えば株主総会対応から新規ビジネスの法的リスク相談まで、特定の分野にとどまらず企業内の法務に関するさまざまな業務を幅広く担当して経験を重ねていく傾向があります。一方、米国では専門分野ごとに弁護士がいて、自分の担当分野の仕事を深く極めていく傾向があります。どちらがより優れているということではなく、環境やキャリアに関する考え方に違いがあると理解しています。
ただし、米国でも日本でもコミュニケーション能力が求められる点は共通しています。企業の法務部では企業内外のさまざまな関係者と対話をしながら状況を把握して、法的な問題やリスクを分析し、それを法律の専門家ではない相手も含めて説明し、利害関係を調整する機会が多くあります。そのため、法的専門性を裏付けにしたコミュニケーションを通じて相手の状況を正確に把握する力や、社内外の人と対話する力が求められます。