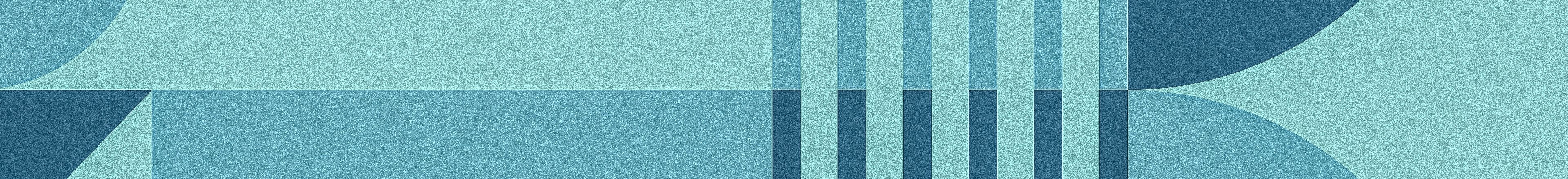船会社として自然にやっていた取り組みがDXだった
船のIoTに早くから注目し、デジタルデータの有効活用に努めてきた日本郵船。2019年には『日経コンピュータ』主宰の「IT Japan Award」で、デジタルデータにより安全運航を図る「船舶IoT」がグランプリに輝くなど、DX活動を通じた企業価値貢献が高く評価されている。グローバルな視点を武器にデジタライゼーション化の中核を担っているのは、技術本部執行役員(DX推進グループ/イノベーション推進グループ担当)の鈴木英樹氏だ。鈴木氏に、日本郵船におけるDXの方法論を聞いた。
――日本郵船がDXに取り組んだきっかけを教えてください。
鈴木 昔から、われわれの生活の必需品である食料品や日用品、電化製品など、さまざまなものがコンテナ船によって輸送されています。今は、コンテナ船事業はOcean Network Express社に移管していますが、当社は、コンテナ船で年間何百万個というコンテナを世界中に輸送していました。安全に確実にお客さまに荷物を届けるためには、コンテナ内の荷物の状況を把握していないといけない。そのためには湿度、温度、衝撃といったさまざまなデータをとって管理する必要がありました。
例えば、“コンテナ船が冬の太平洋を航行しているとき、荷物はこのような状態で、アメリカで鉄道に乗り換えるとこのようになります”というデータを収集しておいて、お客さまから要望があると、実験施設でそれを再現して「梱包はこうした方が、より安全に荷物を運べますね」ということを提案するわけです。やはり、自分たちがサイエンティフィックにモノの流れを把握できて初めて、お客さまへの提案や相談の解決もできるのです。そういったグローバルなビジネス展開というのは、船の世界では早い時期から始められていました。それこそ手書きでデータ分析をしていたところから、徐々にデジタルツールが発達してきて取り入れていくという、われわれが自然にやっていた取り組みがDXだったということなのです。
――具体的には、どのような取り組みを行ったのですか。
鈴木 大きな取り組みとしては、2つあります。1つは「船をもっと徹底的に知ること」。具体的には、当社の技術研究開発を担うMTIという会社を、2004年に私も中核メンバーとなって設立しました。当時は航海中の船体がどのように動いて、どう気象海象の影響を受けているのかよく分かっておらず、オランダの研究機関と共同でデータを取り始めたのが最初になります。その後、船内の荷物の状態だけでなく、船体が波の影響をどう受けて、エンジンの状態がどうだ、といったことも含めてさまざまな船のデータをとり始めました。それを続けていく中で、2008年ごろから「船舶IoT」(運航船のエンジンや各種装置に搭載されたセンサーなどからデータを収集し、安全運航に活用するプロジェクト)SIMS(船舶データをリアルタイムで収集・解析できるシステム)がスタートしました。その成果が「IT Japan Award 2019」でのグランプリ受賞につながったと思います。
もう1つの取り組みは「物流の見える化」。MTI設立当時、世間ではICタグが注目を浴びていたのですが、この領域ならば世界に伍していけるという思いもあり、幸運にもEPCグローバルから物流部界の議長をやってほしいという依頼まで受けました。今の経済産業省が「日本が国際標準化をリードするチャンスだから引き受けてほしい」と、実証実験などの予算を工面してくれまして。そのときの数え切れないほどの実証実験が、物流の可視化につながりました。
 丸の内(東京都千代田区)にある日本郵船の本社
丸の内(東京都千代田区)にある日本郵船の本社