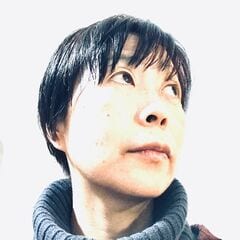2009年ソニー株式会社入社。R&Dでデバイス開発に従事した後、同僚と社内新規事業提案制度を利用してライフスタイル製品を立ち上げ。2016年退社後は、フリーランスとして活動し、3 年で50 の新規事業プロジェクトを伴走し、近年は社会課題のテーマに積極的に参画。自身も婦人科系疾患や流産、不妊治療経験を経て、患者が治療を体系的に理解するための形式知化、治療のデータエビデンスへのアクセサビリティに課題を感じ、患者に寄り添うサービスを作りたく本事業を企画。東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻修了、工学修士。
2009年ソニー株式会社入社。R&Dでデバイス開発に従事した後、同僚と社内新規事業提案制度を利用してライフスタイル製品を立ち上げ。2016年退社後は、フリーランスとして活動し、3 年で50 の新規事業プロジェクトを伴走し、近年は社会課題のテーマに積極的に参画。自身も婦人科系疾患や流産、不妊治療経験を経て、患者が治療を体系的に理解するための形式知化、治療のデータエビデンスへのアクセサビリティに課題を感じ、患者に寄り添うサービスを作りたく本事業を企画。東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻修了、工学修士。
「cocoromi」は不妊治療における情報を当事者自身が蓄積し、活用できるデータベースサービス。従来の不妊治療の課題をデータの力で解決したいと、vivola 角田夕香里氏が2020年に立ち上げたものだ。cocoromiが目指すことと、さらにその先に見ている未来について聞いた。
きっかけは「客観的な情報が欲しい」という自身のニーズ
不妊治療はまだまだセンシティブな領域で、当事者が治療を受けていることを周囲に話すことが少なかったり、周りもタブー扱いしてしまうため、当事者以外は情報に接することが圧倒的に少ない。角田氏自身、不妊治療を始めた際に感じたのは"情報弱者になったような感覚"だったという。
多くの場合、自分の状況を把握する意味で、どういう治療をすることになるのか、費用はどれくらいかかるのか、似た条件で同じような治療を行っている人はどのくらいの期間で成功するのかを知りたいと思うはずだ。しかし、そもそもの情報がない。あったとしても、ブログやInstagramなどSNSで交わされる属人的な情報で、角田氏が求めていたのはもっと客観的なもの、治療データとして扱える情報だった。
そこで、自分で集めていくことになる。Instagramを見ると、「#妊活アカウント」「#妊活記録」などのハッシュタグで自身の検査データをアップしていたり、タグで検索しながら、自分と似た環境で妊活をしている人を探すというユーザーの行動がある。そうした情報を手元のExcelでデータ化していったのだ。最初は自分のためだけに、300人分くらいの治療データを収集し、そのデータを見ながら次にどのような治療をしようかとはじき出していた。そのことをSNSで発信すると大きな反響があったという。
角田 もちろん、診療行為はできないのですが、ただ、300人のデータから、こんな治療をされている方がいるとか、年齢や子宮内膜症といったような疾患で引いてみると、こんな治療をして成功しているようです、などと発信していったときに、私も見てほしいみたいな形で反応がありました。それであれば、きちんとシステムに落として、皆さんに届くような形でしっかりサービスを作りたいと思って、やり始めたという感じです。
Instagram上で点として存在する情報を集めて、データ化することで参照可能な形にする。そこには角田氏の明確な意図がある。治療はもちろん、医師とともに進めていくが、医師と患者という関係ではどうしても情報の非対称性が生じる。自分がどういう治療を受ければいいかを客観的なデータで判断したい、と。
不妊治療に関する相談プラットフォームなど、心のケアをサポートするサービスや、自分のデータを記録していくサービスは既に世の中にあったが、欲しいのは、年齢や疾患、治療履歴、検査内容・検査値などさまざまなパラメーターを持つ大量のデータ群の中から自分に合ったものを抽出し、客観的な情報として届けてくれるというサービス。角田氏は当初、このアイデアをリソースのある大手企業に持ち込んだが、ニッチ過ぎる、スケールしないのではないかと、難色を示されたという。ただ、生殖医療を専門とする齊藤英和先生という理解者との出会いもあり、それなら自分で・・・となったのが、サービスを立ち上げた経緯だ。
不妊治療の課題は「リテラシー」と「仕事との両立」
現在、cocoromiが提供する機能は大きく3つ。①自分の治療の記録、②統計データから自分と近いもの(同質データ)を表示する、③コミュニティ だ。まず、会員はアカウント登録し、自身のデータを入力していく。ちなみに、病院名は登録するが、アカウントと本名のひも付けはしていない。
 20代から40代のデータを元にした統計データから、治療期間、治療費用、排卵の回数、移植の回数などの分布図を見ることができる。また、同質として定義する項目が一致するカップルをデータベースから拾ってくる。つまり、統計データとは別に自分の近い条件の人の情報を比較して見ることができる
20代から40代のデータを元にした統計データから、治療期間、治療費用、排卵の回数、移植の回数などの分布図を見ることができる。また、同質として定義する項目が一致するカップルをデータベースから拾ってくる。つまり、統計データとは別に自分の近い条件の人の情報を比較して見ることができる
不妊治療の課題として、まず患者のリテラシーの問題がある。不妊治療は基本的に自費診療で進んできた、ある種、特殊な領域。内科や外科のように(保険適用の範囲であれば)どの病院に行ってもある程度は同じレベルの医療が受けられるという世界ではない。つまり、病院ごとに治療方針や治療費用が異なってくる。リテラシーが低い状態で不妊治療を始めてしまうと、自分に合わない治療を続けてしまうことにもなりかねない。そうした意味で、患者の立場で最初に病院を選ぶためのリテラシーも必要だし、自分の治療計画を判断するためのリテラシーも必要となる。
そうでないと、知識が全くない中で医師に言われた治療を理解しないまま自費診療で数百万円という金額を支払っていくことになる。しかも、体外受精の成功率はまだ35歳で20%程度の医療行為であり、最終的には確率の話になってしまうもの。だから、患者自身のメンタルケアとしても知識を身に付けることが重要で、自分が何の治療をしていて、それがどれくらいの確率の治療なのかを知ることで、治療に対する覚悟が違ってくるし、結果の受け止め方もかなり異なってくる。
cocoromiでは会員自らが検査結果を入力する。最初は知識がなくても、入力工程を通し、検査データの意味を考えたりすることで徐々にリテラシーを身に付けていく。また、同士が交流できるようコミュニティ機能を用意することで、リテラシーの底上げ、知識の循環を狙っている(ただ、現状、日々の入力負荷がかかっていることは確かで、そのあたりは入力に関するインセンティブ設計に一工夫入れることを考えているという)
ここで気になるのが、検査結果など多くは病院側で管理し、患者は自由にできないのではないかということだが、この点、不妊治療の場合、自費診療のため、クリアできている部分が大きい。不妊治療の初診で行う検査は1年以内であれば転院先でも使えるなど、費用的にも身体的にもなるべく負荷を減らす努力がされている病院も多いという。
もう1つ、不妊治療の課題として挙げられるのが、仕事との両立だ。治療期間が1、2カ月であれば通院頻度が高くても、なんとか我慢ができるかもしれない。だが、どうしても不妊治療は長期化する。実際、仕事と両立できず、不妊治療をする2割の人が退職しているという。vivolaが把握しているデータでも平均25カ月間の治療で成功という状況で、5年、6年続けている人も多い。そして、もちろん、成功しないまま不妊治療から卒業していく人もいる。角田氏はその点においても、データできちんとエビデンスを伝えるべきだとする。
角田 高齢の芸能人が出産しているニュースを見てしまうと、45歳でも普通に妊娠できるのだなと思ってしまうかもしれません。しかし、年齢が高くなると、残念ながら体外受精の成功率は本当に低い。45歳になると一桁の数字になってきます。うまくいっているのは、本当にレアケースです。90%の人は泣く泣く卒業されているということも、その事実をしっかりデータとして伝えていかなくてはいけないと思っています。覚悟と、そしてこれだけの費用と期間、労力をかけて自分は治療しているのだということも認識していただく。まずは、そのためのベースをつくりたいと思っています。
その上で、判断の1つに使っていただく。例えば、排卵を促す卵巣刺激法には大きく分けると低刺激と高刺激の2種類がありますが、このクリニックでは低刺激法しかやらないけれど、同質データで見ると高刺激の方が自分には合っているのではないかと分かったりします。じゃあ、転院するかどうか先生に相談してみよう、となるわけですが、ここまでにはまだ2ステップはあり、まずメンタルヘルスをケアするとことができ、ご自身の気持ちが整って初めて、データ活用の段階になるかなと思っています。

日本の生殖医療にはそもそもの"分析できるデータ"がない
今、日本で不妊治療を受けている患者は50万人いるといわれる。「不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は5.5組に1組の割合」という数字もある(国立社会保障・人口問題研究所の「2015年社会保障・人口問題基本調査」による)。
しかし、一方で日本の生殖医療は非常に成績が悪い。2016年に発表されたデータでは、グローバルにみても日本は体外受精の件数が最も多いにもかかわらず、採卵当たりの治療成績でいうと6%。これは世界平均の20%に対して、非常に低い値だ。その背景として、角田氏は、日本の女性が治療を開始する年齢が高過ぎることも大きな1つの要因だが、情報がしっかり伝わっていないこと、日本の生殖医療の現状をしっかり分析できるデータベースがないところも課題だと捉えている。
角田 例えば、アメリカには生殖医療に関する詳しいデータを集めている第三者機関があります。アメリカの仕組みがどうなっているかというと、一般不妊といわれるタイミング法や不妊治療の最初のステップとして行われる治療はかかりつけ医が行うことが多く、そこからステップアップして体外受精までやろうとする場合は総合病院に行って行う仕組みになっています。日本よりも病院数が少なく、その総合病院のデータを第三者機関がデータベースとして集めています。
日本は非常にもったいない。日本にもデータがあるはずなのに、詳細な治療データは集められていない。そのため、うまく治療のガイドラインが決まっていないところがありますし、自費診療ということで患者は情報弱者になってしまい、患者さんの選び方次第で結果が変わりかねない状況になっています。日本の医療技術が低いわけではありません。日本の胚の凍結技術も高く、日本独自の技術もあるので、決して低いわけではない。ですが、個々の患者に最適な治療という部分でまだ余地があると考えている。
高額な自費治療ならより自分に最適な治療が受けられると思ってしまうところだが、結果にある程度、確率が介入する点も難しい。例えば、美容整形であれば、きれいに二重施術ができる、鼻筋が通せる、という医療技術と結果の関係が分かりやすいが、不妊治療の場合は、治療を最適なものにしたとしても、どうしても確率の問題という壁がある。着床のメカニズムであったり、まだまだ生殖医療の研究が進んでいかないと越えられない壁だが、角田氏は、そこにたどり着くまでもまだまだ最適化されていないところがある、データをもって言えることはたくさんある、と言う。
サービスを作って当事者がデータを活用できるようになれば、それで終わりではなく、vivolaのゴールは不妊治療の最適化にある。実際、当初は産婦人科の医師たちに正面から「データ分析をさせてほしい」とお願いしていたというが、そこで突き当たったのは、医学と工学におけるデータの捉え方の違い。医学の世界では母集団の数を工学と同じように担保するのは大変だし、患者の背景情報等の条件をそろえるのは非常に難しい。
角田 やはりここはビッグデータがすごく効いてくる領域だと思うので、たくさんのデータを集めて新しく言えることがあるのではないかというのは、いろいろな先生方にご相談をさせていただきました。最初は難しい反応を示す先生が多かったですが、サービスとして作って、患者さんが使ってくれているアプリを見せていくと、先生方も少しずつ興味を持ってくださるようになって。最近、お会いする先生方からは、うちの病院のデータも分析してみて、と言われるようになりました。
追い風になっているのは、不妊治療の保険適用を拡大しようという流れだ。現在、2022年度からの導入を目指し、自費診療となっている体外受精などの高度な治療を保険適用の対象にする議論が進んでいる。
角田氏は、保険適用となれば、ガイドラインの順守とある程度の結果を出すことが義務として課されるのではないかと指摘する。となると、同じような治療を、成果も出ないまま、何度も繰り返している病院は残っていけなくなる可能性もある。つまり、医師の側にとってもデータ分析が重要になってくるわけで、治療の経験則に加えて、不妊治療のデータベースを見ながら、「こういう治療を2回して失敗した患者さんが、3回目にどんな治療をしたら成功に近づくのか」を考えるようになる。最終判断はもちろん医師の判断になるが、判断の一助にはなるはずだ。
生殖医療とAI、急速に増えるフェムテックのプレイヤー
既に生殖医療の分野においても、従来は人間の経験則が必須とされてきた部分にAIが入ってきている。例えば、「受精卵(胚)の培養」。体外受精でできた複数の受精卵(胚)のうち、どの胚を優先的に移植する(子宮に戻す)かは胚のグレードにより選別するが、このとき、用いるのが胚の形態評価だ。具体的には、胚培養士が目検で胚の形態の良し悪しを評価し、良いグレードの胚を子宮に戻すというフローになるが、この部分に機械学習による画像認識が導入され始めている(例えば、コーネル大学の研究チームが開発した「STORK(コウノトリ)」は培養士による評価より高い精度で胚のグレードを判別できるという)
角田 良い胚の画像認識というのが今のトレンドですが、メインのプレイヤーはどちらかというとアメリカやヨーロッパに多いですね。医療機器はやはりそちらの国の方が強いので。ドイツの医療機器メーカーが作っている培養器にももうAIの機能が付いていて、顕微鏡で自動的に育ち方も記録しながら胚のグレードを選別できる。これは日本にもかなり入ってきてはいます。
ただ、私が着目しているのはその手前です。画像認識で良い胚、悪い胚を分類できるようになってきているので、そのデータとひも付け、良い胚を作るためにどんな治療をするのかをデータで見極められるようにしたいと思っています。良い胚を作るまでの医師の細かい処方のチューニング、その結果としてのホルモン値や採卵、受精、培養の情報を分析しています 。不妊治療における個別医療の道に、少しでも可能性を示せるよう、日々切磋琢磨しています。
実際、日本のフェムテックは10年遅れているといわれるが、この半年でも関連事業を手掛ける企業はおよそ50社増。更年期や生理・PMSなど、小さなカテゴリーごとにたくさんのプレイヤーが出てきている。
法規制の問題もあるが、この点は「フェムテック振興議員連盟」など野田聖子氏を中心とした組織で議論が進んでいる。「吸水ショーツ」など新たな製品を販売する上での扱い、例えば、ナプキンと同じように医薬部外品にしないと経血の給水量がどれくらいかなどをCMで言えない。そうした、これまでなかったカテゴリーでプレイヤーたちがしっかりアピールできるように法規制を整えていこうとしている。
だが、角田氏がここで指摘するのは表面的には受け入れていても、真の意味で多様性を重視しない日本のカルチャーをどう変えていくか、だ。例えば、企業の福利厚生として不妊治療をメニューに入れようという話をしても、「個別のニーズに関しては不公平感が生じてしまうから導入できない」となってしまう。多様性の議論で重要なのは「それぞれの違いを認める、受け止めること」だけではないはず。会社の中には、介護、育児、結婚、妊活と、さまざまなライフステージにいる人たちがいるわけだから。
角田 やはり不妊治療を福利厚生の中に入れると、妊娠する、子どもを持つことを会社が推奨していると思われる、と。何かあったときのリスクが先に出てくるので、不妊治療をしている方の思いであったり、そういうアンケートを社内でとりましょうという次のフェーズに行きたいんですが、話がそこで止まってしまうところはあるかなと思います。うまく、マインドセットというかカルチャーを伝えられるといいと思っています。

vivolaでは、企業などにもしっかりリテラシーを導入していこうと、生殖医療分野の医師らと連携し、企業向けの啓発コンテンツを作っている。生殖医療の適齢期はあるという前提で自分のキャリアをどう描くかをしっかりと伝えていかないといけない、と。また、当事者以外の人たちに向け、不妊治療で何をやっているのか、どうしてこんなに会社を休まなければいけないのか、理解を促す動画もシリーズで進めている。
コロナ禍で問題として顕在化した「生理の貧困」もその一例だが、これまで女性特有の問題としてパブリックに議論されることがなかったこうしたトピックが明るみになり、議論されるようになったのは、少しずつでも進んできたといえるだろう。
オンライン診療を通じて地域間格差をなくす
現在、vivolaが進めているものの1つがオンライン診療の仕組みづくりだ。自由診療が基本となる不妊治療はやはり都市部と地方では格差が生じてしまう。実際、体外受精ができる施設は全国で618箇所あるが、そのうちの320が関東一都三県に固まっている。そのうち都内は102箇所。つまり、都市部と地方では全然見え方、治療環境が異なっている。
角田 地方は総合病院や公立病院が地域医療のハブになっていることが多いですが、生殖医療はすごく特殊なので、そもそも不妊治療が受けられる医療施設が県に1つしかない、そこまでに2、3時間かかる、交通インフラも整っていないので車で行かないといけないという患者さんがすごく多い。生殖医療というのは少子化対策、子どもを産むという意味では、国や自治体がサポートしていかなければいけない領域であり、都市部に比べて患者数の少ない地域でも、病院の質を担保するための新しい技術や設備を整える公的な補助が必要であると思っています。
弊社も今、オンライン診療の仕組みを作ろうとしていますが、それは地方の治療環境に恵まれない方をサポートするためのシステムから始めて、できれば地方の生殖医療の先生方の技術的なサポートもできればと思っています。
vivolaが進めるオンライン診療は「地域医療を生かすこと」を柱とし、地元の産科や婦人科の医師と県の生殖医療の医師が連携することで、通院頻度の高い検査は地元の産科で受け、そのデータをvivolaのデータベースを通じて生殖医療の医師が診断し、治療の方針を伝えるというもの。経済産業省の補助金に採択され、今年中に特定のエリアで実証実験に進めるよう、準備を進めている。
最後に、角田氏の考える未来の社会像について聞いた。
角田 不妊治療の領域では、期間を短くすることがすごく重要かなと思っています。どれだけ保険適用になって金銭的なサポートが得られたとしても、それが長期間続けば患者さんのメンタルヘルスは崩壊してしまうし、旦那さんとのコミュニケーションも難しくなってくるところがあるので・・・。不妊治療を始めたらもう1年で結果が出るような人が大半になるような世界に変えていきたい。その最短化を実現できるような治療のデータベースをまず絶対に作りたいと思っています。患者さんがステップアップしやすい世の中であったり、そこを支える職場環境など、啓蒙コンテンツで働き掛けながら、「本人も納得して治療を卒業していく」という世界をまず実現したいと思っています。
その先の事業として、将来的には、vivolaの事業として女性ホルモンを軸にしたライフログであったり、管理を事業として広げていきたいと言う。女性ホルモンのデータが大量に集まってくると、例えばPMSであったり、産後鬱、更年期というところの病気予測や管理につなげられる可能性がる。そこを自分でうまくコントロールできれば、世の女性たちがもっと自身らしく、納得のいくライフサイクルを歩めるようになる。