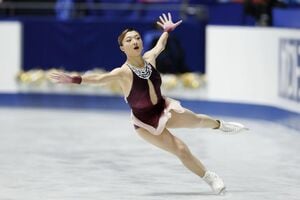2018年1月の箱根駅伝で最終10区を走り、4連覇のゴールテープを切った青山学院大の橋間貴弥選手(写真:YUTAKA/アフロスポーツ)
2018年1月の箱根駅伝で最終10区を走り、4連覇のゴールテープを切った青山学院大の橋間貴弥選手(写真:YUTAKA/アフロスポーツ)
いまやお正月の風物詩となった「箱根駅伝」。その熱い戦いは一部始終がテレビ中継され、見る者の胸を打つ。だが、熱いドラマは箱根の本番だけではない。最高の舞台に向け、選手たちは一年間、走り込んで地力をつけ、チーム内での競争を勝ち抜き、そして最高のコンディションを整えてきた。テレビには映らないその様子を、元箱根ランナーで作家の黒木亮氏が実体験を踏まえて解説する。(JBpress)
(黒木亮:作家)
今年(2019年)も箱根駅伝は「絶対王者」青山学院が本命と目されている。過去、圧倒的な強さで箱根駅伝4連覇を飾り、去る10月・11月の出雲全日本大学選抜駅伝と全日本大学駅伝でも優勝し、箱根駅伝5連覇と2度目の大学駅伝3冠に挑む。
私が箱根駅伝を走ったのは40年ほど前である(1979年3区、1980年8区)。当時から大学駅伝の最高峰だったが、日本テレビが1987年にテレビ中継を始めて以降は、一般大衆を巻き込んだ国民的行事となり、シューズやトレーニング方法などの改良と相まって、競技レベルは飛躍的に伸びた。それにともなって監督の役割も大きく変化した。一言でいうと、「選手対監督」の関係で済んでいたのが、「総合マネージメント能力」が求められる時代になった。
トレーナー、栄養士、鍼灸師まで揃えたバックアップ体制
私の現役時代は、栄養管理のようなものもなく、当時の早稲田の中村清監督は、好物の焼き芋をむしゃむしゃ食べながら「お前ら、こういう物を食うたらいかんぞ。体重が増えるからな」というくらいだった。私は何とか体重を減らそうと(体重が1kg多いと、20kmにつき1分遅くなるという感覚だった)、水を飲まないようにしていたため、大学3年の関東インカレ(30km)を脱水症状で棒に振った。
またマッサージをしてくれる専任のトレーナーなどはおらず、選手同士でやるか後輩にやってもらうしかなかった(私は慢性的な太ももの裏側の筋の故障を抱えていて、頻繁にマッサージをしないと走れなくなるので、練習後は毎日、合宿所の中をうろうろして、マッサージをしてくれる相手を探していた)。