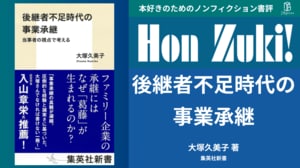「納豆といえばワラ」というのは、実は私たちの思い込みに過ぎなかった?(写真はイメージ)
「納豆といえばワラ」というのは、実は私たちの思い込みに過ぎなかった?(写真はイメージ)
(文:清水 克行)
私自身もそうだが、東日本に生まれ育った者ならば、誰しも納豆については、大なり小なり一家言あるのではないだろうか。関西人から納豆はダメだという話を聞くたびに、心のなかで密かにその味覚の狭隘さを哀れむし、たまに外国人で納豆が食べられるという人に出会うと、「なかなかやるじゃないか」と、急に親しみを覚えたりする。
その根底には、あのニオイとネバリの良さが、そう簡単によそ者にわかってたまるか、という思いがある。納豆はクセがあるだけに、他の食べ物と違って、それを好む者同士の連帯感や自尊心をつねに複雑にくすぐるもののようだ。
打ち砕かれる私たちの納豆に対する既成概念
ミャンマーの奥地でアヘン栽培に携わり、西南シルクロードの密林を象で縦断、ソマリアで氏族紛争や海賊の現場を取材するなどして数々の“レジェンド”を築いたノンフィクション作家・高野秀行の最新作『謎のアジア納豆 そして帰ってきた<日本納豆>』は、なんと、その納豆が主題である。
高野は、タイやミャンマーなどの山岳地帯で作られている<アジア納豆>の様々を精力的に取材し、こんどはそんな私たちの納豆に対する既成概念を打ち破ってくれた。
多くの日本人にとっては、そもそも日本以外の土地で納豆が作られているという事実自体が十分に驚きだろうが、それ以上に本書で驚かされるのは、その製法・調理法の多様性だ。固形化して、使う量をそのつど砕いて料理に入れるミャンマー・シャン州の「せんべい納豆」、言われないと納豆が入っていると分からないネパールの「納豆カレー」、野菜と納豆だけで芳醇な味わいを実現させた元・首狩り族の「古納豆のスープ」などなど。<アジア納豆>は、煮る・炒める・粉末化する、じつに多様な姿をしている。それに比べれば、ナマ(?)で食べることしかしない日本は、「納豆後進国」だったということを、悔しいが認めねばなるまい。