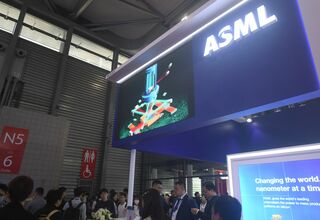ニッケイ新聞 2011年12月23日~27日
(世界各地の沖縄出身者がネットワークの構築と交流のため一堂に会した昨年の大会から)
第20回 二つの顔が盛衰する歴史、文芸復興運動に集約か
沖縄県人は「琉球ナショナリズム」という“龍”を心の中に抱えている。それが対日本政府であれ、対米国占領軍であれ、沖縄を支配する覇権に対して抵抗するときに、これが高まるようだ。
例えば、米軍基地反対運動が盛り上がったときに琉球ナショナリズムが高まって「琉球派」が台頭して「独立論」が頭をもたげ、先鋭化した活動家が旗印にする。平時には「日本ナショナリズム」が強くなり「沖縄派」が幅を利かせる。
この「琉球派」と「沖縄派」の二つの“顔”が時代状況によって盛衰することで、歴史が作られてきたようにみえる。
ウィキペディアの「琉球ナショナリズム」項目によれば、琉球大学の林泉忠准教授が07年に行なった沖縄県民意識調査では、県民のうちで自分が「日本人ではなく沖縄人である」と回答した人はなんと41・6%にものぼる。今も強い同族意識を県民が持っている。
ただし、「沖縄が独立すべきだ」と回答したのは20・6%で、大半は独立に賛成していないことが分かる。「沖縄人」としての強いアイデンティティを持っているが独立まではしたくないという志向だ。
☆ ☆
占領軍の政策のままに推移すれば、沖縄は独立国になっていた可能性があった。終戦直後の米軍の布告では日の丸の掲揚や君が代を歌ったものには罰金が科せられた。
1947年7月25日の「亜国日報」創刊号に、翁長助成元日本新聞社主(ブラジル移民)が次のような当時の辛い心境を寄せている。
「広島や長崎は原子爆弾でやられても日本であることに変りはない。広島市民も長崎市民も依然として日本人である。しかるに我々の郷里沖縄は日本から切りはなされ米軍政の下にあり(中略)、我々沖縄県人は引き続き日本人であるか、あるいは沖縄人として外国の統治下に戦前の南洋委託統治領の島民同様の取り扱いを受けるか、今その分かれ道に置かれている」(『アルゼンチン日本移民史』戦後編、34頁)。
日本復帰運動が50年代に始まると、君が代、日の丸は米軍占領への抵抗運動のシンボルとなった。60年代には日の丸掲揚運動や標準語励行運動が展開され、日本人になるために懸命に努力を続ける中で、ウチナーグチなどの伝統文化が忘れ去られていった。そのような「沖縄派」の方向性が最大限に発揮された結果、72年に念願の本土復帰が実現された。
 「ウチナーの心が見たかったら南米に行け」と語る沖縄テレビの前原信一さん
「ウチナーの心が見たかったら南米に行け」と語る沖縄テレビの前原信一さん
沖縄テレビの前原信一(まえはら・しんいち)さんは、「あの頃はみんな東京に心が向いていた」としみじみ思い出す。普通の県では生れたときから日本人だが、沖縄の戦後は日本人であることを「選んだ」世代だった。
ところが復帰後10年を経て、懸命に日本人になろうとしたストレスの反動が出たようだ。
80年代には安心感が広まり、逆に「ウチナー」というアイデンティティを求める動きが出て、90年の第1回「世界のウチナーンチュ大会」に繋がった。その中で、古い方言が残っている海外子孫に“明治の沖縄”があり、そこに学ばねばという復古志向が生れたようだ。
「沖縄の心」という振り子が右に揺れれば「琉球派」となり、左に戻せば「沖縄派」となるわけだ。今はゆり戻しの時期だが独立志向ではなく、琉球独自の伝統を復古する志向が高い、いわば琉球ルネサンス(文芸復興運動)という形だ。
大会はこの流れにのり、「国際的なアイデンティティ見直し」「グローバルなエスニック意識」という要素を含んでいる。これは琉球派と沖縄派が共に手を合わせて取り組める寛容性を持っていることで大きく盛り上がってきており、さらなる独自展開が続くだろう。
グローバル時代に合わせた県民丸ごとの自己認識練り直しの座標軸に、海外子孫がいる。