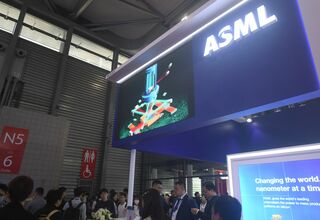沖縄にとって長年にわたる米軍の基地の存在とは、どのようなものだったのか。地上戦から米軍統治を経て1972年に日本に返還されて40年経ついまも、日本国内にある米軍基地など米軍が占有している面積のうち約74%が沖縄に集中している。
「米兵らの刑法犯罪は、復帰から2011年6月までに5726件、その1割が殺人や強姦などの凶悪犯罪。航空機事故は510件(墜落43件)」(読売新聞)だという。これらは基地があることで起きた犯罪であり事件・事故である。
沖縄本島だけを見ると、総面積の約19%を米軍の施設などが占めている。これらによってもちろん戦後、占領下の住民の暮らしの利便性は損なわれた。飛行機の騒音など環境面は言うまでもなく、根本的に町づくりは基地によって制約を受ける。
沖縄をレンタカーで回った経験のある人なら分かると思うが、カーナビが故障しているのではないかと思うほど画面に何も出てこないグレーなゾーンがしばしば登場する。これが基地の存在を示す。救急車の出動一つとってみても、こうしたゾーンを迂回しなければならない。
正当性を持たせようとする手続き重視の問題
米軍の普天間飛行場の辺野古への移設に関して、防衛省は移設した場合の環境影響評価(アセスメント)をすでに沖縄県に送り、県では7000ページに及ぶ評価書を審査し、これを基に仲井眞弘多知事が防衛省に意見を提出する運びになっている。
すでに沖縄県の環境影響評価審査会では、低周波音による周辺住民への睡眠障害などが懸念される新型垂直離着陸輸送機「MV22オスプレイ」については、評価が不十分だという指摘をしている。
これは評価のほんの1項目だが、これを投げかけた防衛省としては全体として「環境保全上、特段の支障はない」と結論づけているという。一方、仲井眞知事は評価以前の問題として「辺野古への移転反対、県外移設」という基本方針を変えていない。
なんとしても移設を実行したい国は、辺野古での建設を前提に、影響がないことを“科学的”に示すことで施策の正当性を持たせようとする。こうした形式的な政策の進め方を見て、いい加減なんとかならないかと思っている人は多いのではないだろうか。
原発建設での公開ヒアリングなど、一連の「建設ありき」を前提とした事の進め方と同じだ。形式上は“科学的”で“民主的”だが、真に批判を受け入れながらの議論は欠いたままだ。