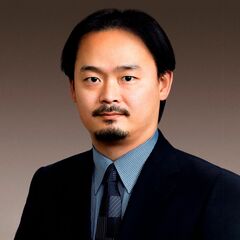ドライバーの労務管理の厳格化で「物が運ばれなくなる」と懸念された物流の2024年問題。2025年現在、物が運ばれない状況は回避できている。しかし、「2024年問題を乗り越えれば終わりというわけではない」と国際的なコンサルティングファームであるローランド・ベルガー、パートナーの小野塚征志氏は指摘する。
持続可能な物流の実現に向け、「事業者」「発荷主」「着荷主」はそれぞれ、どのように物流の効率化を図るべきか、ロジスティクスやサプライチェーンの効率化・最適化を支援する小野塚氏が解説する。
物流危機は「2024年問題を乗り越えれば終わり」ではない
物流危機ということで、昨年まで2024年問題が注目されてきました。「トラックドライバーの時間外労働時間の制限により輸送力が不足する」と懸念されていましたが、さまざまな企業努力や政府の措置がなされた結果、「物が届かない」という事態は回避されたかと思います。
しかし、物流危機は2024年問題を乗り越えれば終わりというわけではありません。
物流危機のそもそもの原因は、人手不足です。物流業界が抱えるこの問題は、今後ますます深刻化すると言われています。例えば、人手不足による需給ギャップ(輸送能力の不足)は、2024年問題の際には14.2%だったのが、2030年には34.1%に達するという試算もあります。
人手不足が進む中で、持続可能な物流を実現するには、中長期的な視点で物流の効率化を考える必要があるでしょう。
では、実際に「事業会社」「発荷主」「着荷主」それぞれの立場において、どのように物流の効率化、最適化を図っていくのが良いのでしょうか。これについては、3つのステップがあると考えています。