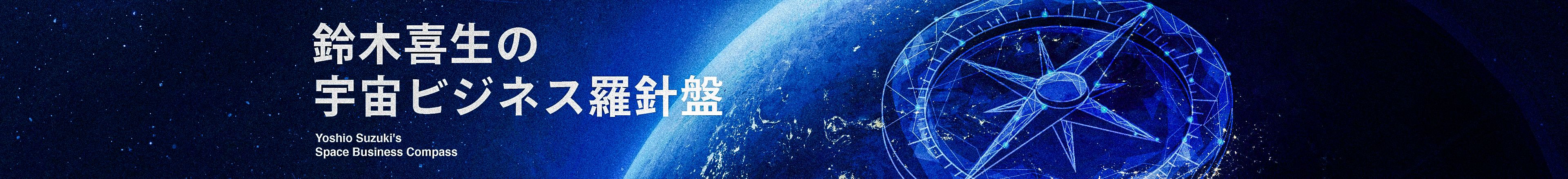高度経済成長期に敷設された長大な水道インフラが老朽化し、漏水が発生するケースは年間2万件を超えるⒸTenchijin
高度経済成長期に敷設された長大な水道インフラが老朽化し、漏水が発生するケースは年間2万件を超えるⒸTenchijin
民間企業によるロケット開発、人工衛星を利用した通信サービス、宇宙旅行など、大企業からベンチャー企業まで、世界のさまざまな企業が競争を繰り広げる宇宙産業。2040年には世界の市場規模が1兆ドルを超えるという予測もあり、成長期待がますます高まっている。本連載では、宇宙関連の著書が多数ある著述家、編集者の鈴木喜生氏が、今注目すべき世界の宇宙ビジネスの動向をタイムリーに解説。
今回は、近年注目を集めている、人工衛星を用いた水道管の保全サービスを紹介する。果たして、水道管の老朽化および漏水リスクといったインフラ危機を抱える自治体にとって、救世主となるのか?
崩壊しつつある国内水道インフラ
2025年1月に埼玉県八潮市で道路陥没事故が発生し、2月には所沢、4月には京都で上水道管が破裂するなど、上下水道の保全管理に対する危機感が全国的に高まっている。
日本列島に張り巡らされた上水道管の総延長は、地球18.5周分に相当する74万kmに達し、そのうち地球4周分にあたる17万kmが、2022年の時点で法定耐用年数である40年を経過している。
また、漏水事故の原因は水道管の老朽化だけではない。砂質地盤や軟弱地盤では耐用年数よりも早くラインが破損することがある。こうして発生する漏水事故は、年間2万件以上に上る。
水道管からの水漏れを調査する際には通常、「音聴棒」と呼ばれるツールが使用されるが、地中のかすかな漏水音を探るため、その作業は騒音のない深夜に限られ、結果的に多くの人員と時間が必要となる。人口の減少によって水道事業による収益が減少している地域も多く、何より保守すべきエリアが広すぎるため、予算が確保できない自治体も多い。
こうした状況を打開する手段として、近年では人工衛星を活用した水道管の保全サービスが注目を集めている。地球を周回する軌道から衛星によって地表を観測し、水道管が敷設された場所の地面のコンディションを見極めることによって、保全すべきエリアを絞り込んで作業効率を劇的に高めるのだ。