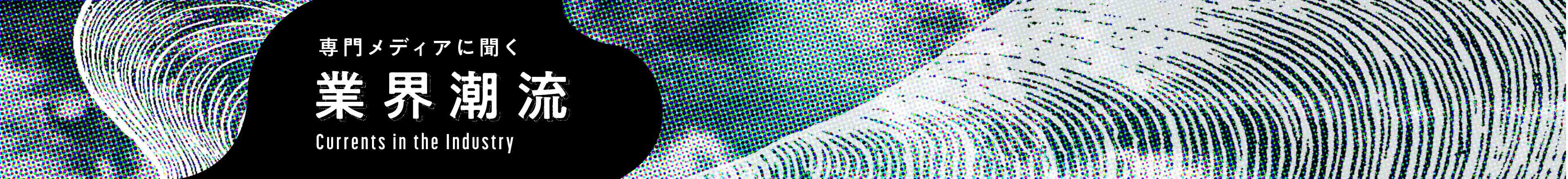Champiofoto /Shutterstock.com
Champiofoto /Shutterstock.com
2024年5月に公布された改正物流効率化法で、2028年度までに全運行の50%について、1運行当たりの荷待ち・荷役時間を2時間以内に短縮することが示された。時間のかかる従来のバラ積み、バラ降ろしを続けるのが難しくなる中、「パレット輸送」導入が急務となっている。
製品サイズの変更や独自規格のパレットを開発する荷主企業の動きについて、物流メディア「ロジビズ・オンライン」編集長、『月刊ロジスティクス・ビジネス』副編集長の藤原秀行氏に聞いた。
改正物流効率化法は事実上の「バラ積み禁止令」
──2024年5月に公布された改正物流効率化法は、物流業界にどのような影響を与えるのでしょうか。
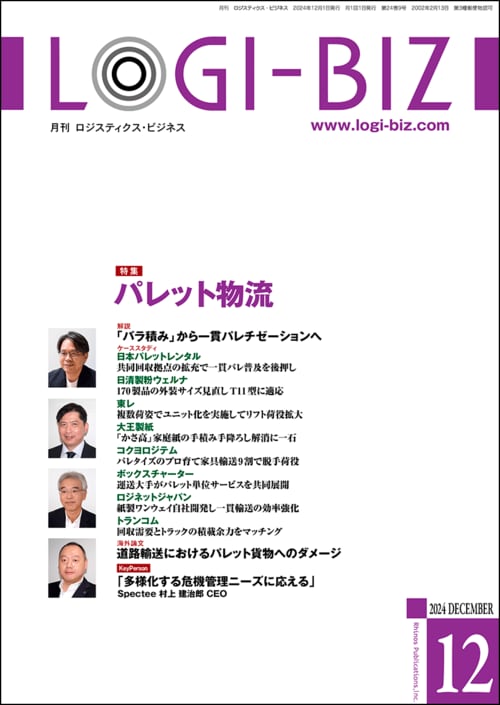 【月刊ロジスティクス・ビジネス】
【月刊ロジスティクス・ビジネス】2001年に創刊したロジスティクス管理の専門誌。 一般経済紙よりも深く、物流業界紙よりも広い視野から、独自のビジネス情報を発信。
藤原秀行氏(以下敬称略) 今回の改正のポイントの一つは、物流センターなどでの荷待ち、荷役の時間を削減するために、物流にパレットを使うことを促している点です。2028年度までに全体の5割の運行について、3時間と推計されている1運行当たりの荷待ち・荷役時間を2時間以内に短縮することを挙げています。これにより、バラ積み、バラ降ろしをもはや続けられなくなる事業者は増え、「パレット輸送」の導入が急務となっています。
形や大きさの異なる段ボール箱などに入った荷物を手作業で積み込み、積み降ろしするバラ積み・バラ降ろしに比べると、規格が標準化されたパレットを利用した場合、ドライバーの拘束時間が31%も削減できるとか、荷物の積み降ろし時間が75%短縮できるという調査報告もあります。
改正法が施行されると、一定規模以上の事業者は改善計画を作成して国に報告しなければならない上に、計画がきちんと進んでいるかどうかも定期的に報告することが義務付けられます。その義務を果たす上でパレットの利用は非常に有効と考えられますので、少なくとも一定規模以上の事業者はパレットを使用せざるを得なくなると見られます。
日本では1960年代から物流にパレットが使われるようになりました。1970年には、サイズが1100mm×1100mmのT11型パレットが日本産業規格(JIS)規格になっています。このTは「一貫輸送」という意味の「Through-transit」の頭文字をとったものです。
同型・同サイズのパレットに荷物を入れてトラックなどに積めば積載効率がよくなりますし、フォークリフトを使って積み降ろしができるので、物流の効率化に大きな効果があるとされています。