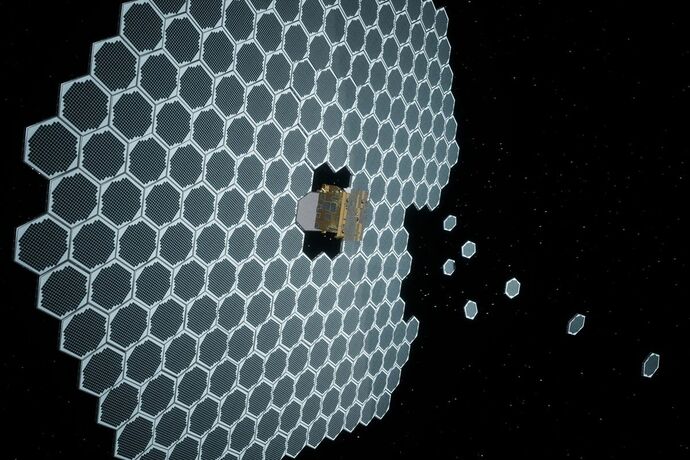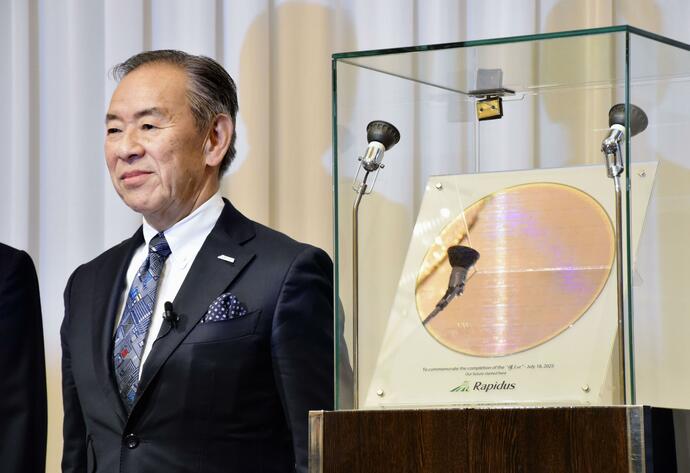品質不適切行為、防ぐために何をしているか
では、このような品質不適切行為の予防のための対策や機能強化、体制の見直しなどに多くの企業が取り組んでいるかというと、それほど多くはないようにも感じている。世の中で問題が発生してもそれは対岸の火事なのか?決して問題がないというわけでもないようでもあり、対外の火事と見做(みな)しているわけでもないようである。JMACにて品質保証実態調査を実施したが、なんらかの懸念事項や可能性を否定できず不安を感じている企業が一定数あるという調査結果も出ている。
改善、改革の必要性は理解されている一方で、なかなか取り組みにくいテーマであるということだろうか。確かに全社的に声を大にして「問題がある。改革が必要だ」とは言いにくいとは思うが、啓発的活動(品質意識の周知活動)にとどまってしまわないようにする必要性があると考える。意識改革が根底に必要ではあるが、目に見えるしくみの強化改善、組織の役割と責任の見直し、自浄作用が働くようなチェック活動やガバナンスなどの取り組みが、意識改革に大きく作用すると考える。
今一度、後遺症の怖さを考え、ワーストケースも想像してみてもらいたい。お客さまにとって、そして何より自分たちの会社にとって、従業員もマネジメント層も真に安心できる絶対品質保証を考えるべきである。品質不適切行為の予防は、対象とする業務の範囲は大変広いが、無理難題な問題ではない。これらの問題に過剰におびえることはないが、「うちの会社は絶対大丈夫」と自信を持って言えるだけの根拠は持ちたい。事件・事故が起きてしまってからでは後悔してもしきれないのである。

コンサルタント 安孫子靖生(あびこ やすお)
生産コンサルティング事業本部
シニア・コンサルタント
品質の領域を中心としたコンサルティング活動を展開、品質保証体制の構築、品質マネジメントシステムの構築、改善、品質管理改善、業務プロセス改善、ISO9001・IATF16949・ISO13485などの導入支援などを専門としている。製造業をはじめさまざまな業界での経験を有し、営業、設計開発、製造のプロセスの連携を重視した品質マネジメントを目指し、改革立案、推進指導、各種研修を展開している。