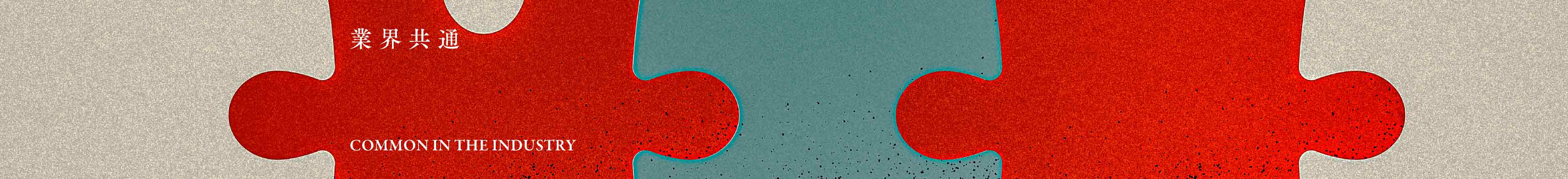多くの大企業がデジタルプロダクトを立ち上げている。うまく展開している企業がある一方で、思うような成果が出ていない企業も多い。背景には、既存事業と同じ手法でデジタルプロダクトを企画・運営している現状がありそうだ。ともすると、プロダクトの立ち上げ(ローンチ)が重視され、その後の維持拡大という本来の目的が軽視されがちな傾向も見て取れる。
成功しているデジタル由来のスタートアップ企業と大企業のデジタルプロダクトは何が違うのだろうか。リクルートで「カーセンサー」などの従来の紙媒体事業をウェブサービスに発展させてきた反中望氏と、サプリメント販売と並行して運動記録を健康ポイントとしてためられるアプリ「Comado(コマド)」を展開するサントリーウエルネスの小林俊太郎・岩佐浩徳の両氏が、大企業で起こりがちな課題と解決策について語った。
本稿は2024年2月6日に行われたビービット主催のオンラインセミナー「大企業デジタルプロダクトの光と影―DXとPdMの奇妙な関係」の内容を採録したものです。
メーカー思考とスタートアップ思考
 藤井 保文/ビービット 執行役員CCO(Chief Communication Officer)
藤井 保文/ビービット 執行役員CCO(Chief Communication Officer)東京大学大学院修了。上海・台北・東京を拠点に活動。国内外のUX思想を探究し、実践者として企業・政府へのアドバイザリーに取り組む。AIやスマートシティ、メディアや文化の専門家とも意見を交わし、人と社会の新しい在り方を模索し続けている。 著作『アフターデジタル』シリーズ(日経BP)は累計22万部。最新作『ジャーニーシフト』では、東南アジアのOMO、地方創生、Web3など最新事例を紐解き、アフターデジタル以降の「提供価値」の変質について解説している。 ニュースレター「After Digital Inspiration Letter」では、UXやビジネス、マーケティング、カルチャーの最新情報を発信中。
https://www.bebit.co.jp/blog/all/newsletter/
大企業がデジタルプロダクトを立ち上げる際、ローンチそのものがゴールになっているケースが見られる――。ビービット執行役員CCOの藤井保文氏はこう強調する。例えば数年間、魂を込めてサービスを作ってローンチしたチームがその瞬間に解散し、全然関係ない人たちがやってきて運用を始める。するとサービスの「魂」もなくなってしまう。予算配分も同様で、プロダクトが拡大していけば「予算規模は大きくなっていき、(携わる)人も多くなってくるはずだが、初めからローンチ後の予算が削られていく構造になっている」(藤井氏)。
こうした考え方を藤井氏は「メーカー思考」と「スタートアップ思考」に分類した。前者は「時間も予算も大量にかけてプロダクトを作り、販売はマーケティング費用を使い売り上げで利益を出していく構造」と分析する。
一方、スタートアップ思考は「ローンチしてから成長させていくところが命」。全てのメンバーが「みんなでこのサービスを大きくするぞ。成長させれば後からマネタイズがついてくる」というモチベーションで、自分ごととして取り組む。こうした企業は、ローンチまでさほど時間をかけず、市場の反応を見ながら「PMF(プロダクトマーケットフィット)」で市場とプロダクトを擦り合わせていく。