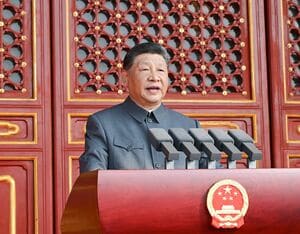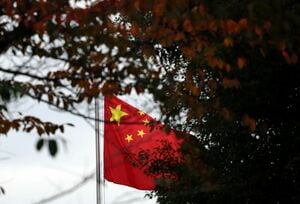個人的な好き嫌いは別として、中国との経済関係の重要性を否定する日本人はいないはずである。日本にとって中国は最大の貿易相手国であり、日本企業の対外直接投資が最も集中している国が中国である。すなわち、日本にとり中国は最重要の工場であり、最大の市場でもある。
対中関係の重要性は、国際貿易や直接投資の面だけに限らず、安全保障の観点からも重要である。むろん、中国にとっても対日関係の重要性は同じだ。
しかし、これまでの10年間を振り返れば、日中関係は必ずしも順調に発展していない。歴史認識の違いや領土・領海の所有権を巡る対立により、日中関係はぎくしゃくしている。日中両政府はこれらの問題に冷静に対処しているが、アンケート調査によれば両国の国民感情はどんどん悪化している。
仮面をかぶっていた日中の蜜月時代
小泉純一郎元総理の時代に、日中関係は大きな転換点を迎えた。それまで両国は互いに「我慢」していたが、その頃から言うべきことをはっきりと言うようになった。
本来、国益が関わっていれば、言うべきことを言うのは当たり前である。では、なぜそれまで両国は言うべきことをはっきり言わなかったのだろうか。その背景には、かつての戦争という負の遺産があったからである。
第2次世界大戦が終わった直後から、中国は内戦状態に突入した。毛沢東が政権を取ったときから、世界は社会主義陣営と資本主義・民主主義陣営に二分され、冷戦時代を迎えた。その中で、日本と中国は当事者としてきちんとした対話を行うことができなかった。戦後処理はアメリカ主導のもとで進められたが、日本と中国は必ずしも納得していないところが多い。
1970年代に入り、冷戦の基本的な構図が大きく変化した。中ソは激しく対立し、中国はソ連に対抗するために、日本とアメリカに歩み寄る戦略に変わった。
だが、そうした中で日本と中国は、戦後処理に関するきちんとした話し合いを行わないまま、相手との関係を互いに政治的に利用して関係回復に突き進んだ。あの時代の日中関係のキーワードは「曖昧」だった。
経済発展が大きく遅れた中国にとって、日本との関係改善は経済のキャッチアップにおいて必要不可欠だった。一方、日本にとっても、中国との関係を改善することは日本の国益にかなうだけでなく、当時の日本の国民感情にも合致するものだった。日中友好を推進すれば、中国人に戦争のことを許してもらえると日本人の多くは願っていた。