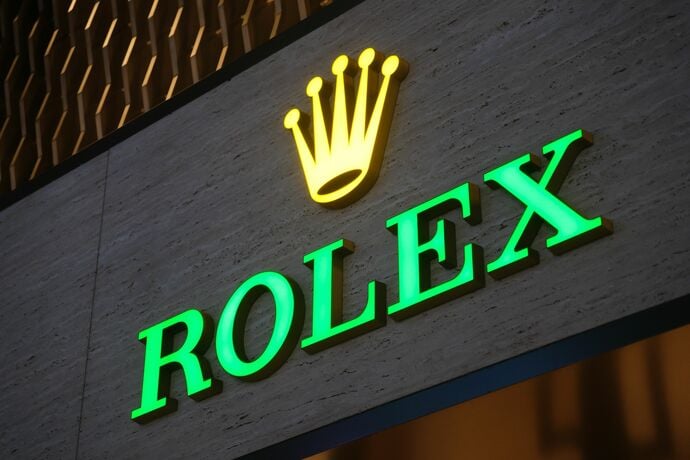BYDの記者会見 BYDがPHV日本初投入 BYDの記者会見=2025年1月24日午前、東京都江東区(出所:共同通信社)
BYDの記者会見 BYDがPHV日本初投入 BYDの記者会見=2025年1月24日午前、東京都江東区(出所:共同通信社)
2024年、電気自動車(BEV)の販売が失速する一方で、顕著な成長を遂げたのがプラグインハイブリッド車(PHEV)だ。しかし、PHEVの開発に消極的な自動車メーカーも少なくない。世界初の量産型電気自動車「i-MiEV」(アイ・ミーブ)の開発責任者・和田憲一郎氏は、「世界の自動車メーカーはPHEVの開発・販売に積極的な企業と、ほとんど関心を示さない企業に二分されている」と指摘する。PHEVに積極的に取り組む企業とそうでない企業の間には、どのような考え方の違いが存在するのか? PHEVの成長は続くのか? 和田氏が解説する。
世界初の量産型プラグインハイブリッド自動車を生み出したのはBYD
最初にPHEVについて説明したい。PHEVは、大型のバッテリーとモーター、さらにエンジンを備え、通常モーターにて走行するが、バッテリーに蓄えた電気が少なくなるとエンジンが始動して発電機として機能したり、もしくは直接エンジンを駆動力として走行できるシステムである。状況に応じてモーター+エンジンでも走行することができる。PHEVはBEVと同様に外部からバッテリーに充電可能である。
PHEVが誕生した背景には、BEVの課題解決がある。BEVの航続距離を延ばすためには、大容量のバッテリーが必要となり、その結果、車両価格が高騰する。また、充電インフラが販売地域に十分に整備されているとは言い難い。このような状況下で、BEVの電欠に対する不安を抱くユーザーに対し、バッテリー容量を抑えつつ、エンジンを搭載して発電機や駆動力として利用し、走行距離を延ばすというアイデアが生まれた。
世界で最も早くPHEVの実用化を果たしたのはBYDである。2008年に世界初の量産型PHEV「F3DM」を発表した。F3DMは、容量20kWhのバッテリーを搭載し、バッテリーのみで約60マイル(約96km)走行可能とされ、価格は14万9800元(当時約200万円)であった。ただし、BYDのガソリン車と比較すると価格が高いことから、あまり売れず2012年には販売終了している。その後、BYDは2022年3月をもってガソリン車の開発・販売を中止し、BEVとPHEVのみに経営資源を集中する戦略を取った。2024年、世界で最も売れているPHEVはBYD:秦PLUSシリーズである。