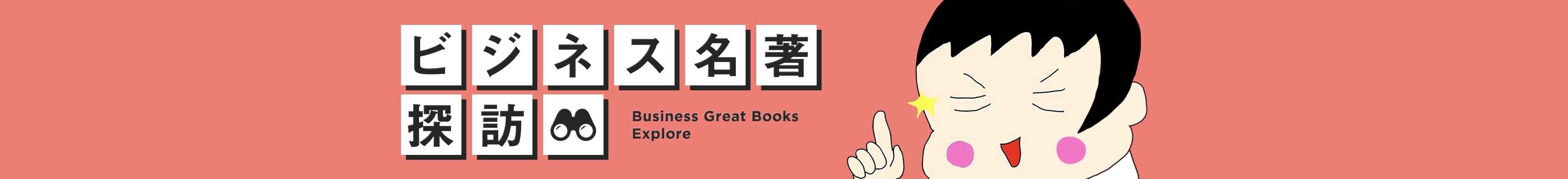『ビジョナリー・カンパニー』『マネジメント』『競争の戦略』など、ビジネスリーダーたちが「座右の書」とするビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、『見るだけでわかるビジネス書図鑑』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者で、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、多くのビジネスパーソンに読み継がれる名著を厳選。多忙な読者が名著のエッセンスを素早くつかめるよう、ツボを押さえた解説とイラストで毎回1冊紹介する。変化が激しく、不透明な時代でも、名著を通じ、ビジネスの「定石」を知ることは、あなたの仕事にきっと役立つはずだ。
連載第4回は、マネジメントの新常識を打ち立て、世界で100万部を突破した名著『学習する組織――システム思考で未来を創造する 』(英治出版)を取り上げる。
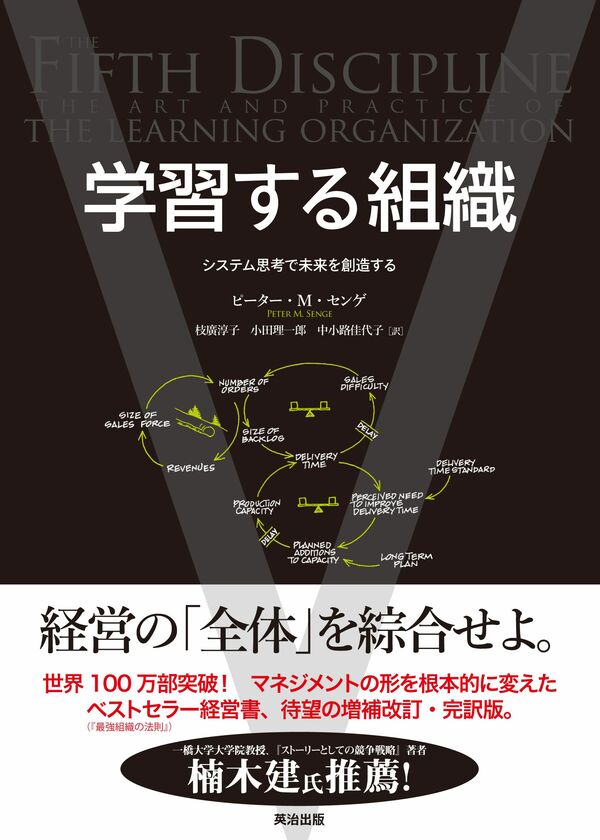 『学習する組織――システム思考で未来を創造する』(ピーター・M・センゲ著、枝廣淳子、小田理一郎、中小路佳代子訳、英治出版)、世界で100万部を超えるベストセラーとなり、1990年代にビジネス界に一大ムーブメントを巻き起こした。
『学習する組織――システム思考で未来を創造する』(ピーター・M・センゲ著、枝廣淳子、小田理一郎、中小路佳代子訳、英治出版)、世界で100万部を超えるベストセラーとなり、1990年代にビジネス界に一大ムーブメントを巻き起こした。
あなたが所属する組織で、パワハラが起きたとする。その事実が、内部告発によって明るみに出た。
当事者は、加害者であるA部長、被害者であるBさん、そして告発をしたCさんだ。
あなたの組織は、おそらくA部長とBさんの間に具体的にどんなハラスメントがあったのかを把握するだろう。そして、ハラスメントの事実が確認された時、A部長は懲戒の対象となる。
さて、一件落着・・・
としてしまっていいだろうか?
もちろん、そんなに簡単に済ませていい話ではないはずだ。
パワハラが起きたというのは、A部長の属人的な原因だけでなく、パワハラが発生してしまう構造的要因があったかもしれない。たとえば過剰な目標に対するプレッシャーなどが根底にあり、それがA部長のパワハラ的行動を促進していた可能性がある。もしくはコミュニケーション力が欠如した人であっても、実績さえあればマネジメント層に昇格してしまう制度的問題があったことも考えられる。
もしそうだとするならば、A部長を外しても、別の場所で新たなハラスメントが発生するだけだろう。
これは一例だが、このように責任が一見明確に見える事象であっても、実は複雑な因果が組み合わさって起きている可能性があるのだ。
だからこそ、私たちは何らかの出来事が起きた時、その事態に「対処」するだけではなく、しっかりと事態から「学習」をしなくてはならない。
しかし、「学習」と口で言うのは簡単だが、実際にはこれほど難しいことはない。私たちの組織は、どれだけ頑張って学ぼうとしても学べないという「学習障害」を抱えているからだ。
では、その障害の正体は何か?