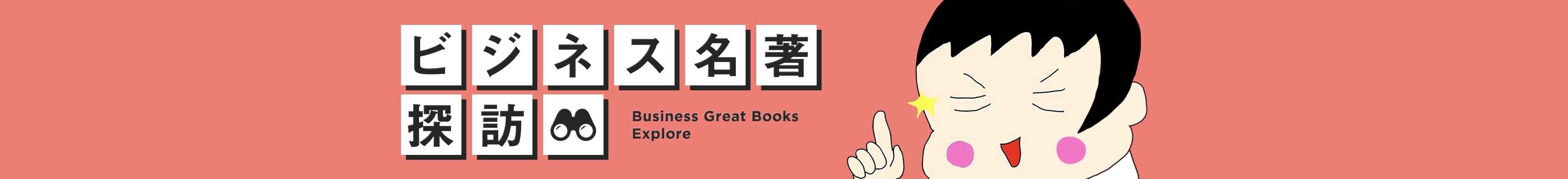ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。
今回は、1月25日に亡くなった知識経営の世界的権威・野中郁次郎氏が最後に著した『二項動態経営』などを取り上げながら、SECI(セキ)モデルや場(Ba)などの理論を振り返る。野中氏が生涯を通じて問い続けた「知」の在り方とは?
温かみと深みのあるセオリー
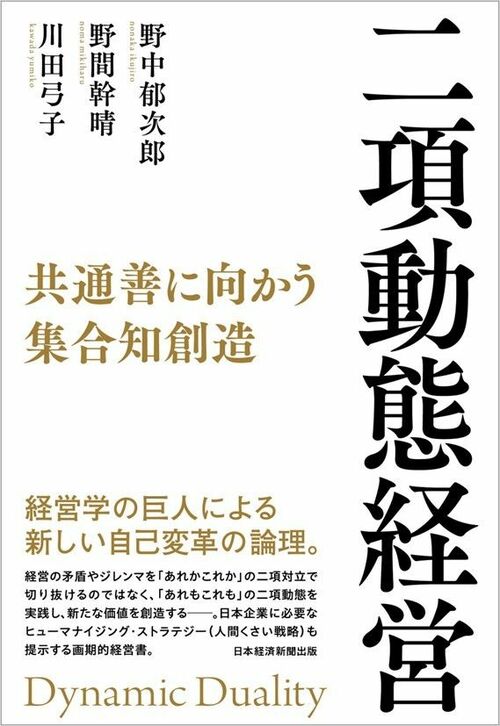 『二項動態経営』(野中郁次郎、野間幹晴、川田弓子著、日本経済新聞出版)
『二項動態経営』(野中郁次郎、野間幹晴、川田弓子著、日本経済新聞出版)
野中郁次郎氏が先日逝去された。本連載でも、『知識創造企業』(野中郁次郎、竹内弘高著、梅本勝博訳、東洋経済新報社)や『失敗の本質』(戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎著、中央公論新社)を通じて野中氏の思想を紹介させていただいた。
彼は組織の知識創造理論で世界的に知られる学者であり、日本のみならず海外でも高い評価を受けてきた人物だ。彼が提唱した知識創造モデルいわゆるSECI(セキ)モデルは、多くの企業や研究者に引用され、暗黙知と形式知の相互転換プロセスを通じて新たな知を生み出す組織のダイナミズムを明らかにした。世界に誇る日本の経営思想家だった。
彼の理論には、温かみと深みがある。おそらくそう感じるのは私だけではないだろう。本来経営理論には冷たさも温かみもないはずだが、なぜか彼の提唱するセオリーからは人間らしさを感じることができるのだ。
それは、彼が「知識とは何か」という問いに向き合い続けたことにある。この問いは、経営学の範疇を超えて、「人間とは何か」という根源的な問いに直結していく。つまり、哲学の領域にまで踏み出さない限り、答えを出すことはできないのだ。