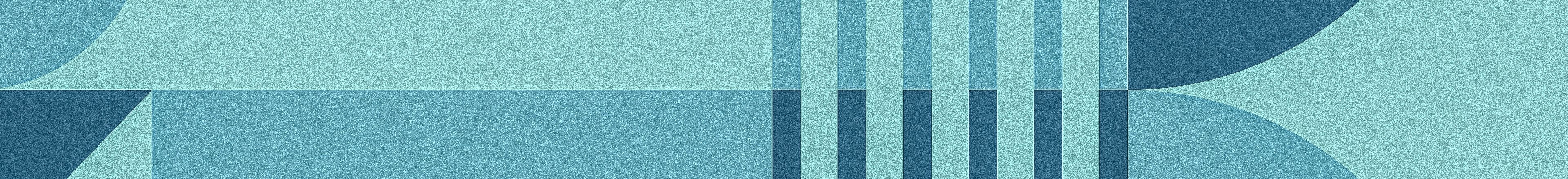マツダのシニアフェローでイノベーションを担当する人見光夫氏
マツダのシニアフェローでイノベーションを担当する人見光夫氏
苦しい経営をバネに、内燃機関の「究極の姿」を描く
マツダが起死回生となるSKYACTIV技術を全面的に搭載したSUV(スポーツ多目的車)の「CX-5」を発売したのは、10年前の2012年のことだった。それ以降、統一感や独自の世界観がある“魂動デザイン”が展開され、この年を境に同社の技術力やデザイン力の評価は一気に高まっていく。
SKYACTIVエンジンは、ガソリン車でありながらハイブリッド車に並ぶ低燃費を叩き出したことで一躍注目を集めたが、同エンジンの「生みの親」が、現在、マツダのシニアフェローでイノベーションを担当する人見光夫氏だ。同氏はこう回想する。
「1990年にバブル経済が崩壊して以降、当社は業績不振に見舞われ、1996年にはフォード社(米国)に経営権が移りました。技術者の多くはフォードのクルマと共用するエンジン開発の方に異動してしまい、私を含めたわずか30人ほどの社員が将来のエンジン開発に関わる程度だったのです」
資金難に陥っていた頃は、フルモデルチェンジの際に外観だけを変え、中身のエンジンやトランスミッション、シャーシは旧型と同一という窮余の策も強いられたという。2000年を過ぎたあたりから、ようやく開発資金も少しずつ使えるようにはなったが、当時はトヨタ自動車の「プリウス」に代表されるハイブリッドカーが台頭していた。
加えて、欧州ではより厳格な燃費規制が2012年から始まることが決まっていたが、マツダではハイブリッドや電気自動車(以下、EV)といった次世代環境車を新たに開発する余裕もなく、同業他社に対抗していくには内燃機関の環境性能を磨く以外、術がない状態だった。「環境対応技術を何も持っていないマツダ」との酷評も浴びた。
「当時、研究開発部門のトップだった金井誠太(後に会長を歴任)が『あらゆることを刷新していかねば厳しい燃費規制に対応できない』と社内に危機感を訴えたのを受け、私は超高圧縮比のガソリンエンジンを提案し、ディーゼルエンジンを含めたSKYACTIVエンジンの開発がスタートしました。それが2005年ごろのことです」(人見氏)
限られた人と開発資金の中でマツダは長期的な技術力、競合力をどう担保していくのか──。人見氏が出した答えが、「あれこれと手を出すのではなく、内燃機関改善の余地に賭けて究極の姿を描く」という“選択と集中”だった。独自価値を生むところに時間とお金を集中させてパラダイムシフトを図る狙いだ。
クルマの燃費効率を上げるには、ガソリンエンジンに取り込む混合気(空気とガソリンを混ぜた気体)を従来よりも強く圧縮することが必要だったが、その圧縮比を高めすぎると異常燃焼が発生し、かえってエンジンの出力性能が低下してしまう。ところが常識外れの圧縮比15くらいでエンジンを回してみると、普通のエンジンよりも性能は落ちたが、想像していたよりも落ちなかった。この低下分ならリカバリーできると考え、世界のどの自動車メーカーも成功していなかった超高圧縮比の手法で燃費を上げる道を選んだのである。