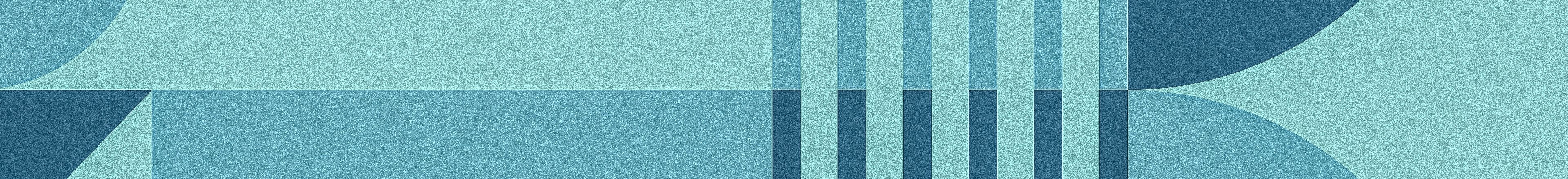株式会社KADOKAWA Connected CDO 兼 Integrated Data Service部 部長 塚本圭一郎氏。【撮影場所】ところざわサクラタウン/撮影:稲垣純也
株式会社KADOKAWA Connected CDO 兼 Integrated Data Service部 部長 塚本圭一郎氏。【撮影場所】ところざわサクラタウン/撮影:稲垣純也
KADOKAWA Connectedは、KADOKAWAグループのDX推進につながるサービスを開発・提供する戦略的な機能を持つ子会社として2019年に設立された。「JBpress」では約1年前に同社の(当時)代表取締役社長 各務茂雄氏にインタビューを行っている。そこでは同社がKADOKAWAグループとしてDXを推進する中で、「攻めのDX」「守りのDX」という表現で、多様な方向性を持ってグループを変革したいという話を紹介した。それから約1年がたち、今回、当時の目標はどれほど達成できたか、また実践した企業だけが分かる課題や大切にすべきことについて聞いた。
KADOKAWA ConnectedのDXの今
今回はKADOKAWA Connected(以降、KDX)において、DXの現場に近いChief Data Officerの塚本圭一郎氏に話を聞いた。早速、1年たってDXの成果は生まれたのか塚本氏に聞いてみた。「KADOKAWAグループで共有可能なデータ分析基盤『Trinity(トリニティ)』(グループ内のコードネーム)を2022年4月にリリースできました。僕が部長を務めるIntegrated Data Service部は、元々ドワンゴのニコニコ事業でデータ分析基盤の開発を行っていたのですが、KDX設立後に、そのノウハウをKADOKAWAグループの誰でもどの事業でも使えるようにサービス範囲を拡大するためにTrinityは開発されました」(塚本氏)
Trinityを使うことで、KADOKAWAのあまたあるコンテンツのうち、今、何がどれだけ伸びているか、期待できるかなどが数値ですぐに分かり、タイムリーかつ効率的に市場を攻めに行けるようになると塚本氏は説明する。つまり、「攻めのDX」につながると言える。
また、グループ内に複数存在するデータ分析基盤を統合することで、データエンジニアを一つの基盤に集約でき、ボリュームディスカウントの効きやすい稼働率の高い基盤システムを提供できたと言う。「そういう意味では守りのDXに近い部分も含まれています」と塚本氏は語る。
同社が目に見える形で具現化したDX施策は、Trinityというデータ分析基盤とのこと。攻めと守りの両方を可能にするとは、なかなか強力なツールといえよう。
データは大事だが「何のために、誰のために」の視点が最も大事
データ分析基盤が整ったところで、どんなデータをどう扱えばよいか、その秘訣を塚本氏に聞いた。
「データ活用って、本当にシンプルなところから始めれば良いと思います。例えば、皆さんの業務の中で、何か課題がある、心配している、もしくは頑張っていきたいという部分があると思うのですが、それを数字に直してみるんです。そして、その数字を増やすか減らすか維持するか、どれが良いかを考えることがデータ活用にとって大切なことと思います」と塚本氏は言う。
例えば、システム担当が「最近、障害が起きてシステムのダウンが多くないか?」という心配を感じたら、それを調べるという行動に移してみれば良い。最初は、手書きでいいから、障害件数と発生タイミングをExcelにでも入力する。そして、月ごとにその数がどう変化するかを見てみる。業務上、問題ある数になるか、それは下回るかを確認する。もし、超えていたら何で超えたのかという疑問から調査を進めれば良いと塚本氏は重ねる。「本当に当たり前の積み重ねが、データ活用の基本だと思っています」(塚本氏)
これは現場向けの話だが、経営向けの話も同様だと言う。経営層にとっては自社の売り上げが重要だが、その売り上げは通常、複数の事業から成っている。では、それら一つ一つの売り上げは把握しているか。また、それらの事業を構成する複数の売り上げについてはどうか。今、理解している範囲は自分が覚えられる記憶能力の範囲で止まっていないか、など正しい判断に必要なデータをしっかり把握しているか、経営者なら常に注意してほしい点だ。売り上げに関心があるのなら、売り上げと因果関係のある数字を追う必要がある。関心事と独立した形で、良さそうなKPIといった指標を定義し、そのKPIが目標値に到達すればそれで良しと思っていないかは、常に振り返りが必要と塚本氏は語る。
「データの先に、データを使って解決したいテーマがないと意味がありません。データは魔法の杖ではありません。データを取るからには、まずは現場の皆さんが解決したいことは何かを定めること。今、問題としている事象は、果たして本当に改善すべき問題なのか、そうなら改善するにはどうしたらいいのかという、問題解決の行動につながる形でデータを取り検証していくことが重要です」と塚本氏は述べる。
ただ、塚本氏も自身も含め一部の現場では、そうした視線が欠けている部分が「正直、あった」と話す。全てが理屈道理にはいかないと塚本氏は語り、今後はTrinityというデータ分析基盤を使いこなす人を増やすことで、顧客自らがテーマを定め、データを使って問題解決をしたり、新しいサービスを開発できるようにサポートしていくことが重要になるだろうと重ねる。