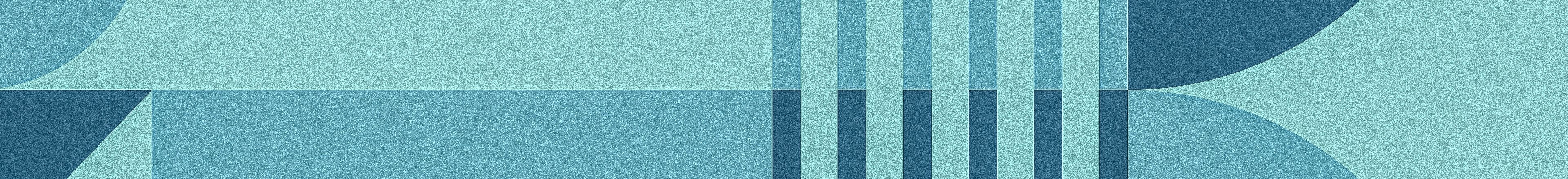北海道大学大学院工学院 合成化学工学修士(1984)。同年、味の素株式会社入社。アミノ酸事業を中心に技術畑を経験。MBA (Univ. of Southern Queensland) 取得後、ヘルスケアを主体とした事業畑に転向し、取締役 専務執行役員アミノサイエンス事業本部長時代に事業改革を実行。現在は取締役 代表執行役副社長 CDOとして全社のデジタル・トランスフォーメーションを推進中。『2000パーセントソリューション』(和訳)、We Will Make the World Green、A Strategic Approach to the Environmentally Sustainable Businessなどの著者。
北海道大学大学院工学院 合成化学工学修士(1984)。同年、味の素株式会社入社。アミノ酸事業を中心に技術畑を経験。MBA (Univ. of Southern Queensland) 取得後、ヘルスケアを主体とした事業畑に転向し、取締役 専務執行役員アミノサイエンス事業本部長時代に事業改革を実行。現在は取締役 代表執行役副社長 CDOとして全社のデジタル・トランスフォーメーションを推進中。『2000パーセントソリューション』(和訳)、We Will Make the World Green、A Strategic Approach to the Environmentally Sustainable Businessなどの著者。
味の素株式会社(以下、味の素社)では、DXに取り組むことで5年近く続いていた株価の下落を上昇に転じさせ、業績も大きく上向かせた。その取り組みを中核となり推進していたのが、代表執行役副社長でありCDOである福士博司氏だ。福士氏は技術者として味の素社に入社し、アメリカやタイにも赴任。その後、徐々に担うようになっていった経営寄りの仕事でも成果を上げた手腕が評価され、DX推進の担当になった。その福士氏に、味の素社がどのようにDXを推進していったのかを聞いた。
DX推進で意識した2つのこと
――味の素社がDXに取り組んだきっかけについて教えてください。
福士 西井が社長に就任して4年が過ぎ、5年が経っても株価の下落が止まりませんでした。過去の中期計画も、一度も達成できていなかったのです。これは業績の停滞もありましたが、主流派であり、当社をグローバル食品企業に成長させてきた人たちは、その成長に陰りが差してもなかなか自己否定できず、今までのやり方を大きく変えようとは考えられなかったわけです。
その点、私は全く違う経歴でしたので、内部者ながらもクールな目で、今の経営に欠けていることや戦略上、人事上の問題などが見えました。そこで社長に、それらの抜本的な変革が必要であると直言しました。この点をよく理解してもらえたことがきっかけです。
最終的にはDXに取り組み、これまでの中期経営計画の内容を受けてパーパス経営に切り替えました。単に「変革をする」というと抵抗が出て、内部同士の戦い、エネルギーの消耗になってしまいがちです。そこで、「この会社は社会的課題の解決のためにある」とし、社長以下、社員全員の意識が外に向くようにしました。これだと必要のない内部での戦いは起きませんし、戦略的にも目が社会的課題に向くので、非常にいい選択だったと思います。
――DXを行うにあたり意識したことはどのようなことですか。
福士 DX展開のステップについては、社外取締役である、一橋ビジネススクールの名和高司先生に相談しました。そこで2つ考えたことがあります。一つは、今さら自分たちオリジナルのステップをつくり出す必要はないということです。
グローバル企業として複数の法人を抱え、事業ラインも複数あるという当社の企業体に適していて、ステップやKPIも明確で、お互いにチェックしながらベクトルを合わせていけるような方法があれば、それを踏襲しようと考えました。そこで、名和先生が提唱するDXn.0モデルが適していると考え、採用した形です。
もう一つは、「ステップ0.0」の必要性です。全社の変革という前に、例えば、生産性の向上などの部分的な変革はどの会社も実施していると思います。当社でも、働き方改革として、テレワークや、「どこでもオフィス」などを数年間取り組んできましたので、これをストップすることなく、DXによる全社改革の前段階としてのステップ0.0としました。
働き方改革など、これまで一生懸命やってきたことを、否定して全く新しいことをやろうとしても、なかなか組織はついてきません。例えば、働き方改革で取り組んできたことは、個人、自己の働き方の変革ですので、これはずっと今後も続けていくことにしました。
ただ、これからは個人、自己だけではなく、会社組織の変革をしなくてはいけないので、ステップ0からステップ1への移行、すなわち、個人ではなく全社、組織でのオペレーションの変革に移行しようと説明しました。即ち、これまでの個人、自己のイニシアティブである働き方改革を企業変革であるDXへと関連付けたのです。
ポイントは「ハブ&スポーク」の組織をつくること
――そうして、会社の変革へとつなげていくわけですね。具体的にはどこから始めたのでしょう?
福士 まずは企業変革の大きな枠組みとして、組織や戦略の変更を考え、実行し始めましたが、気が付いたのは、通常業務だけではなく、変革プロセスにおいても、企業の執行の責任体制や取締役会、企業のガバナンスをしっかりさせないといけないということです。そうしないと、大きな変革はスムーズに進みません。
そこで、ガバナンスについては昨年から中間的段階として、指名諮問委員会等を設置しましたが、最終的に指名委員会等設置会社に移行しました。ガバナンスは人事や組織変更、戦略も関係しますので、それらをしっかり取締役会で監督できるようにしました。
執行については、社長の意思を社内外に徹底しました。社長は組織の執行のトップですから、内部だけでなく外部の人、ステークホルダーを含め、みんなが社長を見ます。そのため、まずは社長の「絶対に変革をする」という決意が必要になります。そして、目指しているのはパーパス経営であり、社会課題の解決であるということを、大きな声で社内外に発信し続ける。これが全社のDX推進の支えになるのです。
私は社長の決意、コミットメントを土台にしてDX推進組織をつくり、担当者をアサインしました。そして私が自ら変革のリーダーとなって推進したということになります。
――従業員の意識や組織の変革ではどのようなことを行いましたか?
福士 一人一人の意識改革については、従前の働き方改革でも取り組んでいました。しかし、オペレーションは個人ではできません。個人と組織を緊密にリレーションメイキングしながら同じ方向に行き、業績を上げていく。これをオペレーショナルエクセレンスとして「DX1.0」に位置付け、推進しました。
その推進のコアとなるものが2つあります。一つは、個人目標発表会で、これを全組織においてグローバルで実施するようにしました。この方法は、私自身がアミノサイエンス事業本部長時代に過去25年間、世界の各地でさまざまなファンクションで実施したもので、非常に有効であることが証明されています。特に個人のモチベーションの点でも、ベクトルを合わせるという意味でも、パフォーマンスに直結するので、それを全社展開したわけです。
もう一つはエンゲージメントサーベイをグローバルで毎年末に実施して、トレンドを追うこと。経営としては全体のトレンドなどをベンチマークして状況を見ていく必要があります。そして、各組織のPDCAを回しながらグローバルで全社的に意識の向上策を実施していきました。これは組織文化の醸成ともいえると思います。個を見ながら全体を見つつ、きちんとカルチャーを変革し、組織を変革し、結果として業績に結び付けるというサイクルです。
――これは個々の従業員にも光を当てるということですね。
福士 これは面白いので具体的にお話しします。30~40名の単位で、1人15分ほどの持ち時間で組織全体に対してプレゼンを行います。そして5分ほどの質疑応答をするわけです。それを、30人なら30回します。そのため、1日では終わらないこともありますが、こうすることで、自分たちの組織にどんな人がいるのか、どのような能力の人がいて、どういう関係性で仕事をしているのかが、把握できます。
一般的な目標制度は、上司と部下の1対1で設定するケースが多いのですが、この方式では1対1が基本の組織になってしまい、情報が伝わりにくくなります。これに対して、私が提案したモデルはハブ&スポークのようなもので、中心に上司がいて周囲に部下がいるという形です。こうすることで、上司と部下のつながりだけでなく、部下同士でもつながります。これを組織単位で推進しました。
このもう一つの効果は、このプレゼン会議を毎年、あるいは年に2回実施していくことで、人や組織の変化や成長が一目瞭然になることです。これは非常にいいことで、従来のように1対1を30回やるよりも情報量とコミュニケーション量が圧倒的に多くなり、共感が生まれるようになります。個々のデータが集団のデータとして蓄積されるわけですから、指標としても非常に有効です。
――組織変革で、難しい点はありましたか?
福士 やはり縦と横の関係は衝突します。既存の組織にはそれぞれの予算の枠組みがあり、イニシアティブがあったので、DXを推進するとなったときに、誰が主体的にやるのか、誰の責任で、誰のお金でやるのかが問題になるわけです。
組織には今までのモーメンタム(慣性)があるので、従来のものを続けようとします。既に予算化されていますし、中期計画もある中で、それを急に横軸主体にして変革するといわれても、そもそもその考え方から抵抗があるわけです。そこでリーダーシップを握るのがCDOであり、CDOに対する社長の支えになります。CDOがかなり強力なリーダーシップを発揮しないと、変革は進まないわけです。