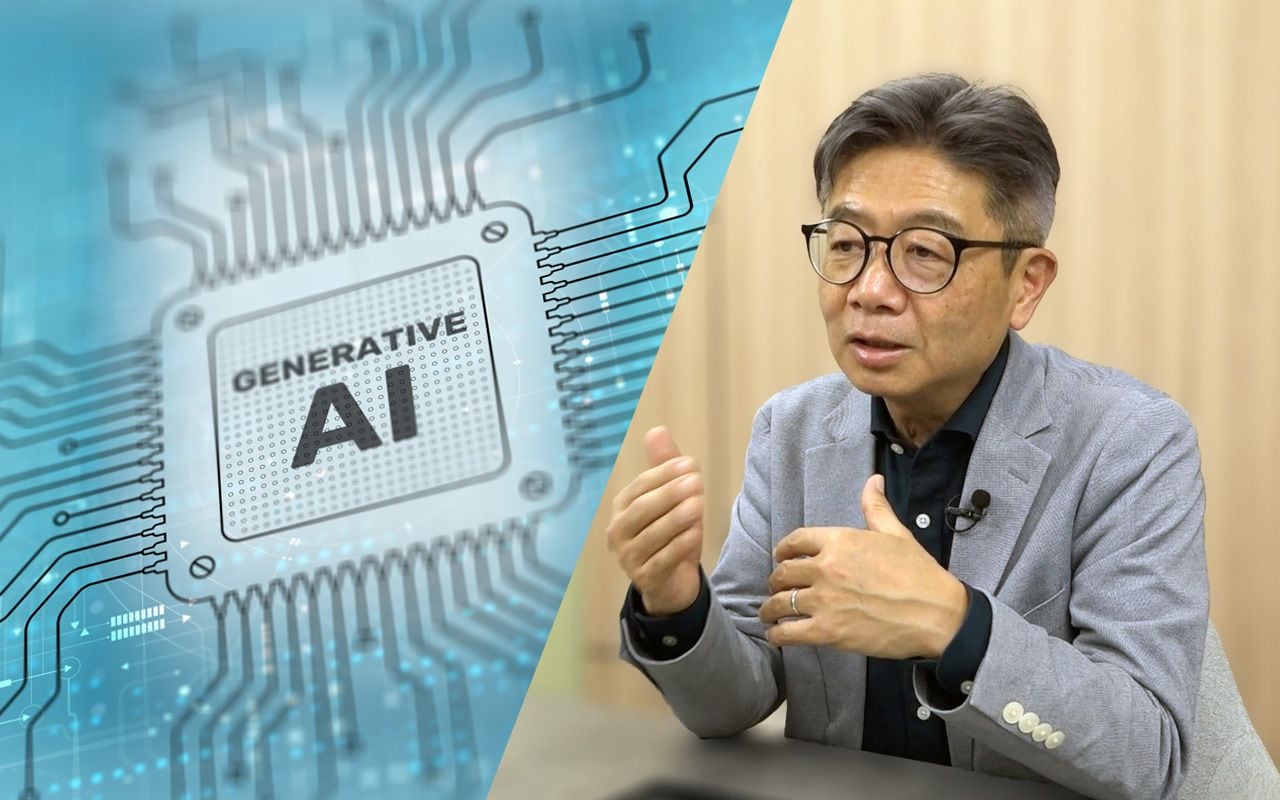
生成AIを「ビジネス現場におけるイノベーション」と捉え、企業活動のあらゆる分野で活用しようと、いち早く導入を進めてきたロート製薬。生成AIという新たな技術を社内の誰もが使いこなせるよう進めてきた、プロンプトエンジニアリングや自社開発などの取り組みと、今後の展望について、同社IT/AI推進室室長の板橋祐一氏に聞く。
生成AIという革新的技術を、どのように捉えるべきか
革新的な技術は、しばしば既存のビジネスモデルを覆します。例えば、スマートフォンはSNSと共に写真の在り方を変え、これを取り巻く産業を一変させました。
こうした技術は、当時「破壊的イノベーション」と呼ばれましたが、現在は「デジタルイノベーション(DX)」に内包されていると、私は理解しています。しかし一方で、DXには長いレンジで起こるものもあります。
生成AIはイノベーティブな技術ですが、現在のところ、当社のような非IT系の製造業のビジネスモデルを急激に変革するものではありません。それにもかかわらず、私たちが生成AIの導入に積極的に取り組んでいるのは、「デジタルで社員の能力を最大化する」というミッションを実現するためです。
昨今の生成AI業界を、簡単に振り返ってみましょう。現在のブームは、2023年にOpen AIが発表した大規模言語モデル「Chat GPT-4」から始まったと言えるでしょう。
その後、論理的思考で高い性能を発揮する「GPT-o1」が登場し、GPT-o4やGPT-4.5などが矢継ぎ早にリリースされました。さらにAnthropicの「Claude」、Googleの「Gemini」、中国DeepSeekの「DeepSeek-R1」などが入り乱れ、技術を競っています。ただし、性能・スピード・値段」の3点で見ると、現在はOpenAIが頭一つ抜けている状況です。
一方、ビジネス側では、2024年には「ビジネスにも生成AIが使える」という認識が広まり、Microsoftの「Copilot」などの導入も進みました。今後は、生成AIが自律的・積極的に人間をリードする「AIエージェント」を中心に、ユーザー体験が変化していくでしょう。
このように、生成AIはまだ進化し続ける技術ですが、ビジネスにおける基本ツールとなることは間違いありません。そこで当社は、生成AIを全ての領域に適用すべきものとして、活用のための取り組みを進めてきました。








