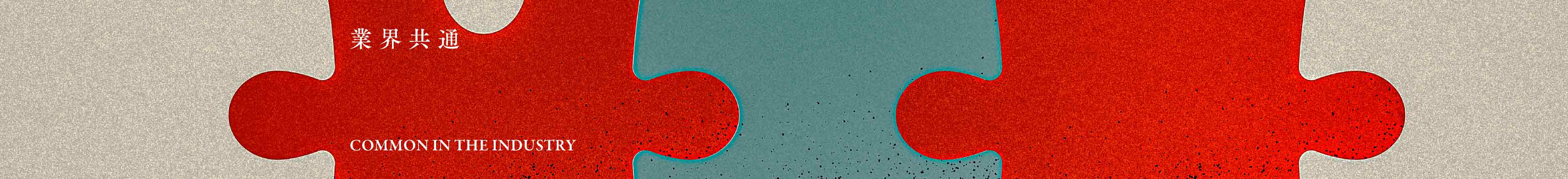ここ数年、国内で脚光を浴びている「オープンイノベーション」。言葉のおおよその意味は分かるものの、どことなく曖昧な響きで実際のビジネスに生かしづらいと感じている読者も多いのではないだろうか。
今回はオープンイノベーションの意義や日本における浸透具合、そして今後の見通しについて、早稲田大学大学院経営管理研究科の川上智子教授(以下、川上教授)にお話を伺った。ビジネスマンにとってより自分ごと化しやすい、マーケティング的な観点からも「オープンイノベーション」を見つめ直してみよう。
日本は10年後れ? 現在はオープンイノベーション「再興」期
自社の知見やリソースのみに頼るのではなく、組織外の技術や知識を掛け合わせることでイノベーションを起こそうとする「オープンイノベーション」。日本ではごく最近のトレンドのように語られることもあるが、実はこの言葉や概念を初めに提唱したヘンリー・チェスブロウ氏の著作『OPEN INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のすべて』(産能大出版部、2004年11月)の原著が出版されたのは2003年と、15年以上前にさかのぼる。
また、消費財メーカーのP&Gはオープンイノベーションによって様々な製品やサービスを生み出している企業として広く知られているが、同社が「コネクト・アンド・デベロップ」と名付けたオープンイノベーション事業を始めたのも2001年の話なのだ。
川上教授も「海外や学会ではブームが終わっている」と前置きした上で、現在は「再興」の段階ではないかと語る。「そもそも、日本は昔から“組織の垣根を超える”事自体は昔からやっているんですよ。産学連携なんかも、今に始まったことではありませんよね」。
加えて「イノベーション」が声高に叫ばれるようになった現状についても、やや違和感があると語る。「それって、企業が昔から重要視していたことですよね。私が企業の基礎研究所で働いていた90年代時点でも他社や大学との連携は普通にありました。ただし、どちらかというと長期安定的な関係で、フレキシブルに相手を変えるということはあまりしていませんでした。イノベーションやオープンイノベーションといった言葉がブームになったのは最近ですが、自社だけではイノベーションは起こせないという考え方は昔から日本にあったものだと思います」
川上教授の推測によれば、日本は特にR&Dへの投資が利益に直結しづらい風土の中、最近は先の見えない基礎研究を自社で抱え込むよりも、市場の利益につながりやすい研究成果を効率的に入手する方に焦点が当たるようになってきた。これによって改めてオープンイノベーションの重要性が叫ばれるようになってきたのではないだろうか、ということのようだ。
技術の追求のみに留まらず、「売り方」のシナリオを描け
昔からある潮流ということで、現在は検証段階を超えて実践段階にあると言えるだろうが、実際には多くの企業が二の足を踏んでいる状況だ。オープンイノベーションを成功させるにはどうしたら良いのだろうか? 引き続き、マーケティング的な観点から語っていただいた。
「シーズを探してくるのも(イノベーションの)一側面ですが、“売り切る”部分まで成功させないとイノベーションとは言えません。研究や開発の段階で、生まれた技術を“どこに”、“どう”売るかまで考えておかないと、他社に先を越されてしまう可能性が高まります」と川上教授は指摘する。この「売り方」のリソースが自社にないケースが多いのだという。
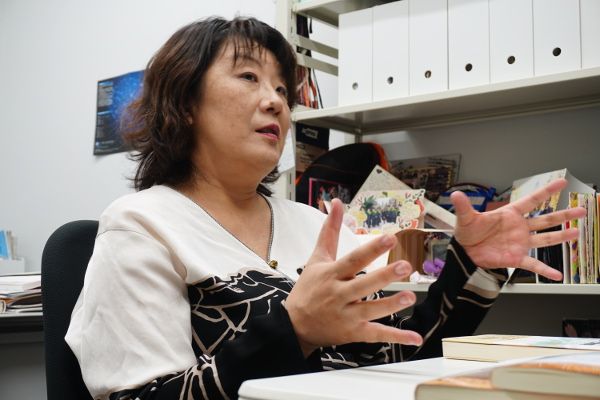
新製品やサービスは、市場に出した直後の売り上げはコスト回収的な面が強くなるため、2回目、3回目と継続的に販売できなければ利益にはならない。あらかじめ3パターン程度「売り方」のシナリオを用意しておき、状況に応じてフレキシブルに選択できるようにしておくのが理想だという。自社でシナリオを用意するのが難しければ、オープンイノベーションで外部リソースを使えば良い。
出口戦略まで考え、成功させなければオープンイノベーションとは言えない。そのため、マーケティング思考を持った経営陣が「何のためにオープンイノベーションを行うのか」「どうビジネスにしていくのか」の指針(ビジョン)を示すことが必須となる。
「消費者」も巻き込んでチームメンバーに
オープンイノベーションというと「川上」の部分、つまり技術や製品を生み出す段階で外部のリソースを活用するというイメージが強いかもしれないが、今は「川下」の部分で消費者を巻き込んだオープンイノベーションが行われる傾向にあるという。
例えば、2000年に始まった米国シカゴのECサイト「Threadless」の仕組みはその先駆けだ。サイト上でTシャツデザインのコンテストを行い、ユーザーに投票を呼び掛けるのだ。多くの票を集めた作品は製品化され、デザイナーに賞金が支払われる。人気が出て追加生産となれば、その分の報酬も支払われる仕組みだ。このように、ネット上のオープンコミュニティを用いて企業と消費者との垣根を取り払おうとする流れは大きくなってきている。
「最近、企業が私たち(消費者)にいろいろなことをやらせるようになってきました。従来組織の中でやっていたことを、私たちにアウトバウンドしているわけです。結果的に消費者の仕事は増えているけれど、“やらされ感”がないから増えてきているし、当たり前に受け入れられていますよね。こうした取り組みは、消費者と一緒に価値を作っていくという考え方に基づいています」

アンケート調査等に留まらず、場合によってはThreadlessのように、企画の段階で消費者に関わってもらう手法が取られるようになってきた。以前から重視されていた「消費者の声」がより根元の部分から活用されるようになってきたということだ。
従来は企業の「外」にいた消費者に、同じ価値の創出を目指すチームメンバーになってもらう。外部リソースを用いてイノベーションを目指すという面からすれば、こうした施策も立派なオープンイノベーションと言えるだろう。
「価値の共創」を目指し、意義のあるイノベーションを
インターネットの普及により、「餅は餅屋」的な考え方が企業にとって当然のものとなってきた。組織の内と外との境界線はますます曖昧なものになっていくだろう。今まですべて1社で担ってきた機能が細分化(アンバンドリング)され、それぞれができることを担うようになっていく。個々の企業に残される役割は今よりずっとシンプルになるはず、と川上教授は予測する。
自分の事業をどう分解し、どんな役割を社外に任せて何を社内に残すのか。これはオープンイノベーションへの関心度に関係なく、すべての企業にとって考えるべき課題だ。

ただし同業他社の「残す機能」を真似しても、必ずしも自社にとってプラスとなるわけではないので注意したい。自社に残して融通が利く状態にしておいた方が良い機能もあるだろう。その製品やサービスを世界で展開させたいのか、それとも国内展開のみなのか等によっても戦略は変わる。やはり全体設計が重要ということだ。
最後に今年3月、川上教授が審査員長を務めた第2回「グリーン・オーシャン大賞」で大賞を受賞した化粧品メーカー、ラッシュジャパンの取り組みを紹介してくれた。
同社は福島県の南相馬市の菜種油を素地に使った石鹸を販売し、社会問題起点の優秀なビジネス事例として高い評価を得た。菜の花には土地から放射性物質を吸い上げる働きがある上に、収穫後の種から作られる菜種油には放射性物質が移行しないという特徴を利用した取り組みだ。川上教授は、このように社会性の強い企業も今後はオープンイノベーションによって増えていくだろうと期待を寄せる。
「とにかく“儲かれば良い”と思って株主利益の最適化ばかり追い求めていると、必ず無理が生じます。少しずつ成長する事を目指すのが企業にとって一番無理が無いんです。経済のクオリティを上げることを意識して、皆がやれることをやり、作れるものを作る。オープンイノベーションによって、価値の創造の方向性を探っていけたらと思います」
自社や株主が潤うことやだけを考えていても生き残れない。企業間や消費者との垣根を取り払い、皆で価値の共創ができる社会。実現のためには企業も個人も、経営や人生の目的を明確に表明できるようにしておく必要がありそうだ。