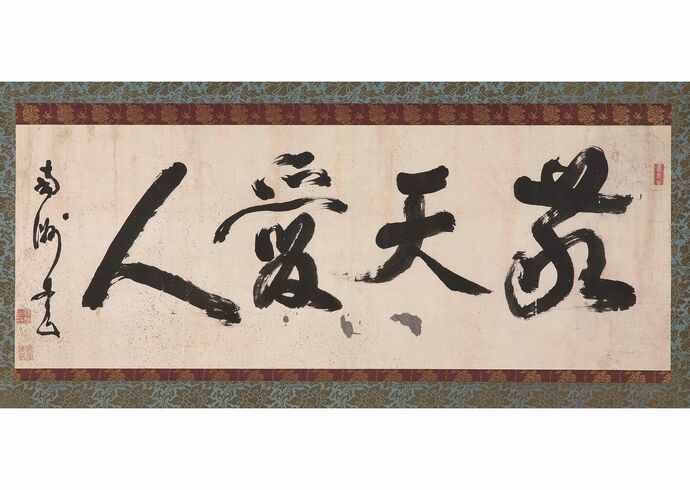ドラッカーは、世界最強を誇ったゼネラルモーターズの戦略的欠陥を見抜いていた
ドラッカーは、世界最強を誇ったゼネラルモーターズの戦略的欠陥を見抜いていた画像提供:shutterstock.com / Paper and Lens Co
『マネジメント』(ダイヤモンド社)をはじめ、2005年に亡くなるまでに、39冊に及ぶ本を著し、多くの日本の経営者に影響を与えた経営学の巨人ドラッカー。本連載ではドラッカー学会共同代表の井坂康志氏が、変化の早い時代にこそ大切にしたいドラッカーが説いた「不易」の思考を、将来の「イノベーション」につなげる視点で解説する。
AIが社会の隅々に浸透する今、ドラッカーが語った「正しい問いを発すること」の意味が重みを増している。効率化が重視される時代に、人間だけが持つ「真摯さ」とは何なのだろうか。
外からやってくるもの
AI(人工知能)は、もはやSFではない。私たちの仕事、学習、そして思考の様式にまで、実に驚くほど深く浸透している。その広がりは、かつてのスマートフォンをしのぐかもしれない。その能力も、人間の知性を超越したようにさえ見える。
私は幸運にも、最晩年のピーター・ドラッカーに面会を果たした者の一人だ。ただし、彼との対話の中に、このAIとの向き合い方のエッセンスが豊富に含まれているのに気付いたのは、ごく最近のことである。
 写真:著者提供
写真:著者提供
2005年5月、生涯を閉じる半年前の彼にカリフォルニアの自宅で会ったとき、そこにいたのは「マネジメントの父」というより、時の流れを見届けてきたかのような、静かな哲学者だった。赤いカーディガンを羽織り、籐椅子に深く腰掛けた95歳の賢人は、穏やかにこう語ったのだった。
「日本の企業にしても立派なインフォメーションシステムを持ってはいるものの、中身のほとんどは組織内部の情報だ。しかも、過去のことについての情報である。外部の情報をいかに手にするか、それをいかに使いこなすかという問題こそ、われわれに課された情報に関わる最大の課題であり、挑戦である」