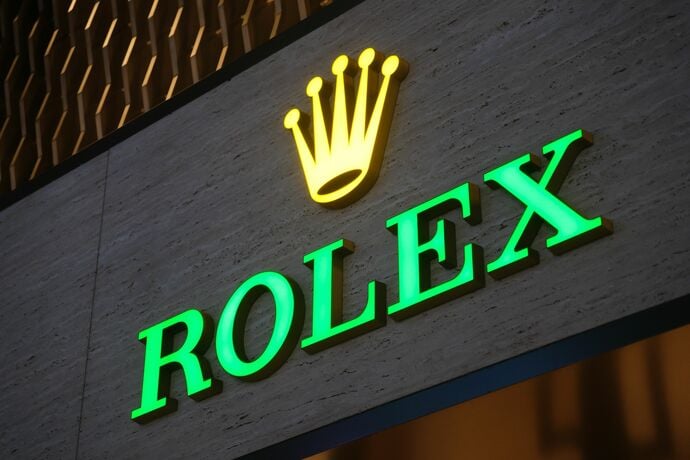GenesisAI 代表取締役社長/CEO、北陸先端科学技術大学院大学 客員教授の今井翔太氏(撮影:冨田望)
GenesisAI 代表取締役社長/CEO、北陸先端科学技術大学院大学 客員教授の今井翔太氏(撮影:冨田望)
米国オープンAIなどビッグテックがリードする生成AIに、中国ディープシークが一石を投じた2025年。最新のAIはどこまで進化しているのか。そして、AIの浸透によってビジネスや企業経営はどう変わるのか。AI研究者であり、AI開発会社の社長としても活動する今井翔太氏に聞いた。
ディープシークがもたらした「オープンソース」の衝撃
――2025年1月、中国のディープシークが発表した生成AIが、一時大きな話題になったものの、すぐに終息した印象があります。この経緯と米国テック企業の対応をどう見ていますか。
今井翔太氏(以下、敬称略) ディープシークの特徴は2つあり、1つは開発コストの安さ、もう1つはオープンソースという形で提供されたことです。このどちらも、生成AIで先行していた米国のテック企業にとってはショッキングな出来事でした。
米国ではその後安全保障の観点から、ディープシークが開発したAIについて政府内での使用を制限する可能性が示唆されたため、利用が拡大せず、現在に至っています。
ディープシークがなぜ低コストで生成AIを開発できたかについては、すでに多くの専門家が分析を行っているので、私は、もう1つの特徴であるオープンソースであることについてお話しします。
これまでの主な生成AIは、その開発技術がブラックボックス化していました。例えば、米国の生成AI開発をリードするオープンAIは、「オープン」という言葉が入った社名とは裏腹に、実は非常にクローズドな企業として知られています。開発した最新のAIモデルは基本的に公開せず、自社の技術に関する論文も書きません。
それに対してディープシークは、ソースコードを公開し、自由に追加学習してもいいと宣言しており、論文も公開しています。オープンAIやアンソロピックなど米国のAI開発企業は、技術を隠すことで自分たちの利益を守ってきたのですが、オープンで無料、あるいは安い技術が台頭してしまうことは死活問題です。