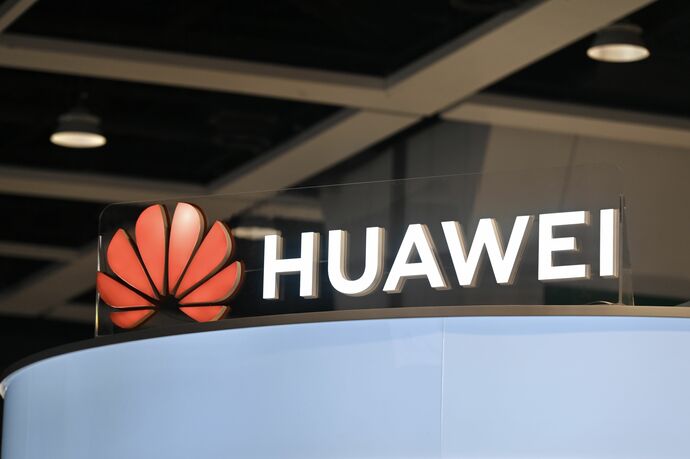メンバーの意識を変えるには地道な努力が必要
監査やコンサルティングなどプロフェッショナルサービスファームとして、クライアントのビジネスを変革するためのサポートを提供し続けるEY Japan。2020年7月には松永達也氏をチーフ・イノベーション・オフィサーとして迎え、テクノロジーを活用したアセットの導入を推進。また、同年8月にはクライアント向けアセット開発を行う「クライアント・テクノロジー・ハブ(CTH)」を新設し、データ&テクノロジー分野のサービス強化に努めている。グローバルな企業での経験を生かし、EY Japanの変革に取り組む松永氏に、同社のDXについて聞いた。また、2022年からCTHのリーダーを務める加藤芽奈氏に、現状や展望を語ってもらった。
――EY JapanがDXに取り組むようになったきっかけを教えてください。
 松永達也/EY Japan チーフ・イノベーション・オフィサー
松永達也/EY Japan チーフ・イノベーション・オフィサー大手外資系IT企業にて、コンサルティング・パートナー、人事部長、常務執行役員として、金融メガバンクグループ事業コグニティブソリューション事業担当などを歴任後、2020年7月EY Japan チーフ・イノベーション・オフィサーに着任。最新のテクノロジーを活用した、EYのデータ分析能力の向上やお客さまのDXを支援するアセットの開発、導入を推進している。
-----
組織のイノベーションを考えるときにお勧めしたい書籍:『両利きの経営』(チャールズ・オライリー、マイケル・タッシュマン著)
松永 会計士は監査という観点で、税理士は税務という観点でクライアントの課題を見つけ、その解決策をクライアントと共に考える。コンサルタントはクライアントの情報を分析して、社内外の情報と比較しながら、ビジネスの課題を抽出し解決策の実行を支援したり、新しいビジネスモデルを考える。いずれのEYの事業でもデータを分析して、そこから新しい課題やビジネスチャンスを見つけ出しています。その際にデータ分析の生産性を上げていく、あるいはデータを活用して将来を予測することができれば、クライアントへのサービスの価値向上につながります。そこで考えられるのが、テクノロジーの活用です。EY Japanでは、このデータ分析能力の向上をDXの主目的として取り組んでいます。
2020年8月には、クライアント向けにアセット開発を行う「クライアント・テクノロジー・ハブ」を新設し、世界各地にハブを作りました。それにより、EY Japanとして、データ&テクノロジー分野のサービスの強化を目指しています。
――DXを推進するためのステップは設定されましたか。
松永 最初のステップとしては、必要なデータの収集ですよね。紙の帳簿だったものをデジタル化し、共通のプラットフォーム上にデータを集める。そうすると、データの共有基盤ができます。次にそのデータを分析し、新しいことを発見するためのインサイトを求めていきます。そこからできてくる分析モデル上でシミュレーションをして、未来予測をできるようになると、価値の高いソリューションを提供できるようになります。
このように自動化やシステム化が進むと、近い将来、人間に代わりテクノロジーが多くのプロセスを担当するようになります。また、データを1カ所に集めるとなると、情報漏洩等のセキュリティの問題が出てきますし、大きな投資も必要となります。最近、データを分散型にしていこうという動きが出てきました。まさにweb3.0への進化ですね。ブロックチェーンやエッジコンピューティングなどの技術を使ってデータを分散させ、現場で分析してその結果だけを持つ。つまり、データを中央集権的に管理する必要がなくなります。
例えば、自動運転がさらに進んでいくときには、集中管理のシステムではなく、その場その場でリアルタイムにデータを判断できるような環境を作って、その結果だけを、分析のフレームワークや手法を作る人が把握できるというやり方に変わっていくと思います。
データから分析を導き出す際に、AIや統計モデルを使うことには大きな意味があります。前職では、量子コンピューティングに将来性を強く感じました。量子コンピューティングが出てくると、飛躍的にコンピュータの処理スピード感が増します。今はデータや検索結果を持っている会社が強いとされていますが、その認識も大きく変わる気がします。
――DX推進のステップごとに直面した課題はありましたか。
松永 テクノロジーを活用するということは、会計士や税理士、コンサルタント、さらにはクライアントも、現在の仕事のやり方を変えることにつながります。当然、最初は心理的な障壁があるわけです。それを、「これをやることによってサービスの質やスピードが上がるのだ」「社員が仕事をしやすく、結果的にハッピーになるのだ」と意識を変えるのには、地道な努力が必要です。
そのために共有と啓蒙が必要です。監査サービスでは私の着任以前より、アシュアランスイノベーション本部がリードして毎年計画を立て、AI等の最新技術を活用した監査の高度化と生産性向上がオントラックで進んでいます。全てのパートナーやメンバーと目標を共有して実行してきた成果が表れています。
また、2022年には社内向けのデジタル研修を行いました。テクノロジーを軸にAI、ブロックチェーン・メタバース、、アナリティクスなどの観点から取り組んでいることをビデオにまとめ、研修プログラムの一環として受講できるようにしました。
テクノロジーのケイパビリティは事業部門ごとに活用の仕方は異なりますが、根本的なところは一緒です。そこで、それらEYに必要なテクノロジーのケイパビリティを共通化し、会計士、税理士、コンサルタントとしてのキャリアと並行してテクノロジー人材向けのキャリアフレームワークをグローバルで導入しました。やはり、これからは、テクノロジーに精通した人たちがさらに活躍できる環境を社内に作っていくことが重要ですから。
先日、出張で加藤とサンノゼに行きましたが、私があった大学生はデータサイエンティストを目指していました。データサイエンティストは、分析の知識だけがあればいいわけではなく、ビジネスに生かすことが重要で、彼らも実社会で学んだことを実践するのを楽しみにしていました。こうしたデータサイエンティストをはじめ、日本はデジタル人材が絶対的に不足しています。よって、今やデジタル人材の育成は、多くの企業にとって課題になっています。
では、日本でDXリードできる人材を育てるにはどうすればよいか。テクノロジーの専門家は育てたり、外部の専門家に依頼できますが、テクノロジーをどう自社のオペレーションに活用していくのか、例えば製造業のファクトリーのオペレーションをテクノロジーを活用してどう変革していくか。このようなインダストリーを変革するソリューションの開発は日本人が得意とすることころだと確信しています。日本人の今までのケイパビリティにより、業界ごとの変革をリードできるところだと思います。よって、現場の人材を巻き込むことがDXの成功要因だと考えます。
例えば、企業の社長がDXをしようと専任部門を立ち上げても、現場の人たちにはオントップの仕事だと思われがちです。そうすると、日々の業務に追加された余分な仕事というふうに見えてしまう。そうではなく、今の日常業務のやり方を変えるためにDXするのだと。今まで人がやっていた業務をシステムに置き換えるというのはやはり受け入れにくいところはありますが、そこを先取りして常に変革し続ける会社が成功するのだと思います。
――具体的な例があれば教えてください。
松永 保険業界のクライアントで、EYのテクノロジーを活用したDX推進プロジェクトが進んでいます。保険業界も、最近はネット生保やネット損保などが出てきて、非常に利便性が高まっています。
従来、スマホの画面を変えるには、メインフレームがいろいろなアプリケーションにつながっているため、さまざまなケースを想定してテストしなければならず、時間と経費がかかりました。ところが、ネット生保さんなどは、そういった重いシステムを持っていないので、リリースまでのスパンが圧倒的に短い。
そこで、当社が提供を始めたのが、保険会社の抱える技術面の課題や組織間の障壁を軽減できる「EY Nexus」というテクノロジーアセットです。スマホの画面やメインフレーム等のAPI連携ができるようなツールで、米国のベンチャー会社が開発したものですが、ノーコードソリューションとクラウド上のデータベースを組み合わせて導入することにより、今までのメインフレームはそのままで、柔軟な対応が可能となりました。
こうしたクライアント自身の変革を促すツールに、業界特有の知識やテクノロジーの知恵が入り込んでいるものには、米国やヨーロッパで持っていたナレッジが組み込まれていますので、日本でも活用しやすいと思います。一からコンサルタントが学んで勉強していくのではなく、アセットの中に入ったノウハウを活用することにより、グローバルスタンダードのものが日本に提供できるようになる。グローバルの経験や知識を日本流に構築された上で提供されるという点が、お客さまにとっては価値が高いのではないでしょうか。