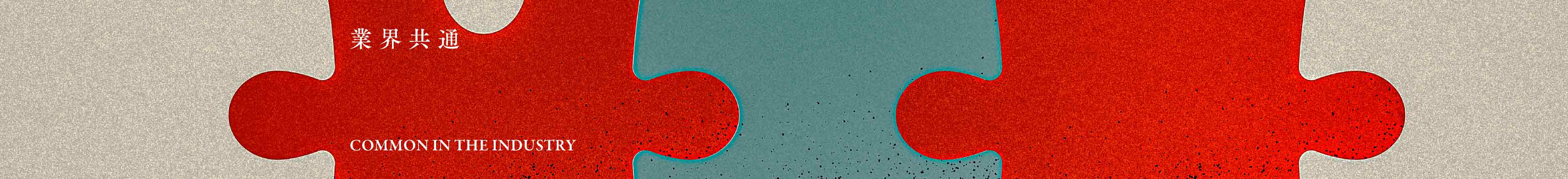アジャイル開発手法「スクラム」に大きな影響を与えた野中郁次郎教授(写真:山口結子)
アジャイル開発手法「スクラム」に大きな影響を与えた野中郁次郎教授(写真:山口結子)
新しいソフトウェア開発方法論「アジャイル開発」の一手法である「スクラム」の源流は、日本発の論文にあった。その論文著者の一人、野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授、中小企業大学校総長)が語る「アジャイルの真髄」とは何か。(JBpress)
新しいソフトウェア開発手法として、さらに組織変革やビジネスの革新手法として注目を集めている「アジャイル」。「スクラム」はその中で最も普及している具体手法である。その「スクラム」提唱者の一人ジェフ・サザーランド氏が着想を得る原点となったのが、日本企業におけるイノベーションの成功要因を研究した日本発の論文なのだ。
サザーランド氏が、その論文を竹内弘高氏(現ハーバード・ビジネス・スクール教授)とともに執筆した野中郁次郎氏に実際に対面したのは、「スクラム」を提唱してから時間が経った2011年だった。サザーランド氏が着想を得た論文の中核部分は何か、またどのような経緯で対面が実現したのか。新刊『アジャイル開発とスクラム 第2版』(平鍋健児、野中郁次郎、及部敬雄著、翔泳社)から著者の野中郁次郎氏が執筆した部分を引用する(斜体部分)。
古い論文が再度脚光を浴びている!
著者(野中郁次郎)がアジャイルと呼ばれるソフトウェア開発手法に出会ったのは、2010年である。ソフトウェア製品を開発するチェンジビジョン社の社長である共著者(平鍋健児)が一橋大学に訪れ、ソフトウェア開発を変革しようとしているコミュニティで私に講演をしてほしいという。私はソフトウェア開発の技術的内容はわからないから、とお断りしようとしたのだが、あまりに熱心なので少し話を聞いてみたいと思った。
平鍋氏によると、竹内弘高教授と私が1980年代に書いた論文「The New New Product Development Game」(1986年、Harvard Business Review)が、今ソフトウェア開発業界の最新手法、アジャイル開発として話題になっているというのだ。
強かった1980年代の日本の製造業。その新製品開発手法を研究して紹介した論文の中で、専門組織をまたいで集められたチームが、一体となって製品開発する手法を私たちは「スクラム」と名付けた。それがそのままの名前で、ソフトウェア開発手法として米国で提唱され、今、日本にも逆輸入されている、というのだ。
これにはとても驚いた。35年以上前の論文が、新しい文脈で脚光を浴びている。そして、その新しい文脈とは、当時想定していなかったソフトウェア開発の領域なのである。
2010年、「アジャイルジャパン」というコミュニティによるカンファレンスで、私ははじめてソフトウェア開発者たちの前でスクラムの講演をした。私の言葉は彼らに届くのだろうか、という不安を私自身が抱えて。しかし、その不安はまったくの杞憂であった。
そこでは、若い日本のエンジニアやリーダーたちが集い、目を輝かせて最新のソフトウェア開発手法について議論をしていたのだ。それは技術的な議論だけではなく、人と人との協調、共感といった感情面も含めた、チーム作りや組織作りにまで及んでいた。そして、彼らは正解を学んでいるのではなく、新しいコンセプトを使って、自分たちのやり方を形作ろうとしているように見えた。まさに、私たちが「スクラム」という言葉で呼んだ共感と共振がそこにはあったのだ。