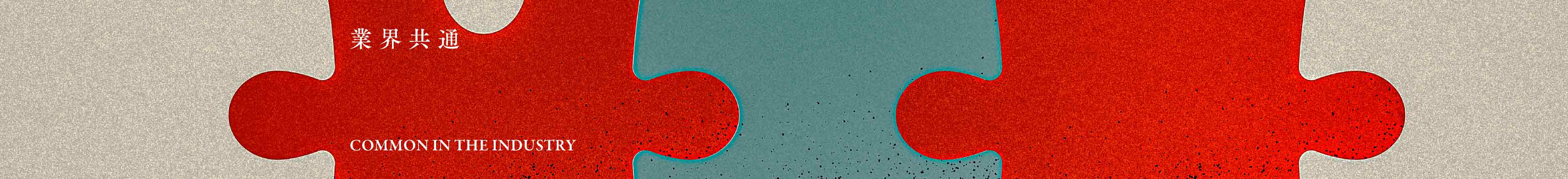熱意とスピード、継続で2020年の「先」を目指す
そして、3者それぞれの立場から見るオープンイノベーション市場の展望が語られた。
前田氏は、今後の日本を引っ張っていくポテンシャルの高い中小企業を1000社、2000社と増やしていく「スーパージャパン1000社」構想を語った。真にポテンシャルの高い企業が足りない技術を国内外問わず外部から補うことで、さらに成長していくことで正のスパイラルを起こしていくという考えだ。また、並行して現在約300万社存在する中小企業を50万社程度にまで統合し、価格競争によって人件費が下がってしまう状況を回避していく必要もあるという。
端羽氏は、「オープンイノベーションという言葉がなくなるような社会」を目指したいと語った。「イノベーションってそもそもオープンだよね、という時代が来るように頑張りたいですね。そもそもイノベーションというのは組合せだと思っています。今はもう、ゼロから新しいサービスや製品を作っていくというスピード感ではないと思うんですよね。今あるものを上手く組み合わせることで、新しい価値をつくる。iPhoneやルンバも、登場した当時は特に革新的な技術が使われていたわけではありませんでした。技術を上手く組み合わせることで、イノベーションが生まれたわけです」
今後は「組合せ」の速度を加速させていくために、自社の持ち物だけでなく他社の技術や知見を巻き込むことが当たり前になっていくのだろう。
伊地知氏も前田氏と同様、国際競争に触れた。日本ではここ数年、東京オリンピックが開催される「2020年」が様々なシーンにおけるベンチマークとされてきたが、2019年に入った今もこの状況が変わっていない状況を憂いているという。
「技術的な社会導入を含めて、『2020年』が色々進むきっかけにはなったと思うんですけど、これをベンチマークにしているのは日本だけです。他の国は2025年や2030年を見据えて投資している中、日本だけが近視眼的になりすぎている。これはちょっと危ないのではないかと思っています」
 「Creww」代表取締役・伊地知天氏(左)© OPEN INNOVATION CONSORTIUM
「Creww」代表取締役・伊地知天氏(左)© OPEN INNOVATION CONSORTIUM
また、Crewwとしてはコミュニティの参加者を増やし、横のつながりを充実させることで日本全体のイノベーション創出活動を支援していきたいという展望を語った。
最後に、3者が考えるイノベーションを起こす「鍵」が語られた。前田氏は「失敗してもトライし続けること」、端羽氏は「一歩を踏み出すまでのスピードと続けること」、伊地知氏は「パッションを持って社内を巻き込めるイントレプレナー」だと答えた。伊地知氏の言葉の真意はこういうことだ。企業において、オープンイノベーションを行う部署は本業から切り離された「出島」等と言われることがあるが、「本島との間に橋を渡してその上を行き来できる人」、つまりパッションを持って社内の人間を巻き込んでいけるイントレプレナーが活躍できる場でなくてはならないのだという。
日本ではまだ始まったばかりのオープンイノベーションの取り組みだが、既に世界のスピード感とはギャップが生じ始めている。オープンイノベーションは取り組んだ先から売り上げを伸ばしてくれる魔法のような手段では無いが、だからこそ早めに社内で共通のビジョンを共有し、一丸となって取り組んでいく必要がある。既に社内で取り組んでいるが効果が感じられない、もしくは取り組もうとしているが尻込みしているという方は、改めて自社におけるオープンイノベーションの必要性について、中長期的な視点で見つめ直してみてはいかがだろうか。