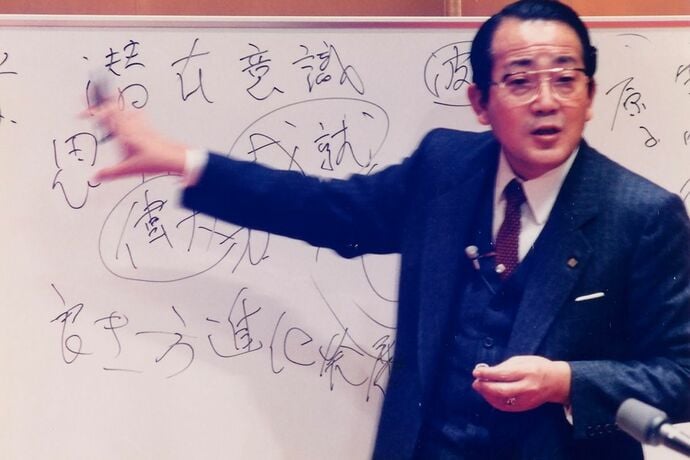写真提供:共同通信社、日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:共同通信社、日刊工業新聞/共同通信イメージズ
15年後に生き残れるのは、どのような自動車メーカーなのか? 脱炭素化、AI普及など、世界が「ニューノーマル」(新常態)に突入し、ガソリンエンジン車主体の安定した収益構造を維持できなくなった企業が考えるべき新たな戦略とは? シティグループ証券などで自動車産業のアナリストを長年務めてきた松島憲之氏が、産業構造の大転換、そして日本と世界の自動車メーカーの、生き残りをかけた最新のビジネスモデルや技術戦略を解説する。
第5回は、トヨタとホンダの投資計画を基に、電動化、車載ソフトをはじめとする競争力強化の戦略について解説する。
好調だった2024年3月期決算と先行投資実施の25年3月期
自動車会社の2024年3月期決算は絶好調で、多くの企業が過去最高益を更新した。最大手のトヨタ自動車(トヨタ)の営業利益は前期比96%増の5兆3529億円と過去最高を更新、日本企業で初めて5兆円台の大台に乗った。米国などを中心に世界で収益源であるハイブリッド車が販売好調だったことや円安が寄与したからである。この決算内容について少し解説しよう。
24年3月期の営業利益の増減要因を見ると、①営業面の努力(特にハイブリッド車の販売増)2兆円、②為替変動の影響(円安メリット)6850億円、③原価改善の努力1200億円、④諸経費の増減・低減努力(原材料などのコスト上昇)▲3800億円、⑤その他2029億円となっている。
インフレ進行で原材料価格が上昇しているのがマイナス要因となっている。また、人件費などの上昇圧力が生じている部品会社に対する値引き要請が緩くなっているため、原価改善の努力は従来に比べて少なくなっていた印象だ。
25年3月期の営業利益予想は4.3兆円と高水準ながら減益になると発表した。営業利益の増減要因を見ると、①為替変動の影響(円安メリット)550億円、②販売面の影響▲2150億円、③原価改善の努力▲1500億円、④諸経費の増減・低減努力(コスト上昇)▲7800億円、⑤その他371億円となっている。
為替前提はドルが145円と前年と同じだが、ユーロは160円(前年157円)で円安メリットが発生しプラス要因になる。しかしながら、インフレ進行による資材価格高騰などのマイナス影響が大きく、原価改善の努力では吸収できないとしており、これは正しい見方といえるだろう。
一方、販売面での収益はかなり慎重な予想で大幅減益を見込んでいる。②販売面の影響▲2150億円の内訳として、台数・構成1750億円(前期9800億円)をかなり少なく見ており、その他という項目で▲4300億円(前期9200億円)の大幅減益要因を入れているが、販売面はかなり慎重な計画と見てよいだろう。
また、人件費高騰の影響や先行投資負担拡大で諸経費がかなり拡大して、④経費の増減・低減努力(コスト上昇)が▲7800億円と大幅減益になると計画しているが、これは妥当な内容である。諸経費拡大については、佐藤恒治社長が、モビリティカンパニーへの変革に向けた投資を拡大すると宣言、成長領域に関する部分を5000億円円増額して1兆7000億円を見込むとしており、潤沢なキャッシュフローを将来投資に活用する姿勢を鮮明にした。
電動化、AI、車載ソフトなど、自動車や関連サービス分野での競争力強化のための先行投資であるが、今まさにこれを実行せねば未来はない。これは、ホンダなど他の自動車会社にも見られる姿勢である。