ブルゴーニュ最大規模かつ、大いに尊敬される生産者「メゾン・ジョゼフ・ドルーアン」。日本に輸入されて50周年となる今年、当主のフレデリック・ドルーアン氏が実に8年ぶりに来日し、あらためてメゾン・ジョゼフ・ドルーアンのワインがどれだけスゴいかを颯爽と見せつけていった。
 フレデリック・ドルーアン
フレデリック・ドルーアン1880年から続くブルゴーニュのワイン商にして、ブルゴーニュ全域に100ha、アメリカ・オレゴン州にも100haの自社管理畑を持つブルゴーニュ最大規模のワイン生産者「メゾン・ジョゼフ・ドルーアン」のオーナー一族、ドルーアン家の4代目当主。4兄弟の末っ子で兄・姉もメゾンで重要な役割を担っている
ブルゴーニュワインのど真ん中
私は以前、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンの「クロ・デ・ムーシュ」という畑のワインをして「ブルゴーニュワインのど真ん中」と言ったことがある。個人的に好み、ということもあるのだけれど、ブルゴーニュワインの面白さに触れたいなら、あれこれ遠回りするより、まず、このワインを試すのが手っ取り早いと、今もおもっている。
メゾン・ジョゼフ・ドルーアンはブルゴーニュワイン業界で最大規模を誇る家族経営の生産者だ。日本には1975年から輸入されていて今年で50年。1975年なんて、日本で誰がワインを飲んでいたのだろう……という時代だとおもうので、そもそも日本人にとってのブルゴーニュワイン、あるいはワインのイメージ形成に大いに影響している生産者だとおもわれる。
この50周年を記念して、先ごろ、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンの当主、フレデリック・ドルーアンさんが実に久しぶりに来日して(8年ぶりだそうだ)メディア向けにあらためてメゾン・ジョゼフ・ドルーアンを紹介するイベントを開催した。
会場で着席して、この日テイスティング予定のワインの一覧を見て驚く。
赤ワインがClos des Mouches(クロ・デ・ムーシュ)とMusigny(ミュジニー)、白ワインがClos des Mouches(クロ・デ・ムーシュ)とMontrachet(モンラッシェ)。
すべてがブドウ収穫年(ヴィンテージ)違いで3種類ずつ用意されていた。贅沢、ここに極まる!
 これを個人で全部揃えようとおもったら百万円じゃあまるで足りない……
これを個人で全部揃えようとおもったら百万円じゃあまるで足りない……
そして完全に本気のラインナップでもある。格闘技なら全部が一撃KO級の必殺技。なぜなら、北はシャブリから南はマコネまで(というかボジョレーまで)ブルゴーニュの全域と、さらにアメリカ・オレゴン州にも畑を持つメゾン・ジョゼフ・ドルーアンのなかでも、精神的支柱というべきブドウ畑クロ・デ・ムーシュに、ブルゴーニュ最高峰の産地ミュジニーとモンラッシェのワインを並べているからだ。
ブルゴーニュワインの歴史とメゾン・ジョゼフ・ドルーアン
ちょっとここでザクッとブルゴーニュの歴史の話をさせていただきたい。
時は10世紀。つまり西暦900年代。クリュニー修道院(ベネディクト派)という組織がブルゴーニュの南のほうを拠点に活動していた。彼らは貴族に免罪符出すような集団で、貴族たちからお礼として土地を寄付されていた。これで修道院はたくさんの土地を所有した。そこにはブドウ畑も多く、キリスト教はミサでワインを出す関係上、クリュニー修道院はかなり大きなワイン生産者集団となった。
クリュニー修道院は100年ほどの間に1,500修道院ほどを影響下に置き、そのトップともなるとローマ教皇並の権力を誇っていたという。もともと彼らは権力と結びついて堕落した修道会に対して批判的な存在だったのだけれど、組織が肥大化し、自分たちが権力者の立場になると、批判される側になってしまう。
クリュニー修道院への反対派として12世紀ごろに勃興したのがシトー派修道会だ。彼らの拠点は、同じブルゴーニュ地方のコート・ド・ニュイからその南のボーヌのあたりにあって、ブドウ研究にも熱心だった。彼らは良いワインができるブドウ畑を見つけると、そこを石で囲った。これをClos(クロ)と言う。
現在、ブルゴーニュワインは、コート・ド・ニュイからコート・ド・ボーヌと呼ばれるエリアの評価が最も高く、そこにはクロなになに、と言われる畑がいくつもある。また、ブルゴーニュでは伝統的に造り手ではなく畑に格付けをする。この文化の誕生にはシトー派の活動が影響している。
その後、ブルゴーニュワインに大きく影響したのはフランス革命。この時に貴族とともに教会の権力は大きく削がれ、その土地は解放された。その後、資本主義が生まれたこともあって土地は商人や資産家のもとへ。ところが1800年代後半になると蒸気機関ができて、フランス南部からパリに、十分においしいワインが、ブルゴーニュより安い価格で流通するようになった。セーヌ川でパリまでつながっているブルゴーニュの地理的強みを、技術が覆したのだ。これとフィロキセラという害虫の被害でブルゴーニュワイン業界が苦境に立たされると、地主たちは土地を手放し、結局、ずっとそこにいた農家が畑を守るようになる。いまブルゴーニュには4,000くらいの造り手がいて、多くが家族経営の小さなワイナリーなのはここに理由がある。
農家は真面目に良いワインを造る。だけれど売れない。買ってくれる人に届かない限りは、どんな良いワインでも売れないからだ。そこにあらわれたのがネゴシアンなどとも呼ばれるワイン商たち。彼らは農家からブドウやワインを買って、必要とあらば自分たちで醸造、ブレンド、熟成をして、自分たちのブランドで売っていた。これでブルゴーニュは持ち直した。
メゾン・ジョゼフ・ドルーアンの創業年は1880年。当時の彼らはブルゴーニュワインの中心地、ボーヌのワイン商だったというから、この時代のワイン商が起源なのだ。
ところがその後、第一次世界大戦付近の苦境のなかで、ワイン商たちは徐々にワインビジネスから手を引くようになる。要するに儲からなくなったのだ。それでブルゴーニュワインはワイン商から再び農家の手へと戻っていくのだけれど、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンは、ここでワインをやめなかった。それどころか父の事業を継いだ2代目のモーリスは、ワインの安定供給のためにと1921年に畑を手に入れている。この畑が冒頭に名前を出したクロ・デ・ムーシュという畑(クロ)だ。格付けはプルミエ・クリュだから上から2番目。場所はボーヌの南の方。同クロ中、なだらかな丘の中腹にあって、南東向きの土地、14haをメゾン・ジョゼフ・ドルーアンが所有している。
その当時のクロ・デ・ムーシュは第一次世界大戦とその前のフィロキセラの被害で見るも無残な状態だったそうだ。モーリスは、ブドウ樹を植え直し、このクロを再生した。ブルゴーニュの伝統に従って、ピノ・ノワールとシャルドネとを混植し、ワインもピノ・ノワールにシャルドネを混ぜて醸造していたのだそうだ。
 美しく整備された現在のクロ・デ・ムーシュ。石垣はここがクロであることの証
美しく整備された現在のクロ・デ・ムーシュ。石垣はここがクロであることの証
以降、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンはワイン商よりもむしろ造り手として成長していく。1957年に事業を引き継いだ3代目・ロベールの時代になると、この傾向はさらに顕著になって、プルミエ・クリュ、グラン・クリュとブルゴーニュの名畑を複数所有するようになり、4代目、フレデリックが当主となった現在、ブルゴーニュに100ha(うちグラン・クリュが14カ所、プルミエ・クリュが30カ所)の畑をもつ、ブルゴーニュ最大級の生産者になった。
ナチュラルなワインの先駆者
というような話をフレデリックさんは、集ったメディアの面々を見て「もう皆さん知っていますよね?」という感じで、詳しくはしなかったので補足させていただいた。
メゾン・ジョゼフ・ドルーアンはその出自ゆえにもともと持っていた畑というのがない。現在所有する畑のほとんどは農家や地主が大事に守ってきた土地。それを関係性のなかで手に入れ、場合によっては蘇らせたのだから、畑への思い入れと責任感はとても強い。
今回、フレデリックさんが強調したのは気候変動への対応状況だった。もともとオーガニック栽培への転換も1988年から始めている、かなり先駆的なメゾン・ジョゼフ・ドルーアンは、オーガニックで許容されている農薬の類もなるべく使わないで済むようにと、あの手この手を講じてきた、文字通りの意味での自然派な造り手だ。例えばグラン・クリュとプルミエ・クリュの畑では土を固めて土中の生態系を壊さないようにと馬で耕作している。80年代からすでにバイオダイナミック農法も取り入れている。
そのうえで、避けられぬ温暖化に対しては、温暖な気候に強い品種の研究に熱心に投資していて、ブドウ樹の剪定方法にも独特の工夫を凝らしている。
さらに、航空輸送は当然のように禁止。アメリカまでは帆船でワインを運ぶのだそうだ。積載されるワインボトルについても、重量を420gにまで減らす目処がついているとのこと(現状のブルゴーニュの標準的な軽量ボトルはおよそ550gだそうだ)。
クロ・デ・ムーシュ VS グラン・クリュ
ということなので、あとはもう、みなさん飲んでみてくださいという感じなのだけれど、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンの魂の畑、クロ・デ・ムーシュについて、もうひとつ私が知っている逸話を話すと、まだピノ・ノワールとシャルドネを混ぜて醸造していた1928年。シャルドネの成熟が遅れて、ひとまずピノ・ノワールだけを先に収穫する、という事態になった。そして結局、この年はシャルドネが間に合わず、両品種を別々にワインにした。そうしたら、このシャルドネが素晴らしいワインだった。
当時の当主、モーリスは仲の良かった、パリの名レストラン「マキシム・ド・パリ」のディレクターにこのシャルドネを試してもらった。即座に300本欲しいと言われたのだそうだ。世界中にその名を知られるマキシムに選ばれたことで、クロ・デ・ムーシュは、そして、ワインの造り手としてのメゾン・ジョゼフ・ドルーアンは、一躍、ワイン界のスターになった。(このワインは15年ほどマキシム・ド・パリ専売だったという)
今でもメゾン・ジョゼフ・ドルーアンのクロ・デ・ムーシュは白ワインの方が評価が高い傾向にある。それから、クロ・デ・ムーシュに限らず、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンの高級ワインたちは、フランスの名レストラン御用達だ。
今回、このクロ・デ・ムーシュの白ワイン、赤ワインと並べられたミュジニーとモンラッシェについては、ブルゴーニュを愛する日本では特に人気があるから、すでに言説が溢れているので、私が何か言うまでもないのだけれど、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンが所有するミュジニーは0.68haで、赤ワイン(ピノ・ノワール)の畑。一般的には女性的とか上品、エレガントと言われる畑だけれど、メゾン・ジョゼフ・ドルーアンのそれはフレッシュネスの中にあるグッと力強い、そしてすごく個性的でおいしいタンニンが印象的だった。2022年、2019年、2011年を試せたのだけれど、2019年ですでに、ちょっと表現のしようがないほどに素晴らしく、これはヤバいぞ、と感じ、2011年までいくと味わいや香りの複雑な要素が完璧に統合されていた。これは危ない。こういうワインを飲んで、人はワインに取り憑かれる。人生が変わりかねないキケンな飲み物だ。
対するクロ・デ・ムーシュは2023年、2019年、2011年。30万円級のミュジニーと比べると3万円級と現実的だけれど、こちらも2011年は印象的で、タンニンと酸と、両方がよく熟成していて素晴らしい。また、同じ2011年ということで比べるなら、よりエネルギッシュだ。現時点でオススメなのは2019年。これは熟成させてよし、今飲んでよしだとおもう。おそらく若干、酸が落ち着いている。それで軽快感と旨味を感じやすい。この内の旨味は、ブルゴーニュではわりとよく見かける、ブドウの梗も発酵に使う全房発酵という技法を一部採用している影響もあるとおもわれる(メゾン・ジョゼフ・ドルーアンは2005年から全房発酵を取り入れている)。ブドウの皮とは違うフェノール類の旨味とスモーキーさがある。
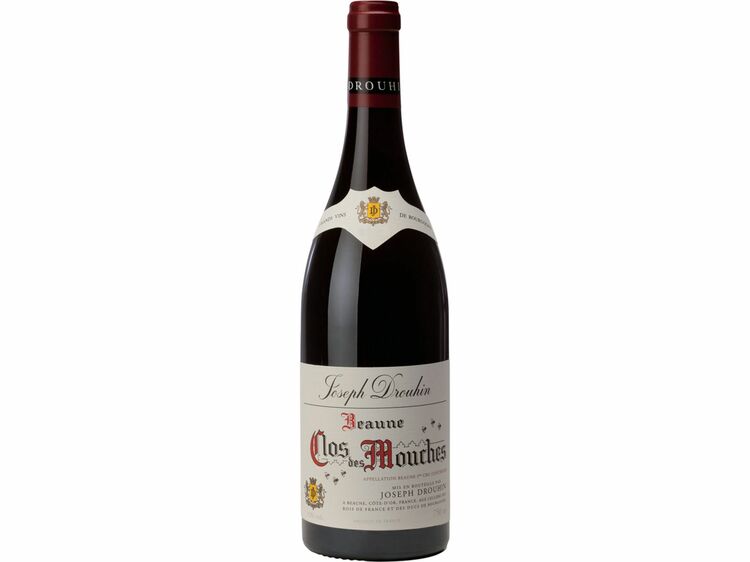 ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ムーシュ ルージュ
ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ムーシュ ルージュ
そして本命の白ワイン(シャルドネ)。
モンラッシェの方は、そもそもラギッシュ公爵家という貴族が1363年から所有していた、モンラッシェの中では最大のひとつづきの畑で、ピュリニー・モンラッシェ側にある。1940年代に、モーリスはここのワインを買っていたのだけれど、質に満足できず、1947年に醸造はドルーアンでやりたい、と申し出た。それ以来、この畑はドルーアン家の管理下にある。現在の畑の面積は2.06ha。
 こちらも石垣に囲まれた美しいモンラッシェの畑。一生モノの経験になるようなワインがここから生まれる
こちらも石垣に囲まれた美しいモンラッシェの畑。一生モノの経験になるようなワインがここから生まれる
今回は2022年、2017年、2011年のものを試すことができた。基本、2022年はおいしい。引き締まったこの畑の特徴と、温かい年ならではのよく熟した果実という、好相性のワインだ。ただ、ちょっと難しい年なんじゃないかと想像していた2017年のバランスがものすごくいいのは意外かつとても好みだった。そして2011年となるとかなりの熟成感があるかとおもいきや、全然、エネルギッシュだし、金属のような固く冷たい雰囲気がある。それがグラスのなかで空気に触れ、温度が上がって、徐々にふっくらとしていくのは実に贅沢な経験だ……
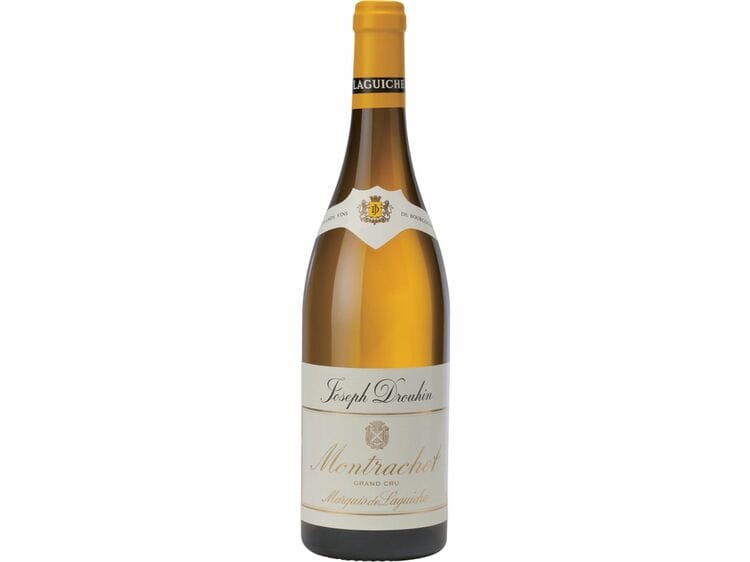 モンラッシェ グラン・クリュ マルキ・ド・ラギッシュ
モンラッシェ グラン・クリュ マルキ・ド・ラギッシュ価格は公式にはオープン価格だが小売で1本20万円から、といった高級品
対するクロ・デ・ムーシュは……モンラッシェの方が値段が7倍くらい高いのだけれど、あえて負けていないと言いたい。そもそもメゾン・ジョゼフ・ドルーアンはシャルドネに樽を使うスタイルだけれど、果汁が果皮に触れることや酸化、さらに還元反応に対して、よりおおらかになっているとのこと。
 ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ムーシュ ブラン
ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ムーシュ ブラン何年のものをいつどう買うかにもよるけれど、価格は2~3万円付近から
試したのは2023年、2018年、2012年で、2023年からしてこれは!という高級感があった。まろやかで、控えめでありながら、上質でしっかりとした酸味とそれに寄り添う苦み。個人的には2018年が好みだった。そもそも良いヴィンテージだとおもうけれど、味わい深いグルマンな白ワインに仕上がっていて、かつ、酸も非常に美しい。2012年はかなり熟成感があるけれど、年月を経た白ワインが好きな人にはそれも好ましい要素だろう。酸は強く、スパイシーかつ赤いリンゴのようなジューシーさもある。こちらもグラスの中で時間が経つと、どんどん華やかになる。
と、以上で、特に結論のようなものはなく、このレベルまでくると素晴らしいとしか言いようがない。こういうワインを知ってしまうと、ブルゴーニュワインの虜になる。やっぱりメゾン・ジョゼフ・ドルーアンはブルゴーニュワインのど真ん中だ。参りました!


