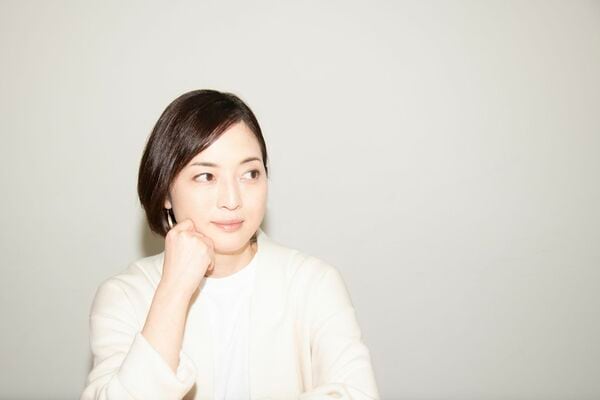(取材・文:松原 孝臣 撮影:積 紫乃)
はじめて氷上に立ったときから、どれくらい時間が過ぎただろうか。
選手として、プロスケーターとして、今日では指導にあたり、あるいはメディアなど氷上以外でも幅広い形で、フィギュアスケートとともに歩んできた。八木沼純子はフィギュアスケートの半世紀近い流れを知る人であり、そしてその発展にさまざまな立ち位置で寄与してきた、している人でもある。
長年、フィギュアスケートとともに生きる中で感じてきたこと、現在、そして未来をどう見ているのか。まずはその足跡をたどりたい。
スケートとの出会い
八木沼は東京都内に生まれ育った。スケートと出会ったのは5歳の頃だ。
「家の近くの品川プリンスホテルの中に当時、スケートリンクがありました。友達と一緒にそこで開催されていたお教室に通うようになったのです」
そのとき、出会いがあった。リンクで指導にあたっていた福原美和氏だ。1960年スコーバレー、1964年インスブルックと2度オリンピックに出場している。実は福原氏と八木沼の母は高校の先輩、後輩という間柄であった。偶然の再会を機に、福原氏に教わることになった。
「優しい先生でした。最初は」
と笑顔を浮かべ、続けた。
「試合に出るとなった途端、先生の目の色が変わりましたね。厳しかったです」
当時はその厳しさをそのまま受け止めていたという。
「学校の先生もそうですけど、厳しい先生がいっぱいいる時代だったので、こういうものだという自然な感覚でした」
今だからこそ、気づくこともある。
「試合に出るとなったときには、ときとしていい意味で厳しく導いてあげる、試合への準備のサポートも大切なのかなと思います。思うような演技ができないと子どもたちも試合に恐怖心を抱いてしまったり、やりたくないと感じかねないと思うんです。ですから福原先生が私に対して厳しかった意味は、今考えると分かります」