テネシーウイスキーの代名詞「ジャックダニエル」が『Jack Daniel’s 10Years Old』を100年以上ぶりに復刻し、日本でも2025年8月からオーセンティックバーなどの一部料飲店にて、数量限定で展開を開始する。この発表に8代目マスターディスティラー クリス・フレッチャーさんが来日。そもそもジャックダニエルとはどんなウイスキーブランドなのか? 話を聞いた。
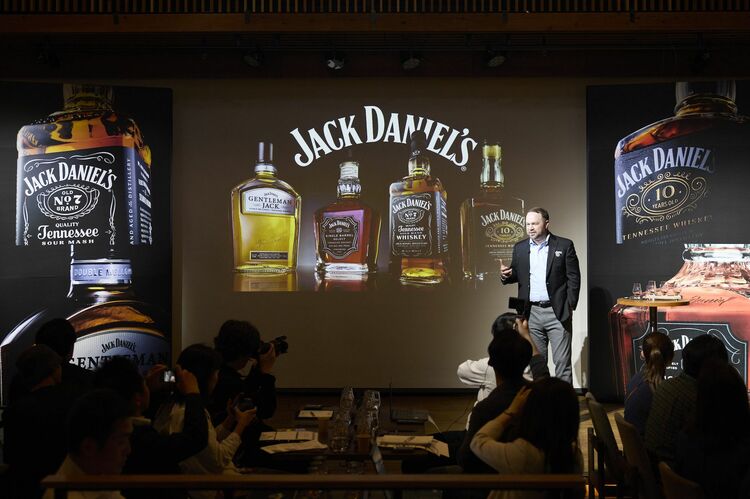
ウイスキーはイースト(酵母)で決まる!?
私がワインが好きな理由は単純で、ブレるからだ。ブドウの生育、発酵、熟成には人間が把握しきれないほど複数の要素が影響し、2度と再び同じことが起こらない。つまり同じワインは2つとないのが私にとってのワインの最大の魅力だ。
ウイスキーも、樽の中に入っている高アルコール度数の液体は、時間の経過によって樽の木材のなかに入ったり出たり、揮発したりして変化するから、2度と再び同じものが造られない。そこに魅力を感じている。
ただ、蒸溜前のウイスキーが持つ個性は、その後に控える蒸溜によって、だいぶ薄れるものだとおもっていた。もちろん、蒸溜前の液体であるニューメイク(ニューポット)の重要性は多くのウイスキーの造り手から聞いているし、使用する穀物がモルトでもグレーンでもさして変わらないなんて話は暴論だとはおもう。ただ、少なくとも発酵は、醸造酒ほどは結果に大きな影響を及ぼさないと考えていたのだ。
だから クリス・フレッチャーさんが「ウイスキーの半分は発酵で決まり、残り半分は熟成で決まる」と言った時、新鮮な意見だと感じた。それで本人にそれを伝えると
「何を言っているんだ。イーストがウイスキーを決めるんだよ。特にジャックダニエルではそうだ。私たちは発酵に7日程度かける。アルコール度数は 12%くらいまでいく。イーストを長時間活動させ、その力をフルに利用するんだ。こうして生まれる風味がジャックダニエルのウイスキーのアイデンティティになる」
 クリス・フレッチャー
クリス・フレッチャージャックダニエルの8代目マスターディスティラーであり、5代目マスターディスティラー フランク・ボボの孫。人口わずか600人の町、リンチバーグに生まれ、代々受け継がれてきた蒸溜所で働いている。映画館もショッピングモールもない町で、幼少の頃からジャックダニエル蒸溜所が遊び場だったことを誇る。化学の勉強をしてからウイスキー造りの仕事をはじめ、2014年、マスターディスティラーを継ぐべく故郷に戻った。2020年から現職
発酵を起こすのには以前の発酵の残りを使う、サワー・マッシュという方法を使い、蒸溜は銅製のコラムスチルで一度。これでアルコール度数70%まで高めて樽に詰める。
ジャックダニエルというと、チャコールメローイングという工程が有名だけれど、それ以外にも個性的な工程があるのだった。
そのチャコールメローイングについては誤解されている場合があるようで クリス・フレッチャーさんは、この工程は「ニューメイクに味付けする工程」ではないと強調する。
チャコールメローイングはサトウカエデを焼いた炭を桶のようなもののなかに入れて、そこにポタポタとニューメイクを垂らす工程。ここで炭の味がニューメイクにつくようなことはなく、これはむしろウイスキーから余計な成分を取り去る、ろ過・フィルタリングに近い。ジャックダニエル的に言えば「ウイスキーを磨く」工程だ。
 この桶の中にサトウカエデを焼いた炭が入っている。そこを通してニューメイクを磨く。この工程に6日ほどかかるとのこと
この桶の中にサトウカエデを焼いた炭が入っている。そこを通してニューメイクを磨く。この工程に6日ほどかかるとのこと
ジャックダニエルのニューメイクはコーン80%、モルト12%、ライ麦8%というレシピで造られる。主体となるコーンに由来する一種の油っぽさ、コーン臭さを取り去り、まろやかさとフルーティネスを残すのがチャコールメローイングだ。サトウカエデの炭を焼くのにはジャックダニエルのニューメイクが使われるので、石油などの燃料の風味がウイスキーにつくことはないし、炭づくり専門のスタッフがいるとクリス・フレッチャーさんは補足する。
もしも、その説明に疑問があるなら「ジェントルマンジャック」というジャックダニエルの定番ウイスキーを、もっとも定番のジャックダニエル「Old No.7」と比べてみるとわかりやすい。樽詰め前にチャコールメローイングを行うだけの「Old No.7」に対して、ボトリング前にもう一度チャコールメローイングを行う「ジェントルマンジャック」は、よりなめらかでさっぱりしていると感じられるはずだ。
 Jack Daniel's Gentleman Jack
Jack Daniel's Gentleman Jack「ジェントルマンジャック」はウイスキーの独特の強い風味が苦手、という人にもオススメしたい爽やかなウイスキー
そして
「考えてもみてください。コーンからこんなリンゴやシトラスのような風味を感じますか?」
最初の話に戻るけれど、ジャックダニエルはチャコールメローイングした上に蒸溜し、場合によってはさらにチャコールメローイングをする。磨きに磨き込まれるからこそ、それでも残るニューメイクの個性が重要で、それは醸造が重要だということなのだろう。すっかり風味の抜け落ちたエチルアルコールを樽で風味づけしたのがウイスキーというわけではないのだ。
ジャックダニエルの残り半分を決める樽熟成だけれど、これについては、どんなウイスキーの造り手も一家言あるところではある。
ジャックダニエルはトースト(遠赤外線加熱)とチャー(直火焼き)を行ったアメリカオークの新樽のみを使い、バレルハウスと呼ぶ建物に保管して熟成するのが基本。当然ながら樽それぞれで微妙にウイスキーの個性は異なるもので、その差異をブレンドによって均して、いつものあのウイスキーへと仕上げていくのがウイスキーメーカーの仕事だ。ジャックダニエルで言えば「Old No.7」や「ジェントルマンジャック」はそういうウイスキーだけれど、このあたりは、どのウイスキーメーカーでもそんなに大きなちがいはない。ただ、あえてジャックダニエルのちょっと個性的なところを挙げるなら、寒暖差が大きく揮発が多いというバレルハウス上階の樽のなかから、これぞという樽を見つけたら、その樽のウイスキーだけをボトリングする「シングルバレルセレクト」という商品を販売していること。さらにお客が望むのであれば、1樽まるごと購入も可能ということだろうか。
 Jack Daniel's SINGLE BARREL SELECT
Jack Daniel's SINGLE BARREL SELECT
限定商品の話をはじめるとキリがないのだけれど、ジャックダニエルは均一性よりも差異、ブレを楽しむようなウイスキーを出してくることが結構ある造り手のひとつだ。
そのままが美味しい「Jack Daniel’s 10 Years Old」
さて、今回、クリス・フレッチャーさんが来日した目的は今年8月頃から数量限定で、日本の一部オーセンティックバーで提供されるという「Jack Daniel’s 10 Years Old」を紹介するためだったのだけれど、これは4~8年程度熟成させる「Old No.7」を、10年間熟成させたものだと考えておけばよいようだ。
 Jack Daniel’s 10 Years Old
Jack Daniel’s 10 Years Old
ただ、厳密には、樽の置き場所を、最初の7-8年はバレルハウスの上階、残りの2-3年は低層階と変化させて、成分の揮発をコントロールしているそうで、そういう意味では、「シングルバレルセレクト」的な雰囲気を併せ持った「Old No.7」なのかもしれない。
とはいえ「シングルバレルセレクト」ほどダークでヘヴィーではない。だからやっぱり「Old No.7」寄りのキャラクターではある。そのうえで「Old No.7」よりも複雑で多面的だ。グラスから立ち上る香りにはサンダルウッドのような爽やかさが混ざり、これだけで魅力的。舌触りは「Old No.7」よりもさらにまろやかで、甘いフルーツやキャンディー、カラメルのようなニュアンスもさらに複雑性に富む。ややツンとした、新鮮味のあるタンニンも感じられるし、全体にわずかに旨味のある塩味のニュアンスも感じられる。
創業者ジャック・ダニエル時代(ジャック・ダニエルの生年は諸説あるが1846-1911年)には、10年熟成モノは通常ラインナップとして存在していたらしい。それをこのほど、100年以上のブランクを経て復活さぜたのだそうだ。カクテルなどにも使いやすい「Old No.7」、より軽快で爽やかな「ジェントルマンジャック」、一期一会を楽しむ「シングルバレルセレクト」および各種限定品に対して、「10 Years Old」はゆっくり時間をかけてウイスキーそのものに向き合うのが向いていそうなウイスキー。うまくキャラクター分けができているとおもう。10年モノのウイスキーなんて、メーカーのラインナップに無い方が珍しいくらいだし、古くて新しいスタンダードとして、これは定番のラインナップに加えたらいいのではないだろうか?


