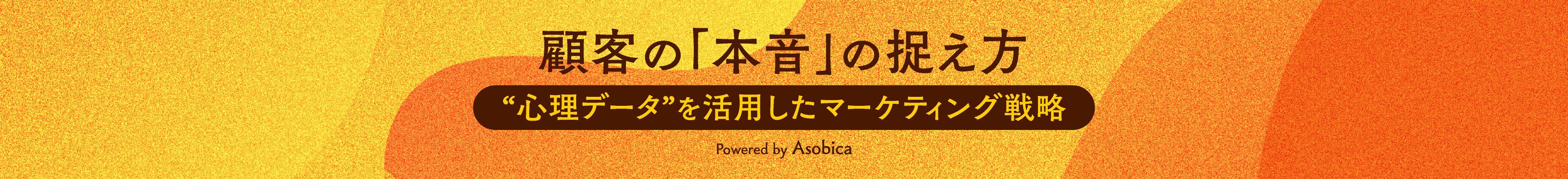Mizkan Holdings 執行役員 ZENB事業マーケティング&ダイレクトグループ グループリーダー 佐藤武氏
Mizkan Holdings 執行役員 ZENB事業マーケティング&ダイレクトグループ グループリーダー 佐藤武氏
顧客体験とブランド価値の向上を目指すカンファレンス「CX+ Summit 2025 ~『CX to BX』"ホンネデータ"からはじめるビジネス変革~」(主催:Asobica)が5月16日(金)、東京・品川で開催された。カンファレンスはオフラインで開催され、SUBARUやパルコ、Mizkanなど、ブランド戦略に定評のあるさまざまな業界の企業が登壇し、多数の参加者を集めた。その内容が7月8日(火)から10日(木)の3日間のみオンラインでアーカイブ視聴ができるという。配信に先立ち、本記事でセッションの見どころを紹介しよう。
▼「CX+ Summit 2025 ~『CX to BX』"ホンネデータ"からはじめるビジネス変革~」
大好評につき、7月8日(火)~10日(木)の3日間のみ期間限定でアーカイブ配信!
詳細はこちら(登録無料)
※本イベントの受付は終了いたしました
SUBARUやDAISOは顧客の声をいかにして活用しているのか
「CX+Summit 2025」は、デジタルデータだけでは捉えきれない顧客の本質的な声や感情に焦点を当て、「未来」を見据えながら「現在」の顧客を立体的に理解するためのカンファレンスだ。
「CX向上戦略」「競争力を生み出すデータ戦略」「選ばれるブランドに必要なコミュニケーション戦略」など、顧客の本音や感情を可視化する実践手法と、それを活用したビジネス成長の事例を、業界の垣根を越えて共有された。
さまざまな業界を代表する企業が登壇する実践的なセッションは、多くの参加者に好評だった。
セッションの一つ、「顧客体験の"ホンネデータ"が変えるこれからのCX戦略」では、SUBARUマーケティング推進部 宣伝課課長の安室敦史氏、電通 スタートアップグロースパートナーズの高井俊輔氏、Asobica 代表取締役 CEOの今田孝哉氏が登壇。アンケートや行動データなどの従来の調査手法の限界を超え、心理的安全性の高い場で得られる“ホンネデータ”を活用し、顧客体験を起点とした全社的なBX(事業変革)を実現する取り組みが紹介された。
外食・デリバリー業界でも顧客理解と関係構築の重要性が増している。セッション「外食/デリバリー業界におけるCX向上戦略」では、「塚田農場」などを運営するエー・ピーホールディングス 取締役 上席執行役員 兼 エー・ピーカンパニー 代表取締役社長の横澤将司氏と、「銀のさら」などを運営するライドオンエクスプレスデジタルマーケティング部プリンシパル 兼 エクゼクティブマネージャーの渋谷和弘氏、Asobica 取締役 CCOの小父内信也氏が、外食・デリバリー業界のリアル店舗において「顧客の声」を起点に、CX向上にどう取り組むべきか実践例を基に意見を交換した。
多くの企業が顧客の声に耳を傾ける重要性を認識する一方、「集めた声をどう活かせばいいのか」「商品開発までどう繋げるのか」という課題に直面している。セッション「ロッテ『クーリッシュ』に学ぶ、顧客の声を活かした商品開発」では、「飲むアイス」で知られるロッテ「クーリッシュ」を題材に、SNS等で寄せられる顧客のリアルな声をどのようにインサイトとして捉え、具体的な商品開発やマーケティング施策に結びつけているのか、ロッテ マーケティング本部 第一ブランド戦略部 クーリッシュブランド課 マネージャーの渡辺和哉氏、マーケティング本部 第一ブランド戦略部 コミュニケーション企画一課の佐藤洸輔氏に、カラビナハート 執行役員 シニアコンサルタントの吉田啓介氏がインタビューし、その実践的なプロセスを深掘りした。
当日のカンファレンスの参加者は、顧客と従業員の本音の声の活用がビジネスの成長を左右すると感じた人が多かったようだ。セッション「従業員やお客様の声を活かした、"ホンネ"起点の価値創造」は、そうした参加者の関心や気づきに応える内容となっていた。大創産業 グローバル社長室 グローバル情報システム部 グローバルDX企画課の山田亜梨沙氏、Asobica VP of Strategy 事業推進室 室長の佐藤頌太氏が対談。DAISO、Standard Products、THREEPPYなどを展開する大創産業の事例を基に、EX(従業員体験)をCX(顧客体験)に繋げる秘訣やデータ活用の進化と未来について解説された。
▼「CX+ Summit 2025 ~『CX to BX』"ホンネデータ"からはじめるビジネス変革~」
大好評につき、7月8日(火)~10日(木)の3日間のみ期間限定でアーカイブ配信!
詳細はこちら(登録無料)
※本イベントの受付は終了いたしました
セール品ばかり購入するからといって「お得好き」とは限らない
激変する市場環境の中、データ活用の結果共有や現状分析だけでは、事業成長は望めない。真に必要なデータ戦略とは何なのか。
そこで、セッション「競争力を生み出すデータ戦略」では、パルコ 顧客政策部部長 兼 J.フロント リテイリング 経営戦略統括部 グループ経営企画部専任部長(グループ顧客戦略担当) 兼 パルコデジタルマーケティング 社外取締役の安藤彩子氏、ブレインパッド 執行役員 Chief Marketing Officerの近藤嘉恒氏、Asobica VP of Strategy 事業推進室室長の佐藤頌太氏を迎え、タネトシカケ 代表取締役 兼 はなまる マーケティング本部 CMO 兼 一般社団法人 マーケティングギルドコミュニティ 代表理事の髙口裕之氏がモデレーターとなって討論が行われた。
安藤氏は、化粧品・アパレルなどのメーカー、小売企業などでCRM戦略策定などに携わってきた経験を基に「データの活用には適切な『問い』により仮説を導き施策を実行していく必要があるが、従来のデータ分析の手法はお客様の購買履歴が中心にならざるを得なかった」と語る。
 パルコ 顧客政策部 部長 兼 J.フロント リテイリング 経営戦略統括部 グループ経営企画部専任部長(グループ顧客戦略担当) 兼 パルコデジタルマーケティング 社外取締役 安藤彩子氏
パルコ 顧客政策部 部長 兼 J.フロント リテイリング 経営戦略統括部 グループ経営企画部専任部長(グループ顧客戦略担当) 兼 パルコデジタルマーケティング 社外取締役 安藤彩子氏
そのために、セール品ばかりを購入する顧客を「お得好き」と考えてコミュニケーションしていたが、実際にはメイン商品を安価な時期に購入する層だと分かった例もあった。これでは、本来のロイヤルティーがどこにあるのかを見落としかねない。
近藤氏は「マーケティング担当者は顧客軸でデータ分析をするが、ブランドマネジャーは競合分析などの商品視点で分析をする傾向がある。そこに仮説のずれが生じる」と指摘する。
安藤氏は、「他のショップでも同じ商品が同じ価格で購入できるのに、なぜパルコで購入いただいたのか。お客様の『気持ち』を測ることが大事だと考えている」と話した。
顧客の本音データで経営を支援するプラットフォーム「coorum(コーラム)」を提供するAsobicaの佐藤氏は「データ活用というと、お客様を購入というゴールに向かわせるために定量的なデータを集めることと捉えがちだが、大切なのは、お客様がなぜ来店いただき、購入されたのかという『Why』すなわちお客様の心理を理解すること」と語った。
安藤氏は「パルコは演劇や音楽などのエンターテインメント事業も行っている。そこに共感して、商品もパルコで購入するというお客様も少なくない。その『共感行動』に寄り添うことが大切になってくる」と話した。
まさに、人の行動の裏にある気持ちを理解することがビジネスの成功のためにますます重要になっていくわけだ。
▼「CX+ Summit 2025 ~『CX to BX』"ホンネデータ"からはじめるビジネス変革~」
大好評につき、7月8日(火)~10日(木)の3日間のみ期間限定でアーカイブ配信!
詳細はこちら(登録無料)
※本イベントの受付は終了いたしました
MizkanとSpotifyに聞く「顧客の声」への向き合い方
Mizkanから誕生したプラントベース食品D2Cブランドの「ZENB(ゼンブ)」と、音楽ストリーミング大手Spotify。異なる業界のリーダーが登壇し注目されたのが、セッション「選ばれるブランドに必要なコミュニケーション戦略」だ。 Mizkan Holdings 執行役員 ZENB事業マーケティング&ダイレクトグループ グループリーダーの佐藤武氏と、Spotify Japan 執行役員 営業本部長の田村千秋氏が対談した。髙口裕之氏がファシリテーターを務めた。
「ZENB」は動物性の原料を使用せず、普段捨ててしまうような皮や種なども全て利用するホールフードの考え方を採用している。また、主力商品には黄エンドウ豆を使用し、たんぱく質と食物繊維が豊富、かつグルテンフリーであることも大きな特長だ。
佐藤氏は「当初はエシカル消費、サステナブルといった考え方に共感する層をターゲットにしていたが、それだけではなかなか買っていただけなかった。市場に投入してみると、グルテンフリーや豊富なたんぱく質、糖質が抑えられるといったことを評価して継続購入いただくお客様が増えてきたこともあり、それらの便益を訴求することにシフトした」と成功の要因を語った。
Spotifyは音楽ストリーミングサービスの世界最大手だ。田村氏は「人の気分や感情といった『マインドベース』『ムードベース』のデータを基に、その時々にユーザーの聴きたいものを届けるアルゴリズムによるプレイリストが『私のことをよく分かってくれている』という体験を提供している」と説明した。
 Spotify Japan 執行役員 営業本部長 田村千秋氏
Spotify Japan 執行役員 営業本部長 田村千秋氏
セッションでは両社のターゲット像の設定やそれに対する訴求戦略などが紹介された。その上で、有形と無形という違いはあるものの、両社に共通するのは時代環境の変化にも対応しながら、顧客の「本能と感情」を捉え、提案を行っていることだと確認された。
魅力的なセッションが目白押しの「CX+ Summit 2025」。2025年7月8日(火)から7月10日(木)の3日間限定でオンライン視聴ができる。関心をお持ちの方は、ぜひ申し込むことをおすすめしたい。
<PR>
「CX+ Summit 2025 ~『CX to BX』"ホンネデータ"からはじめるビジネス変革~」
アーカイブ配信の詳細はこちら
〇アーカイブ期間 2025年7月8日(火)〜10日(木)
※オンライン配信(Zoom・参加無料)
※本イベントの受付は終了いたしました