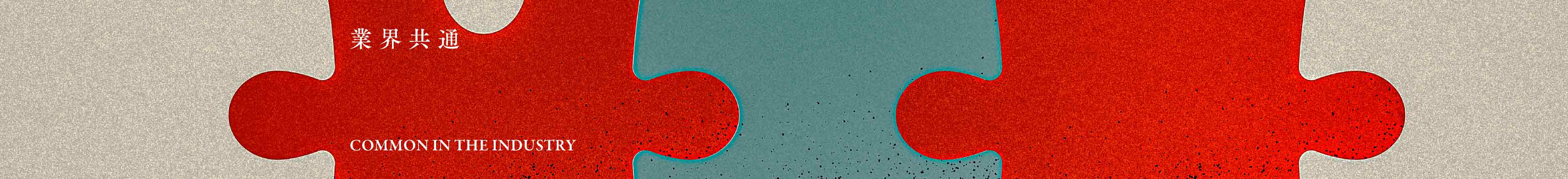金融システムに大きな影響を与えた
TCFDレポート
――2017年に起こったできごととは何でしょうか。
藤井氏 金融安定理事会による、気候関連リスクを財務情報として扱うタスクフォース(TCFD)のレポートが公表されたのです。内容は、気候変動は金融システムに大きな影響を及ぼすものであり、そのリスクを、事前に把握して財務的に対応すべきだ、というものでした。注目すべき点は、レポートが世界の主要国で構成するG20の活動の一環として出されたことでしょう。
同レポートは、企業は自らが抱える気候変動リスクを推計・評価し、財務諸表にその推計コストを計上する必要がある、としています。加えて、金融機関は投融資判断に際して「企業が環境リスクに対処しているかどうか」を評価すべき、としています。つまり、企業は自らの環境リスクを推計して開示しなければ、投融資の対象から外れる可能性が出てきたのです。
金融機関と企業は同レポートにより、気候変動の重みを突如突きつけられたのです。そういう意味で、TCFDレポートは、気候リスク、環境要因、非財務要因を重視せざるを得ないというターニングポイントの一つになったといえます。
一方で、そもそも非財務要因は文字通り「財務として計上できない要因」ですので、企業にも金融機関にも財務的に評価する術がありません。では、その方法論をどうすればよいのか。こうした背景があり、ここ数年で「非財務要因の評価手法の共通化とその開示」への対応が急速に進められています。今年が1つの山となるのではないでしょうか。
――国内外で、企業が環境リスクを定量化する動きは見られていますか。
藤井氏 もともとヨーロッパはNGOや金融市場からの企業へのプレッシャーが強く、既にそうした「評価と開示の共通化」の動きが顕在化していました。SDGsやパリ協定もその一環ですね。また、アメリカもバイデン政権になって、再生可能エネルギーシフトを含めたエネルギー産業の転換に注力し始めており、産業構造全体が環境負荷を低減する流れに向かっています。
 欧州に加え、米国も環境負荷軽減の流れを強めている (PHOTOGRAPH BY Mariana Proença / UNSPLASH)
欧州に加え、米国も環境負荷軽減の流れを強めている (PHOTOGRAPH BY Mariana Proença / UNSPLASH)
これに対して日本は、遅れをとってきました。なぜ遅いのかと言うと、企業がNGOや金融市場等の外部のステークホルダーから受けるプレッシャーが少ないことが大きいと思います。日本は戦後復興から右肩上がりに成長し、1億2千万人の良質なマーケットを抱えてきました。素晴らしい企業がたくさん生まれ、先駆的な取り組みもいろいろ進められた。ただ、その構造はバブル崩壊を経て損なわれたにもかかわらず、以前の「国内市場の成長」を前提とした「勝ち組」思考の余韻が未だに残っています。
この先、国内市場は縮小する一方なので、国内市場だけに立脚した経営のままでは、生き残れない企業がたくさん出てきます。だからこそ、企業は戦略を変えなければいけない。にもかかわらず、これまでは外部からの圧力もあまりありませんでした。しかし、ここにきてグローバルで見られるような動きが、ようやく日本でもみられるようになってきました。
――具体的にどのような動きでしょうか。
藤井氏 例えば、去年、みずほフィナンシャルグループに対して日本の環境NPOが行った株主提案です。この提案では、気候変動への対応を定款に組み込むことが求められ、内外の株主の3割強の賛同を得ました。
今年に入ってからは三菱UFJフィナンシャル・グループに対しても、国内外のNGOから株主提案が行われました。同様に住友商事でも、海外のNGOが気候対応を求める株主提案を行っており、機関投資家も注目しています。こうしたNGOや金融市場からの要請は、今後日本国内でも活発化するはずです。企業経営者はこうした外部からの圧力に答えることを求められています。