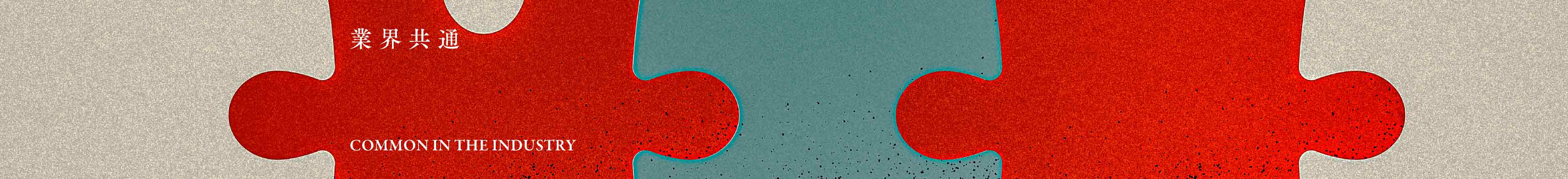顧客ニーズが多様化する中で、データの戦略的活用がより重要になっている。データを精緻に収集・統合し、分析して次の一手につなげる。これら一連のプロセスを高度化するために、AIを有効活用する。こうした体制を構築することが企業に求められるだろう。そんな中、データとAIを駆使した顧客体験価値最大化の戦略と実践について議論するイベント「PendomoniumX Tokyo Data×Al Transformation JAM 2025」が開催された。当日は、データドリブンな意思決定を行うために各社が進めている戦略について話し合われた。
1.人とAIエージェントの業務が混ざり、複雑化する時代に
2.“人”が強みの「郵便局」に、どう生成AIを取り入れるか
3.3社に見る、ユーザーデータをプロダクト改善に生かす方法
4.ユーザーが困りそうな点をデータで見つけて“前始末”する発想
人とAIエージェントの業務が混ざり、複雑化する時代に
今回のイベントを主催したのは、すべてのソフトウェア体験を意思決定と成長の資産に変えるソフトウェア体験管理(SXM)プラットフォームを提供しているPendo.io(本社:米国ノースカロライナ州ローリー、以下Pendo)の日本法人Pendo.io Japan(所在地:東京都渋谷区、以下Pendoジャパン【読み:ペンド】)である。
「今日のこの日のために、アメリカの本社から来ました。これから行われるさまざまなセッションを楽しみにしています」
本イベントの冒頭、日本語を交えてそう話したのは、Pendoの最高収益責任者(CRO)を務めるWill May氏である。同氏が在住するテキサス州の挨拶である「Howdy y'all(こんにちは、みなさん)」という言葉を参加者と一緒に口にするなど、会場は和やかな雰囲気に包まれた。

Will May氏 Pendo 最高収益責任者(CRO)
続いて登壇したPendoジャパン カントリーマネージャーの花尾和成氏は、これからのAI時代における業務の変化を推測した。
「日本の労働人口は2030年までに644万人が不足するという試算があります。これらを補うため、AIエージェントが普及していくでしょう。人とエージェントが行う業務は混ざり合い、複雑化すると考えます」
ここで重要になるのが、AIエージェントをより使いやすくし、社内で定着させること。その際に、Pendoというプラットフォームが有効になるという。
Pendoは、ソフトウェア内でのユーザーの行動データを可視化・分析することで、「使いにくさ」や「離脱のきっかけ」となるボトルネックを明らかにし、プロダクト体験の改善や定着率の向上を支援するプラットフォームだ。たとえば、特定の操作やページで離脱が多いと分かれば、その場面でガイドを表示して操作をサポートするなど、課題に対して的確なアクションを柔軟に実装できる。
「我々はAIエージェントについても、同様に体験管理ができる機能を開発中です。近々皆さまに発表できる予定です」(花尾氏)

花尾 和成氏 Pendoジャパン カントリーマネージャー
主催社挨拶では、Pendoのプロダクト統括SVPを務めるBrian Walsh氏も登壇した。同氏は「Pendoというプラットフォームは、ソフトウェアの分析と改善によって、収益拡大、コスト削減、リスク低減に貢献するものです」と力強く伝える。
その後は、実際にPendoの画面を見ながら、ソフトウェアにおける課題をどう特定し、解決していくのかを説明した。Pendoでは、ユーザーがソフトウェアをどう利用しているか、各種数値などの定量的指標とともに、アンケートやユーザーのフィードバックといった定性的な指標も取得できる。さらにこれらをAIで分析し、「ソフトウェアがどれだけユーザーから“愛されているか”を把握できます」と話す。また、「セッションリプレイ」機能を使うことで、ユーザーが実際にどのように操作したかを、個人情報を自動的にマスキングした状態で可視化・再現することも可能だと紹介した。これは実際の画面録画ではなく、ユーザーの操作イベントや画面の構造情報をもとに再構築されたもので、ユーザー体験の背景やつまずきを把握するのに役立つという。
イベントでは、架空の旅行予約システムを例に、ソフトウェアの課題分析から解決までの流れを説明した。この中では、AIエージェントを使ってユーザーの抱える課題を特定し、優先順位をつけた上で「ガイド」により解決するプロセスが示された。
さらに、先述したAIエージェントの体験管理サービスについても、その構想の一端が伝えられた。「人とAIエージェントがどのようにやり取りしたか、前後の部分も含めて分析します。これによりAIエージェントのROI(投資対効果)やインパクトを測定することが可能に。AIを使った場合とそうでない場合の比較もできるようになるでしょう」

Brian Walsh氏 Pendo プロダクト統括SVP
“人”が強みの「郵便局」に、どう生成AIを取り入れるか
基調講演では、日本郵政 常務執行役・グループCDOの飯田恭久氏と、AI研究者でありGenesisAI 代表取締役社長/CEOを務める今井翔太氏が登壇し、「ユーザー体験を次のステージへ~データ・AIは最強のビジネスパートナー~」というテーマのセッションが行われた。モデレーターは、ノンフィクションライターの酒井真弓氏が務めた。
飯田氏は日本郵政に来る前、楽天USAの社長として、米国を拠点にインターネット業界での事業拡大の基盤作りに従事した経歴を持つ。その後、2021年から現職となり、日本郵政グループのDXを推進してきた。
全国に2万4000ある郵便局には、人のオペレーションが定着している。「その中で、IT企業から来た私が『DXをしましょう』と伝えても、社員の共感を得にくいと考えました」と、“入社直後”を振り返る。だからこそ、まずはDXとは何かを明確に定義することから始めたという。
「日本郵政グループのDXは『郵便局のお客さまの体験価値を、徹底的に高めること』と社内外に宣言しました。さらに当時、当社では『デジタル郵便局』の構想が進んでいましたが、私たちが目指すのは、郵便局の強みである人の力とデジタルをうまく融合させて、郵便局を進化させることです。そこでデジタル郵便局ではなく、『みらいの郵便局』と言い換えました」

飯田 恭久氏 日本郵政 常務執行役・グループCDO 日本郵便 常務執行役員 DX戦略部、JPデジタル 代表取締役CEO
その後、同社ではさまざまなDXが進められている。日経新聞の1面にも取り上げられ、直近話題となった取り組みとして紹介されたのが「デジタルアドレス」だ。住所を7桁の英数字で表すサービスで、一度登録すると引っ越しても同じ番号を持てる。日本の住所は複雑性が高く、簡略化することで間違いが減り、配達員の負荷も低減される。
この取り組みに対し、AI研究者の視点でコメントしたのが今井氏だ。「AIを最大限に活用するには、人間向けに作られていたデータや仕組み、環境を、AIに適したものに作り変える必要があります。デジタルアドレスはその視点でも有効ではないでしょうか」

今井 翔太氏 AI研究者 GenesisAI 代表取締役社長/CEO 北陸先端科学技術大学院大学 客員教授
日本郵政グループにおける「生成AIの活用」についても説明がなされた。現在、同社では社内で「生成AIの民主化」を進めているという。「生成AIはIT部門やDX部門がやるものと思われがちです。しかしそうではなく、どの部門でも当たり前に使えるようにしたいと考え、身近に感じてもらう取り組みを進めています」(飯田氏)。まずは日本郵政グループの本社に勤める約9000人(※2025年7月2日時点)から生成AIの利用を開始したとのこと。今秋には支社にも展開するという。いずれは全国約2万4000の郵便局、配達員なども含めた約40万人の社員が使う状況を作りたいという。
進行を務める酒井氏からは「AIが人の仕事を奪うという意見もありますが、飯田さんはどう考えますか?」という質問も。それに対して飯田氏は、「むしろ逆で、労働人口が減る中、テクノロジーで業務をカバーしていかなければなりません。将来の人手不足を解消するためにAIは必須の取り組みです」と答える。

酒井 真弓氏 ノンフィクションライター
講演の終盤では、AIに対する企業の向き合い方について、今井氏の考えが述べられた。「これからの時代は、AIに任せる勇気を持ちましょう。一人一人の方が、AIという社員を持った経営者の感覚になることが大切だと思います」
今井氏によれば、AIエージェントが代替できる人の作業時間は、約7カ月おきに倍増しているとのこと。2028年〜2031年頃には「人が1カ月ほどかけて行う作業をAIエージェントがまかなえると考えています」と話す。こうした進化の中で、AIに任せる勇気が重要とのこと。
ただし技術進化が早い分、今の機能を大きく超えるAIが翌日・翌週に出てくるケースもある。すべてに素早く飛びつくのではなく、慎重に待つことも重要だという。
3社に見る、ユーザーデータをプロダクト改善に生かす方法
分科会1では、kubell、弥生、スマートドライブという3社のDXキーパーソンが登壇し、「成長プロダクトの開発を手掛ける3社に聞く変化の速い市場で選ばれるための、顧客起点×データドリブン戦略」をテーマにセッションが行われた。モデレーターはPendoジャパンの大山忍氏が務めた。
冒頭で大山氏は、「変化の速い市場では、いかに顧客を深く理解し、迅速に意思決定しながらプロダクトを磨いていくかが問われます。今回は、顧客志向を徹底しながら事業を成長させている3社がどうデータをプロダクトに生かしているのかを伺います」と話した。
国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」などを展開するkubellの福本大一氏は、ユーザーの利用時間が長いというプロダクトの特性上、どのようなアクションをユーザーが起こしているかというデータが膨大に蓄積されていると話す。その中で、有料移行するユーザーは、どういった行動をどれくらいの頻度で行っているかなどの傾向を分析していくという。

左:住澤 大輔氏 弥生 次世代本部 次世代戦略部・シニアマネジャー
中央:福本 大一氏 kubell VP of Marketing
右:塩尻 晋也氏 スマートドライブ プロダクト本部 プロダクトマネージャー
「例を挙げると、Chatwork内でユーザーが作っているグループ数や、チャットによるコミュニケーション頻度やアカウントのアクティブ頻度など、種々のデータから分析しています。その際にPendoを活用して、ユーザーの声を回収する、さらには社内のデータ基盤と組み合わせて仮説を立てながらプロダクト改善につなげていますね」
プロダクトの新規開発や改善においては、着手したい項目が同時に複数発生することも少なくない。それらに対して、どの項目にリソースを割き、優先的に進めるかの判断も重要になる。福本氏は、普段から以下のようなプロダクト開発・改善のスタンスを形成することが肝になると伝える。
「プロダクト開発や改善の目的は、既存の運用、負債の解消、新規開発などに分けられます。これらへのリソース配分を一定程度は決めておくことが大切ではないでしょうか。例えば、自社で使えるリソースの4割は新規開発に充てるなど。配分の方針がないと、得てして負債の解消にリソースが割かれる傾向にあります。するとイノベーションは生まれにくくなるでしょう」
企業のバックオフィス支援ツールなどを展開する弥生の住澤大輔氏は、同社のKGI(経営目標達成指標)から逆算したデータ分析を実践していると話す。
「当社では、契約関連の指標をKGIに置いています。そこで、KGI達成のために重要な要素、すなわち契約関連のアクションを起こすに至る方が多い利用状況をKPI(重要業績指標)に設定しています。具体的には、製品の利用定着率をKPIとしています。給与明細ソフトであれば、どのくらいの方が定期的に給与明細を作成しているかなど。このKPIを改善するために、ユーザーの行動や離脱しやすいポイントなどをPendoで分析しています」
Pendoの導入前は、ユーザーの利用データを分析するにも、製品データベースが持っている情報に限られていたという。また、そのデータを取得するには社内のシステム部門に問い合わせる必要があり、リードタイムを要した。これらを改善し、より広範なデータを素早く分析するためにPendoを導入したとのこと。「現在はリアルタイムでより広範な利用データが可視化されるようになってきています」と話す。

「併せて、プロダクトの改善点が見つかった場合には、Pendoのガイド機能を頻繁に活用しています。特定箇所に操作説明を加えるなどの作業を、私たちがノーコードで行えるのは大きなメリットですね」
SaaS型車両管理システムなどを提供するスマートドライブでは、ウェブとモバイルアプリでサービスを展開している。これまでは各所でさまざまなツールを入れてきたため、ウェブ・モバイルアプリをまたいでユーザーの行動を把握する統一指標がなかったとのこと。「ここにPendoを導入したことで、1つのサービスをウェブからモバイルアプリまで横串でデータ分析できるようになりました」。同社の塩尻晋也氏はそう伝える。
同時にPendoのガイド機能などを使い、サポート・カスタマーサクセスの領域でも効果が出ているという。もともとサービスを使い始めたユーザーに機能などを説明する「オンボーディング」や問い合わせ対応に時間が取られていたとのこと。「ガイド機能により、お客さまがご自身でオンボーディングをできるようになったほか、問い合わせが発生しやすいポイントにガイド機能で『?』マークを埋め込み、クリックすると説明が立ち上がるようにしました。問い合わせの削減につながっています」
今までなら開発チームに依頼が必要だったプロダクト改善を、サポート・カスタマーサクセス部門がPendo上で手軽に行えるようになった点も大きいという。

そもそもPendoの導入経緯として、サポート・カスタマーサクセス部門がオンボーディングや問い合わせの負荷削減を考えていたという。一方、塩尻氏の在籍するプロダクトチームでも、先述のようにデータ基盤の課題を抱えていた。つまり、社内の複数部門で同時多発的にPendoのようなツールへのニーズが高まったという。その後、これらの部門が連携して導入していったとのこと。部門をまたがり、「ひとつのデータ分析ツールに統一できたのは大きなメリットでした」と話す。
3社が語ったのは、ユーザーデータをプロダクトに生かす実践的な手法だ。膨大なデータを分析するだけでなく、Pendoのガイド機能などを活用し、自ら素早く改善を実行することで、プロダクト進化のサイクルを加速させているのだろう。
ユーザーが困りそうな点をデータで見つけて“前始末”する発想
分科会2では、社内DXの推進に向けて、新しい取り組みを先導しているJALデジタル、中外製薬、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(以下、PPIH)のDXキーパーソンが登壇した。各社が変革を進める中で直面した課題や、それらをPendoによって解決した事例が紹介された。モデレーターは、Pendoジャパンの中村貴弘氏が務めた。
2025年4月に、旧社名のJALインフォテックから社名変更したJALデジタル。同社のDX推進に従事してきた樋口寛之氏は、システム導入や刷新を行う中で以下のような壁に直面するケースがあったと語る。
「新しいシステムを導入した際、従業員が必要とする情報がすぐに手に入らないケースがよくありました。新システムの導入時には、操作説明会の開催やマニュアル作成などを行います。しかしそこでは基本的な操作の情報しか触れないため、イレギュラーな状況が発生した場合の対処方法が見つからないケースが多く発生しておりました。そのため、サポートデスクに質問が集中し、対応に時間がかかる状況が生まれていました」

樋口 寛之氏 JALデジタル 運営企画本部 ビジネスプロセス変革部
本来は業務効率化を狙った新システムが、結果的に業務時間を増やしてしまうことがあったという。こうした事象はDXによる生産性向上を妨げ、また社内のモチベーション低下も生むと話した。
これらを解決するため、同社ではシステムに順次Pendoを導入していくという。特徴的なのは、新たに実装するシステムに入れるのはもちろん、今後更新予定となっている現行システムにも導入する点だ。
「現行システムにおけるユーザーの行動データを分析し、それを基に新システムのプロダクト選定や要件定義の設定に活用することを考えています。これまで社内システムにおけるこうしたデータの取得や分析はほとんど行っていませんでした。初の試みであり、今まさに着手し始めたところです。これからいろいろな結果が上がってくる予定です」(樋口氏)
DXを進める中で、JALデジタルと同様の課題を抱えていたのがPPIHだ。つまり、本来は業務を効率化して時間を創出するはずのDXが、かえって業務に取られる時間を増やしてしまうケースがあったといえる。
同社の小林悟海氏は、「ユーザーを理解せずに我々システム部門がシステムを構築してしまい、今度はそれらの機能を改修するため、ユーザーの方にヒアリングをお願いする場合がありました」と話す。これらが現場の手間を増やすことにもつながっていたという。
このような課題に対し、Pendoを活用して解決を図っていくとのこと。「当社では基幹システムの刷新を予定しています。ここにPendoを取り入れることにより、ユーザーからの問い合わせ削減、システムの早期定着、教育時間の短縮を目指したいと考えています」(小林氏)
小林氏によると、今後のシステム刷新により「ユーザーからの問い合わせは通常の3、4倍に増えると予想しています」とのこと。過去のシステム刷新でも問い合わせが大きく増加しており、その事例からの算出だという。これらをPendoによって少なくしようと考えている。
「まずは現行のシステムにPendoを入れて、ユーザーの行動を分析します。その結果を基に、次期システムでのガイド機能の活用を最適化したいと考えています。その場しのぎの改善ではなく、あらかじめユーザーが困りそうな点を分析し、ガイド機能などで“前始末”する。Pendoではこうしたことができるのではないでしょうか」
この言葉を受けて、「前始末という表現は印象的ですね」とモデレーターの中村氏。「小林さんがおっしゃった通り、システム上のユーザー行動を分析することで、事前に問い合わせ増などを予防することができます」と話した。

小林 悟海氏 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ITサポート本部 情報システム部 システムサポート課 課責任者
2019年頃からDXを進めてきた中外製薬では、デジタルやITによるプロダクト・サービスを次々と社内に導入してきた。ただし、同社の田畑佑樹氏は「導入後の振り返りや評価が不足しており、取り組みの継続をもたらす仕組みを作る必要がありました」と課題感を話す。
中外製薬では、新システムやサービスをPoC※(概念実証)の形で積極的に入れる文化が強く、初期導入のハードルは低い。しかしその先で「入れたものを正当に評価し、良いものは広げていくプロセスに課題があったのです」と付け加える。
※PoC:新しいアイデアや技術、システムなどが「実現可能かどうか」を検証するために、小規模に試験的に行う取り組み
そこで同社はデータを軸に上記の解決を図る施策を行っている。具体例として田畑氏が紹介したのは、同社が内製開発した生成AIアプリケーション「Chugai AI Assistant」へのPendo活用だ。このAIは社員全員が使う社内基盤であり、より良いものにするためにユーザー体験を定量評価する必要があった。そこでPendo導入に至ったという。

田畑 佑樹氏 中外製薬 デジタルトランスフォーメーションユニット デジタル戦略企画部 ビジネスアーキテクト 1グループマネジャー
「Pendoによって、提供した機能がどれだけ使われているか、フラストレーションが発生しているポイントがないかなどを把握できるようになりました。仮説に基づいて我々が開発した機能が、実際にユーザーの期待に応えているかをデータで評価できるように。うまくいっていなければ開発をやめる、よければさらに改善していくことが可能になったのです」(田畑氏)
これまで可視化や数値化が難しかったUX領域においても、Pendoを活用することで、正確なデータの取得・分析が可能になった。その結果、「良いものはきちんと次の投資につながる」という健全な流れが生まれつつあると語られた。
セッションの締めくくりでは、「Pendoに対する今後の期待」が語られた。JALデジタルの樋口氏は、「Pendoのユーザー行動データと、お客さまの販売データや予約データを突き合わせて分析したい」と述べた。例えばJALの予約システムにおいて、どのような行動をとったユーザーが最終的に予約に至ったのか、あるいは途中で離脱したのか——行動のプロセスと結果を結びつけて分析する取り組みを進めたいと語った。
社内DXの推進が、逆に業務の足かせになる。こうしたケースを生まないためにも、ユーザーの利用データを分析して、困りごとを早いうちに取り除くという考えは重要だろう。そんな示唆を与えるセッションとなった。
ここまでの前編では、各社のDXや、Pendoによる課題解決の取り組みが紹介された。後編記事では、NECや三井住友海上火災保険、KDDIのDXキーパーソンが登壇したセッションをレポートしていく。
<PR>