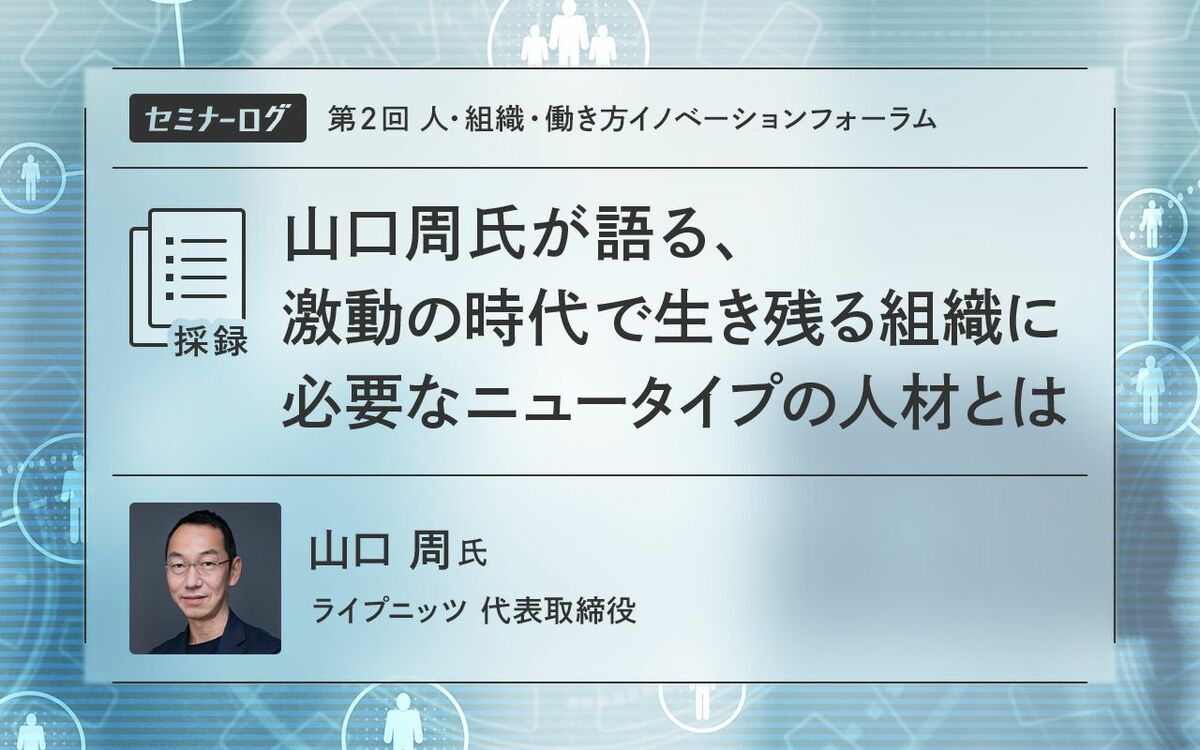
かつて「実直・誠実に取り組む」「正解を出す」「綿密に計画する」といった、誠実な問題解決型のオールドタイプ人材は大きな成果を出していた。しかし、社会環境が大きく変わりつつある中、世界では「問題を提案する」「直感で動く」「行き当たりばったり」といったニュータイプの思考・行動様式が大きな成果を生んでいる。ライプニッツ代表取締役の山口周氏が、ニュータイプ人材のあるべき姿と組織マネジメントについて語った。
※本コンテンツは、2022年11月21日に開催されたJBpress/JDIR主催「第2回 人・組織・働き方イノベーションフォーラム」の特別講演3「これから求められるニュータイプの人材像」の内容を採録したものです。
動画アーカイブ配信はこちら
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/74361
変化の時代にあって新しい問題を見つけられない、日本企業のジレンマ
20世紀の人材育成の常識は、何をおいてもビジネススクールであった。しかし、米国有数のビジネススクールの志願者数は2000年代から年々減少しているという。2016年、イギリスのフィナンシャルタイムズの記事では、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートという美術系の大学院に、17カ国から企業の幹部候補生が送り込まれているということが大きく報じられた。また、2015年のマッキンゼー・アンド・カンパニーによるデザイン会社の買収に始まり、大手のコンサルティング会社が次々とデザイン会社を買収している。
こういったトレンドの変化の理由は、これまでの方法論や経営手法では、もはや大きなインパクトが出せなくなったからだ。さらにこの変化の理由として、人材の求められる姿が大きく変わってきていることにあるといえる。端的にいうと、求められる人材が「誠実な問題解決者」タイプから、「わがままな問題提起者」タイプに代わってきているのだ。
世の中にすでに多くある問題を効率的に解くことを、非常に得意としていた日本企業は、1980年代後半の時価総額世界ランキングでは上位の半分以上を占めていた。1960年代から1970年代にかけて、日本の企業がたとえば洗濯機や冷蔵庫といった低価格で高性能な製品を世界中に輸出した結果、世界中の家電産業が消滅した。
このときに解決した問題は、「家の外に洗濯しに行くのはつらい」「食べ物が保存できないのが困る」といった非常にわかりやすいものだった。そして問題がわかりやすかった分、それを解けば確実に経済価値を生み出せたのだ。
「しかし、こういった問題がことごとく解決されてしまった今、新たな問題(新しいマーケット)を見つけることが非常に重要です。ところが、この新しい問題を見つけるという大変重要な課題で、とても苦労しているのが今の日本企業の現状だと思います」と山口氏は指摘する。
わかりやすい事例が、日本の携帯電話事業だ。2007年に日本で販売されていた携帯電話9種を見比べると、iPhone以外の端末は、一見しただけではどのメーカーのものか判別できない。日本の企業がマーケティングの手法にのっとって、顧客の望む通りの携帯電話を“誠実に”作った結果、メーカー間でほとんど差別化できず、デザイン的にも区別ができなくなってしまったからだ。
一方でアップルは、よく知られているように、顧客の声を聞かない。マーケティングの手法からすると、いわば禁じ手のプロダクトアウトである。しかしこの禁じ手をとったアップルは時価総額世界1位になった。それに対し、顧客の声に実直に耳を傾けた日本企業は同質化に陥り、顧客の望む先の物を作れず、たった10年の間にハードウエアメーカーの携帯電話事業は消滅してしまったのだ。
「この結末は、顧客の困っている問題を把握してそこに対して正解を出していくという、20世紀の行動様式、思考様式というものが、価値につながらない時代になっているということを示していると思います」
企業が新たな問題を発見するには「わがままな問題提起者」こそ必要
先ほどの、“わかりやすい問題”が枯渇している現代では、企業には問題を作り出すことが必要とされる。「問題」は、ありたい姿と現状のギャップにあると定義されるため、組織や人はまず「ありたい姿を描く」、そしてそこから「問題を作り出す」ことが求められるのだ。
「この、ありたい姿を掲げるときに、日本の企業はいきなり『市場は? ニーズは? 顧客のペインは?』 となってしまう。そんな議論から、大きな事業が出ることはありえません。海外の創業者は、独善的にありたい姿を掲げています。あえて強い言葉で言えば、彼らはわがままさゆえに、今そこにある問題、現状を“仕方のないもの”として受け入れず、自分のこととして問題を生みだし、事業を始めたのです」
これからの企業に求められるのは、正解を出すために慎重に計画したりルールに従ったりする「誠実な問題解決者」ではない。むしろ世界を批判的に観察して、誰も気づいていなかった問題を提起し、解決のために組織の空気に従わず生意気に行動する「わがままな問題提起者」であると山口氏は指摘する。
「フェイスブック 19歳、グーグル 25歳、アマゾン 31歳、アップル 21歳。これは、各社の創業者の、創業時の年齢です。平均年齢は24歳。この若い『わがままな問題提起者』たちが、世の中のあり方に対して声を上げて事業が始まり、今や世の中になくてはならない企業となっているのです」
さらに年長者と若者では、得意とする知性のあり方が異なっているという。知性には、大人としての配慮ができ、さまざまな経験の末に獲得される知性(結晶性知能)と、画期的なアイデアを出すような知性(流動性知能)の2つがある。この2つの知能のピークは大きく異なり、結晶性知能のピークはだいたい60代。一方で、画期的なアイデアを生み出す流動性知能は、10代の後半から20代の前半でピークが来てしまう。
「この画期的なアイデアを出す力をいかに取り込めるかが、企業にとっては重要な課題になります。特に、技術的な変化や社会環境の変化が大きく起こっている時にゲームチェンジを起こすのは、常に、高い水準の流動性知能を持っている人たちなのです」










