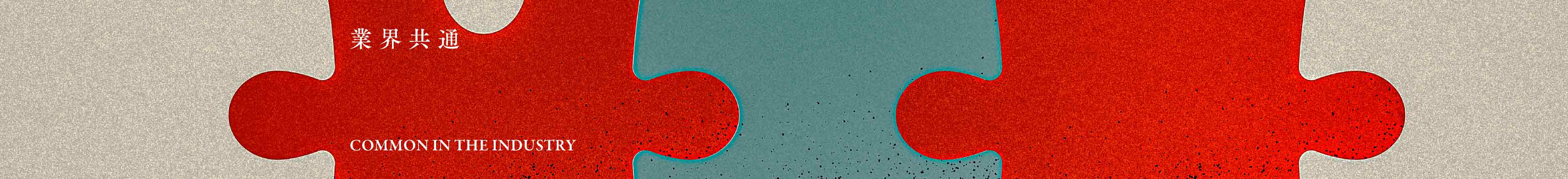日本能率協会コンサルティング 経営コンサルティング事業本部
日本能率協会コンサルティング 経営コンサルティング事業本部ビジネスプロセスデザインセンター センター長、チーフ・コンサルタント 梅田 修二氏
生産性向上や働き方改革の観点から、業務マニュアル作成が再び注目されている。定型業務を標準化することで、価値創造につながる業務にシフトするためだ。ただし、やみくもにマニュアルを作成するだけでは成果につながらない。そのポイントはどこにあるのか。業務マニュアルの作成・活用のコンサルティングで定評のある、日本能率協会コンサルティングの梅田修二氏に聞いた。
オフィスワークこそ業務マニュアル作成が必要
――生産性向上に関心を持つ企業が増えています。背景にはどのような要因がありますか。
梅田 日本の国内総生産(GDP)は米国、中国に次いで世界第3位です。ところが時間あたりの生産性は非常に低いのです。これは何を意味しているのかと言うと、これまで日本は長時間労働で成果を出してきたということです。ただしこれからは少子化により労働人口が減少するとともに、育児や介護で働く時間や場所に制限のある人が増えてきます。これまでのような長時間労働頼みの働き方は通用しなくなるでしょう。
何よりグローバル規模の競争が激しくなる一方ですから、企業は価値を生み出し続けないと生き残ることができなくなります。限られた人的リソースで価値を生むためには生産性を向上させるしかありません。企業にとって「生産性向上」は避けて通れないテーマになっています。
経営環境が刻々と変化している中で、企業はさまざまな新たな課題に対応していかなければなりません。そのためには、定型業務に掛けている時間を減らして、生み出された時間を課題解決・付加価値向上のための業務に割くようにする必要があります。日本企業は世界の中でも生産性が低いと言われますが、見方を変えれば「まだ伸びしろがある」ということです。
――定型業務はルーティン業務とも呼ばれます。日本企業はルーティン業務に無駄が多いということでしょうか。
梅田 日本企業でも製造現場の生産性の高さは世界でもトップクラスです。製造現場の生産性が高い背景の1つは、生産管理や生産技術といった専門部門が決めた効率的な作業スケジュール、作業方法で業務を行っていることにあります。
一方でいわゆるホワイトカラーと呼ばれるオフィスワークでは、専門部門の支援を受けておらず、作業スケジュール・作業方法を自分で考える必要があります。その結果、業務が標準化されず、属人的になっていることがほとんどです。このため、自分が経験したことのない業務に携わる度に、どんな手順でどのように行っていくべきか、自分で考えなければなりません。また、複数の人で同じような作業をしたり、手戻りが起きたりするような無駄も発生しがちです。オフィスワークこそ、業務を標準化してマニュアルを作成することで無駄を省き、効率を上げていくことが求められます。
最初は強制的にでも「マニュアルを活用する場」を作る
――梅田さんはかねて、生産性向上実現の有効策として「業務マニュアルの作成・活用」を提唱していますね。業務マニュアルを作成する意義や目的について教えてください。

梅田 いくつか挙げることができます。第一は、マニュアルがあることによって企業としてきちんと業務を管理できるようになることです。例えば新規の顧客企業と取引を開始する際に、どのような手順で何をすればいいのか標準化されていれば、漏れもなくなりますし進捗状況も評価できます。
第二に、業務を標準化することで業務の質を平準化できることです。誰がやっても一定の品質のアウトプットができるようになるのは価値として大きいでしょう。
第三に、マニュアル作成により助け合う職場づくりにもつながることです。今後、育児や介護のため時短勤務を余儀なくされる社員もますます増えるでしょう。昨今では家族が新型コロナウイルスに感染し、出社できなくなることもあります。そのような際にきちんとしたマニュアルが整備されていれば業務の応援や引き継ぎも可能になります。その他、マニュアルを作成することで、先輩の手が空かない時でも自分で確認できる、何度でも見返せる、教える側にとっても正しい手順を抜けもれなく教えられるといった、教育ツールにもなるというメリットがあります。
もちろん、企業によってはマニュアル作成の意義を理解しているところもあるのですが、全体的にはなかなか進んでいないのが実情です。大きな理由として、1年に1回、2年に1回など発生頻度が少なく、さらに1人か2人でやっているような業務は「担当者の頭の中」ということになりがちだというのが挙げられます。これでは、担当者の急な異動や退職で業務が止まってしまうリスクがあります。
――生産性向上に役立つマニュアルもあれば、そうではないマニュアルもあると思います。違いはどこにあるのでしょうか。
梅田 マニュアルを作る際に大切なのは「そのマニュアルをどのような人が読むのか」ちゃんと意識することです。ベテランの社員向けであれば専門用語や社内でしか通用しない略語が使われていてもいいでしょう。しかし、新入社員や派遣社員など、業務を十分に理解できていない人を対象にする場合は、丁寧に説明し、文章の表現も吟味する必要があります。私はよくマニュアルの読み手のレベル感を想定しやすいように「隣の部署のAさんに業務を引き継ぐつもりで書いてください」とアドバイスしています。
――せっかく時間を掛けて作成した業務マニュアルが活用されていないと悩む企業もあるようです。
梅田 厳しい言い方をすれば、マニュアルが活用されていないのは、活用する気がないからです。「活用しよう」という掛け声だけでは、なかなかマニュアルは活用されません。業務マニュアルが活用されない理由としては、マニュアルを使わなくても何とかできてしまうことが挙げられます。そもそもマニュアルがあることすら社員に知られていないという場合もあります。そのために、せっかくマニュアルを作成したにも拘わらず全く異なるやり方をしているケースもよくあります。
実際に「マニュアルを活用しましょう」という掛け声だけでは活用されないので、マニュアルを活用する場を強制的に作ることが大切です。そのため、月に1回担当者を通して、マニュアルに記載された手順通りに業務が行われているか相互チェックする場を設けたり、年1回はマニュアルが更新されているか総点検する場を設けたりするとよいでしょう。
マニュアル作成ツールの活用で作成・更新・管理が容易に
――生産性向上に役立つマニュアルを作成しようと考えた場合、どこから取り組み、どのようなゴールを目指せばいいでしょうか。
梅田 最初から完璧なものを作る必要はありません。私はいつも「最初は70点のマニュアルでいい」と言っています。これを見れば業務は大体できるというくらいの情報があればいいのです。その後、マニュアルを活用する中で必要に応じて情報を足していき、80点、90点と上げていきます。あらゆる情報を網羅した百科事典のようなマニュアルを作る必要はないのです。そもそもそのようなマニュアルは活用されませんよね。
――マニュアルを作成したものの作りっぱなしになっている企業もあるようです。定期的に更新し続けるためにはどのような取り組みが必要ですか。

梅田 よく「当社のマニュアルは古いままで更新されていません」とおっしゃる方がいらっしゃいます。なぜそのようなことが起きるのかというと、それはマニュアルが使われていないからという説明に尽きます。常時使っていれば、よりよい作業方法や間違いがあることに気付き更新されるはずです。また、更新作業が手間になって更新されないケースもあります。逆に、各担当者が勝手に更新するケースも珍しくないです。これらを防ぐためには、マニュアル管理責任者や更新担当者を置き、承認を得た上でマニュアルがリリースされる体制を設けると良いです。
最近では、マニュアルの作成や管理をデジタルで行えるツールも登場しています。マニュアル作成ツールを使うと、誰でも簡単に質の高いマニュアルを作成できます。また、画像やテキストだけでなく、音声や動画を活用することで視覚的に理解を促すこともできます。さらに、クラウドで提供されているツールであれば、拠点が複数に分かれていてもマニュアルの更新・共有が簡単にできます。
マニュアル作成ツールの中には、作成だけでなく運用管理までカバーしている製品もあります。利用者が必要な情報を見つけるための検索機能や、マニュアルの参照回数、更新日付等など活用状況・更新状況を管理する機能なども備えています。この他、更新の承認をツール上で行えるものもあります。業務マニュアル作成の意義である「企業としてきちんと業務を管理する」ためにも、経営者や管理責任者が確認し承認するフローが必要ですね。
――梅田さんは多くの企業でマニュアル作成を支援されています。成功する企業のポイントがあれば教えてください。
梅田 生産性向上に直結するという点で、マニュアル作成は経営者が率先して取り組むべきテーマです。担当者任せにせず、経営者・管理者がマニュアル作成活動を推進する企業は成果が出ています。
私がコンサルティングを行ったある大手製造業の企業で、人事、総務、経理など間接部門の業務のマニュアル化を進めたことがあります。管理職が「マニュアル作成は重要な仕事の一部である」という考えを社員に徹底し、就業時間内に業務マニュアル作成の時間を計画的に確保して作成にあたったことが大きな特色で、管理者の意識が非常に高かったですね。その結果、間接部門の残業時間を大幅に削減でき、生産現場の繁忙期には間接部門から応援の人材を出すといった柔軟な動きもできるようになりました。
これはほんの一例に過ぎず、日本企業には改善の余地がまだあると私は考えています。先ほどお話したマニュアル作成ツールのような心強い味方もあります。ぜひ、マニュアル作成・活用は経営戦略と一つであると考えて、明日からでも取り組んでいただきたいと願っています。

<PR>