
半導体、ディスプレイ製造装置などを製造する芝浦メカトロニクスは、好調な業績の一方で、旧態依然の業務プロセスに現場の負担が増していた。この課題を解決するため、部門横断のプロジェクトを始動。各部門から集められ、初めてのDXプロジェクトに挑戦したメンバーたちは、第一段階を成功に導いた。その一部始終を、プロジェクトリーダーとメンバーたちの声で振り返る。
1.好調な業績のかげで露呈した、属人化と情報連携不足による現場負荷
2.業務部門からDXプロジェクトメンバーを招集
3.アジャイルの考え方を学びながら開発を進める
4.課題をチームで解決するDX組織に成長
5.小さな成功体験の共有がDX文化定着への一歩
好調な業績のかげで露呈した、属人化と情報連携不足による現場負荷
芝浦メカトロニクスは、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置などの製造と販売を手がけるメーカーである。設立は1939年、2025年3月期の連結売上高は809 億円。従業員数は約1200名の企業だ。ここ数年の業績は好調で、世界的な半導体市場の拡大を受け、製造装置の需要も増加。同社製品の出荷は順調に推移している。
好調な業績の一方で、同社の事業部門ではDXに対する取り組みが進まず、情報やデータの連携が不十分な状態にあった。その結果、現場の業務プロセスに負荷がかかり、判断の遅れや無駄な作業が発生していた。中でも海外拠点での部品在庫管理は、特に大きな課題として浮かび上がっていた。
海外にもサービス拠点を抱える同社では、どの拠点でどんな注文が入っているのかをリアルタイムに把握することができていなかった。そのため、注文に見合った在庫の有無が把握できず、結果として在庫の過不足や製造機会の損失が発生していた。注文や在庫情報はExcelを共有し手作業で集計しており、報告業務に多くの人手がかかっていた。
 芝浦メカトロニクス 取締役 常務執行役員 ファインメカトロニクス事業部 事業部長 黒川 禎明氏
芝浦メカトロニクス 取締役 常務執行役員 ファインメカトロニクス事業部 事業部長 黒川 禎明氏
同社の取締役常務執行役員の黒川禎明氏もこの問題を重視しており、「デジタル化の遅れが、需要の急変などへの対応の遅れにつながることを懸念していました。現場の課題を解決するDXのプロジェクトを立ち上げる必要があると感じていました」と語る。
同社の事業部門であるファインメカトロニクス事業部で統括副部長を務める菊池勉氏も、同社のDXの遅れに懸念を抱いていた。「当社の10年後の将来像を描いたときに、目指すべき姿になれないのではないかと、危機感を持ちました。何か行動を起こさなければいけないと感じていました」。
社内にはDXを推進するための気運も乏しく、慢性的に高負荷な仕事に追われており、モチベーションの低下につながっていた。またデジタル環境の整備が遅れ、データ活用やAIなど、今後のテクノロジーへの対応も難しい状況にあった。
業務部門からDXプロジェクトメンバーを招集
こうした課題を受け、ファインメカトロニクス事業部を中心に黒川氏をトップとした「DX推進プロジェクト」がスタートした。最初の開発案件は、上記の問題を解決する部品在庫管理システムの構築とした。「小さなところから始めることが可能で、すぐに効果が確認できるDXの取り組みとして、部品のオーダー管理と在庫管理を横串でつなぐシステムをターゲットに設定しました」(黒川氏)。
このDXプロジェクトでは、2つのテーマを掲げた。1つ目が、開発者がユーザーと一体となり、ユーザーからのフィードバックを受けながら開発を進めるアジャイル手法の導入である。同社としては初めての試みだが、開発期間の短縮や、環境変化に対応できる開発手法として採用を決めた。
2つ目のテーマが、社内へのDX文化の醸成だった。アジャイル手法による開発はマクニカに伴走支援を依頼しながらも、このプロジェクトによって社内のDX人材を増やし、将来は内製化することを目標とした。
プロジェクトマネージャーを務めた菊池氏は、まず各部門の責任者に声をかけ、プロジェクト参加メンバーの選出を依頼した。「各部門には、次世代を担っていく若手メンバーにプロジェクトに参加してもらうようにお願いしました。さまざまな部門のメンバーが、違う立場で1つのものを作ることを重視しました。」
こうして、さまざまな部門から若手メンバーが6名ほど招集され、DXプロジェクトはスタートした。
アジャイルの考え方を学びながら開発を進める
プロジェクトは、まず必要な要件や最終的なゴールを定め、メンバーで議論することから始まった。
チーム内は、ユーザーの声を聞いてまとめる人(プロダクトオーナー)、開発者(デベロッパー)、開発したものに対して正しく動作できているか試験をする人(テスター)という3つの役割に分かれ、毎週の会議で進捗確認や、次にすべきことを話し合い、最終的なゴールに向かって進んでいった。この「スクラム」と呼ばれる開発手法は同社として初めての取り組みであり、マクニカの伴走支援を受け、メンバー全員が学びながら挑戦していった。
開発中には、いくつかの課題にも直面した。同社グループ内には類似した業務を行う企業が複数存在しているが、それぞれ独自のプロセスで業務を進めており、データも分散していた。そのデータを集めなければ、管理システムは作ることができない。メンバーは各社に働きかけ、共通基盤を作る意義を伝え、理解を促した。
 芝浦メカトロニクス ファインメカトロニクス事業部 ファインメカトロニクス装置統括部 統括副部長 兼 戦略企画グループ グループ長 菊池 勉氏
芝浦メカトロニクス ファインメカトロニクス事業部 ファインメカトロニクス装置統括部 統括副部長 兼 戦略企画グループ グループ長 菊池 勉氏
また、メンバーは既存の業務との兼任で参加したため、負担の増加が懸念された。プロジェクトマネージャーの菊池氏は「部門の業務量をプロジェクト側で容易にコントロールできないため、メンバーによっては負荷が非常に大きくなってしまいました。その中で、いかにモチベーションを維持してもらうかが大きな課題であり、注意したポイントでした」と語る。
黒川氏も、メンバーのモチベーション維持を意識したと話す。「メンバーには自由に伸び伸び取り組んでもらいたいと考えていました。そのため、最初から成果を求めず、失敗しても大丈夫だという雰囲気をつくることに配慮しました」。
課題をチームで解決するDX組織に成長
プロジェクトチームはこれらの課題を乗り越え、開発と試運用を進めた。その結果部品在庫管理システムは無事に完成し、現在本番稼働のフェーズに入っている。
新たな部品在庫管理システムは、ローコード開発プラットフォーム(Mendix)を用いてアジャイル手法によって開発された。同社の世界各地の拠点からExcelをアップロードするだけで、各拠点の倉庫に何個部品があるかを確認できるようになった。
この結果、従来は個別に問い合わせなければ把握できなかった情報が共有され、関係者全体で状況を俯瞰できる環境が整った。グループ内では、どの拠点がどの程度の在庫を持つべきか、各拠点がサービス対象とする製品群に対して部品の保有状況に過不足がないか、といった議論が活発に行われるようになった。それに伴い、納期対応に向けて先回りして動く取り組みへと広がりつつある。
あわせて、グループ内での回答作業やデータ作成の負担が軽減され、より生産性の高い業務に時間を充てられるようになってきている。システム化による効果を実感することは、DX文化の醸成に向け大きな前進といえるだろう。
菊池氏は「今回のシステムは、まだ全社の在庫情報を一元管理できるところまで開発が終わっていませんが、手順を踏んで開発を進め、最終的には、全社の在庫の一元管理だけでなく、得られた情報を基に発注まで賄うオールインワンのシステムを目指しています」と語る。
菊池氏は、今回のDXプロジェクトでは、メンバー同士の議論によるインナーブランディングが非常に重要だったと話す。
「課題である、業容拡大による人の手によるアナログ業務の増加という現状と、目標とする、システム化による人員の最適配置、デジタル活用による新サービスの創出といった未来の間にあるギャップをどうやって埋めていくか、メンバーで徹底的に議論しました。そのプロセスによって、メンバーのモチベーションも向上し、今後の開発もスムーズになったと感じています」
メンバーの1人で、プロダクトオーナーとして業務部門の意見を取り入れる役割を担った鵜野いずみ氏(営業部門でマーケティング業務に従事)は、プロジェクトを経て感じたことをこう話す。
「新しい仕事の仕方で業務効率を上げたい、他の会社で実施しているいい点を自社に採り入れたいと1人で思っていても実現は難しいですが、このプロジェクトを通じて、力を合わせればそれができると分かりました。これからもっと学び、実践したいと思いますし、自分がポジティブに変わればそれが周りに伝わり、それがまた自分にも戻ってくると期待しています」
小さな成功体験の共有がDX文化定着への一歩
黒川氏は、メンバーの小さな成功体験の積み上げが、DX文化の醸成に向けた成果だと話す。「メンバーが、『こういうことができた』『こういう成果が出せた』という、小さい規模でも結果を出せたことが重要です」。彼らは次世代のDX人材としての活躍が期待されている。
同社のDXプロジェクトは、2025年度もテーマを変えた「フェーズ2」として継続されている。菊池氏は、「プロジェクトの継続を通じて、メンバーがさまざまなことを感じ、学び、それを社内に還元できるような人材に育ってくれたら非常に嬉しいと期待しています」と語る。
課題に直面したとき、個人の頑張りで乗り越えようとせず、仕組みで解決しようと考える。そこにデジタルの力をツールとしてどう活かしていくかをチームで知恵を絞る。そういう組織に向けて、芝浦メカトロニクスは第一歩を踏み出した。
黒川氏は、「この結果をシステムの完成だけに終わらせず、実務に直結する活動として、日常業務の改善に活用していきたいと考えています。そして、DXを当たり前のように会社のツールとして使い込んでいく風土を育てていきたいと思います」と最後に語った。
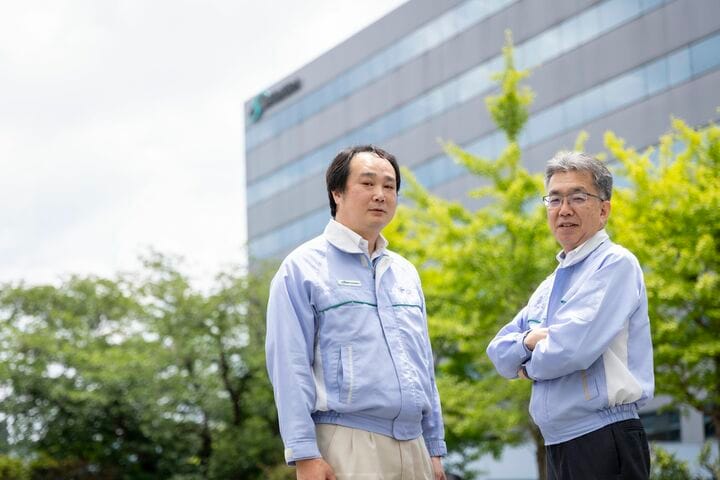
―― 伴走パートナーの立場から ――
DXプロジェクトは「答えのないものを探し求める旅」 成功の鍵を握ったのは・・・
 マクニカ イノベーション戦略事業本部デジタルインダストリー事業部 プロフェッショナルサービス第3部第2課 課長 望月崚馬氏
マクニカ イノベーション戦略事業本部デジタルインダストリー事業部 プロフェッショナルサービス第3部第2課 課長 望月崚馬氏
芝浦メカトロニクス様が、社内にDX文化を根付かせたいという思いからスタートしたプロジェクトにマクニカの参画が決まってから伴走パートナーとしてご支援してきました。 プロジェクトを成功に導くため、当社が長年のプロジェクト支援で培ったノウハウを全面的に提供しています。
今回のプロジェクトは、技術的には当社が販売するローコード開発プラットフォームである「Mendix」を使った業務改善です。 しかし、ただツールを販売して使い方を教えれば終わりということではありません。お客様自身がビジネス課題をツールでどう解決するかを決め、開発し、運用に定着させるまでのプロセスを段階的に進めていく必要があります。
DX文化醸成に際して、当社が最も重視したのは、プロジェクトに参加する各メンバーの動機付けです。DXプロジェクト は「答えのないものを探し求める旅 」のようなものです。マクニカのメンバーはお客様が途中で方向を見失い離脱することがないように、お客様の成功に向けて伴走支援に当たりました。
具体的には、個人の目標とプロジェクトの目標を一致させることを重視しました。所属部門の業務との兼務でプロジェクトに参加しているメンバーの一人一人が、なぜこのプロジェクトに関わっているのかを自ら理解すること。さらに、所属部門のマネジャーにもその意義を理解していただくことで 、メンバーのモチベーションが高まります。窓口となった、芝浦メカトロニクス様側 のプロジェクトマネジャーである菊池勉さんとは密なコミュニケーションを通じて、メンバーのモチベーションが維持できているかを、きめ細かくヒアリングをさせていただきました。
今回のプロジェクト開始にあたり、菊池さんが所属部門のマネジャーに対して、「同社の10年先を担う人材をプロジェクトに出してほしい」と依頼したと聞いています。現場にとってはエースを送り出すのは大きな痛手でしたが、マネジャーは快諾し、その結果、非常に優秀なメンバーが集結しました。このことから菊池さんのリーダーシップ、社内の人望の厚さを感じました。
DX文化醸成のゴールの一つは、お客様自身がローコード技術を活用して業務改善を自律的に推進できる体制を構築することです。今回のプロジェクトの「フェーズ1」が終了した段階で、業務改善に対する関与の割合は当社が7、芝浦メカトロニクス様が3程度でした。「フェーズ2」では内製化の割合をさらに高め、実際に二つ程度のアプリケーションをお客様自身が開発できることを目指しています。当社の役割は、メンバーの動機付けから、より複雑な開発のサポートに段階的に移行していくことを想定しています。
今後も当社は、お客様のDXの進展に合わせたきめ細やかな支援を通じて、DX文化の定着と発展をお手伝いしていきたいと考えています。
<PR>

