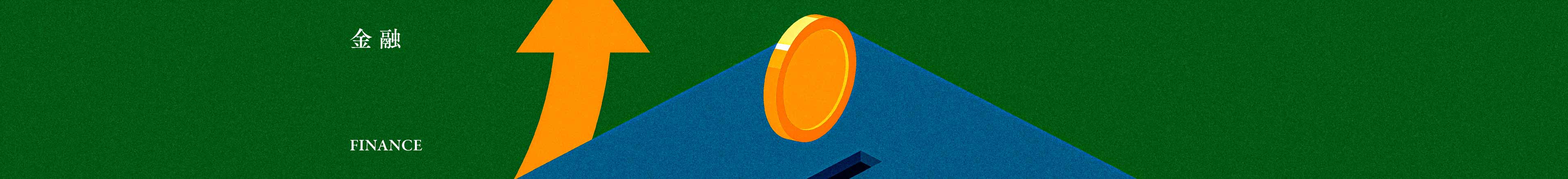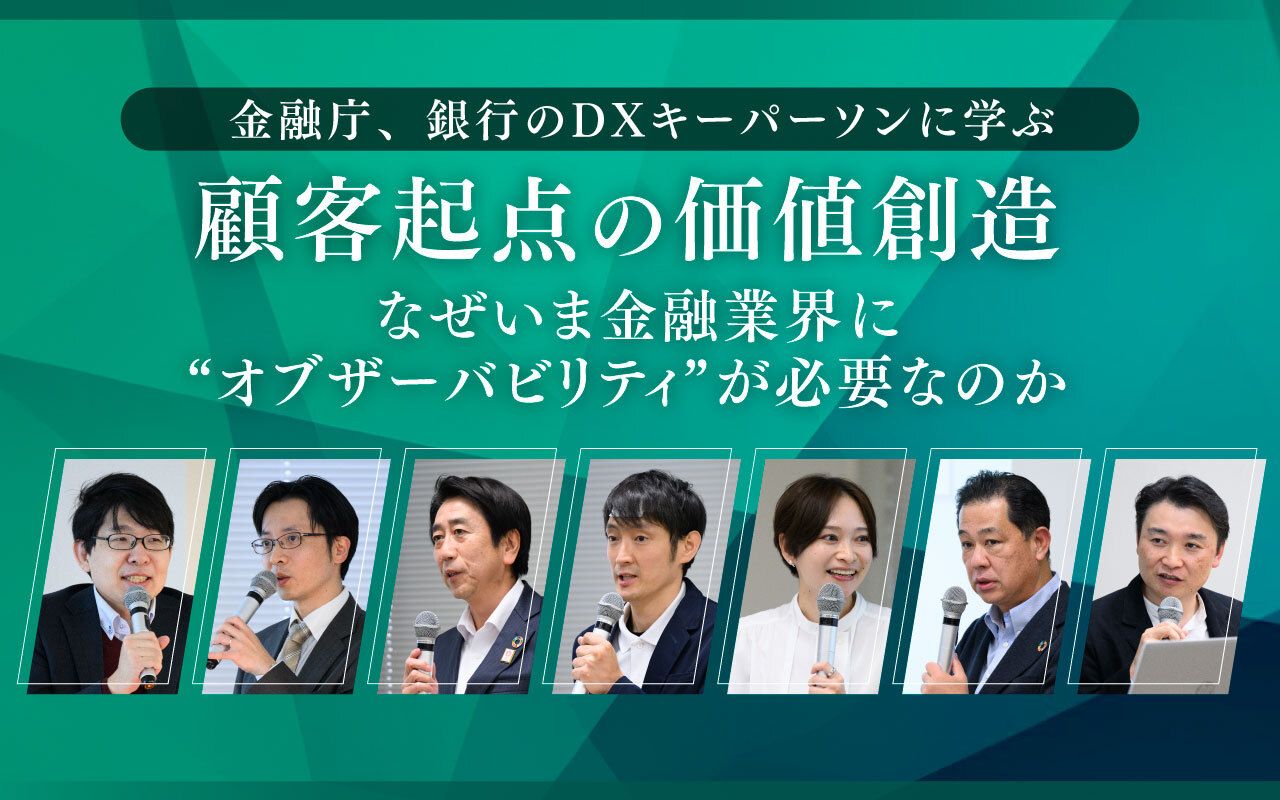
生成AI、ブロックチェーン、クラウドといったデジタル技術の活用が急速に進む金融業界は、かつてないパラダイムシフトを迎えている。この変化を好機ととらえ、顧客起点で新たに価値を創出するためには、レガシーシステムからの脱却やサイバー攻撃への対策、システムの安定稼働といった喫緊の課題を解決するとともに、組織の機動力を向上させ、新しいビジネスモデルの構築やDXの推進によるイノベーションが必要不可欠だ。有識者による深い洞察や業界の先進事例を通じて、イノベーションの実現に必要な考え方や金融DXを支える最先端のテクノロジーについて学ぶ「金融イノベーションカンファレンス in Tokyo」が、2024年12月12日に都内で開かれた。平日の昼間にもかかわらず、金融業界の未来を担う意欲的な参加者が大勢集まった。以下に当日の内容をレポートする。
基調講演:イノベーションの推進に向けた「AI」をはじめとする金融庁の取組み
 金融庁 総合政策局イノベーション推進室 室長 チーフフィンテックオフィサー 牛田 遼介氏
金融庁 総合政策局イノベーション推進室 室長 チーフフィンテックオフィサー 牛田 遼介氏
金融庁 総合政策局イノベーション推進室 室長 チーフフィンテックオフィサーの牛田遼介氏はまず、デジタル技術と金融サービスの歴史を振り返り、金融セクターでの影響力を増すフィンテックでは、QRコードなどの「送金・決済」から、ステーブルコイン、セキュリティトークンなどの「Web3.0」へ進化し、さらに活用の可能性が広がっていると指摘した。
金融サービスと非金融サービスが一体化し、金融機関が前面に出ない金融サービスも数多く生まれているという。「既存の金融機関と新たなプレイヤーの橋渡しをするのもイノベーション推進室の役割です」と牛田氏は話した。
AIのユースケースが金融セクターでも広がっている。かつては不正検知や市場予測などでAIが活用されていたが、生成AIの登場により業務の効率化・高度化などにも使われるようになっている。
一方でAIにはブラックボックスやハルシネーション(虚偽の出力)などの問題もある。「それゆえに金融庁はAIを使うことを否定していると言う人がいますが、誤解です」と牛田氏は話す。逆に、適切なリスクのコントロールを行いつつ、ユースケースが増えることが重要だと考え、さまざまな支援を行っていくという。
2024年4月には政府の「AI事業者ガイドライン」も発表された。金融庁でも、環境整備、事業者支援、調査・研究、ステークホルダーの対話などを通じ、イノベーションの実現を支援する考えだ。「FinTechサポートデスク」の設置や、「Japan Fintech Week」の開催なども積極的に行っている。「Fintechやイノベーションに前向きに取り組んでいるので、ぜひ気軽にご相談いただきたい」と牛田氏は結んだ。
特別講演Ⅰ:〈みずほ〉におけるAI利活用の取り組みと今後の展望
 みずほフィナンシャルグループ デジタル企画部 AIX推進室 室長 石井 宏明氏
みずほフィナンシャルグループ デジタル企画部 AIX推進室 室長 石井 宏明氏
みずほフィナンシャルグループ デジタル企画部 AIX推進室 室長の石井宏明氏は「中期経営計画で成長を支える経営基盤の強化として『DX推進力の強化』を掲げていますが、部門ごとの部分最適ではなく、グループも含め一体的な推進を目指しています」と紹介する。
AIの活用についても、全社活用推進を担う「AIX推進室」を設置し、「攻め」と「守り」の両面から取り組みを進めている。「攻め」では「業務適用推進」「イノベーション創出」「経営陣向け啓発活動」、「守り」では、「責任あるAI推進」などがテーマだ。
みずほフィナンシャルグループでは、独自の生成AIツールも導入している。2023年6月に導入した、みずほ版Chat GPT “Wiz Chat”は、生成AIアシスタントの汎用ツールだ。業務に必要な文案の作成など、さまざまなテンプレートが用意されているという。「まずは事例を量産することで、社内の認知度を高めていきたい」と石井氏は語る。
照会系AI “Wiz Search”は、膨大な社内手続きを検索し、関連情報を取得し回答することができる。個別特価AI “Wiz Create ”は、プレゼン資料を読み込んで説明スクリプト・指摘事項・想定QAなどを作成する。顧客との面談の内容を文字起こししたり、議事録として要約したりすることも可能だ。
コンタクトセンターも生成AIを活用し進化させている。顧客との会話を分析しニーズを正確に捉えチャットボットなどで迅速に回答する。ベテラン行員の暗黙知をデータ化することも目指しているという。
「個別ツールと汎用ツールの使い分けの整理も必要です。AIエージェントなど、技術トレンドもキャッチアップしながら、いち早く活用できるようにしていきたい」と石井氏は抱負を語る。
セッション:金融業界に重要な“オブザーバビリティ”で意思決定と問題解決の加速を実現
 New Relic 技術統括 コンサルティング部 担当部長 会澤 康二氏
New Relic 技術統括 コンサルティング部 担当部長 会澤 康二氏
金融業界でDXの取り組みが加速している。一方で、それに伴いシステムの複雑さとデータ量が増加し、システムの安定稼働と障害対応のスピードや正確さが求められるようになっている。
最近になって注目されているのが「オブザーバビリティ(可観測性)」を活用して金融ITシステムの性能と可用性を高める方法だ。そこで、オブザーバビリティプラットフォームの展開を拡大しているNew Relic 技術統括 コンサルティング部 担当部長の会澤康二氏に、金融業界における具体的な活用事例や、ビジネス価値を生み出すポイントを解説してもらった。
New Relicは米西海岸で2008年に誕生し、日本法人は2018年に設立された企業である。インフラ、アプリ、ユーザー環境領域を1つのプラットフォームで可視化できる「オブザーバビリティプラットフォーム」(SaaS提供型)では世界トップシェアを誇り、全世界1万6000社以上の顧客に採用されている。日本でもすでに金融機関や大手企業、大手SIerを中心に数百社を超える顧客が同社のプラットフォームを活用している。
DX化の波とシステム運用の3つの変化
「オブザーバビリティプラットフォーム」の導入が、近年進んでいる理由について、会澤氏は「DX化の波とシステム運用の3つの変化があります」と指摘した。
3つの変化とは、「役割の変化」「システム構成の変化」「開発体制の変化」だという。「役割の変化」とは、従来の情報保管、業務効率化のシステムだけでなく、スマホアプリやEC、フィンテックなど、ビジネスそのものを担うシステムが増加していることだ。
「システムの変化」とはスピーディーに開発するためにクラウドやコンテナ・サーバーレスになっていること。「体制の変化」とは、ユーザーのニーズに迅速に応えるため、ウォーターフォールからアジャイルな開発体制にしたり、外部発注から内製化に転じたり、SRE(Site Reliability Engineering)や、サービスレベルマネジメントといった管理手法を採用することだ。
3つの変化により、どのような対応が求められるのか。会澤氏は「まず、安定と変革を両立する『両利きの経営』が最重要IT戦略になります」と話す。
だが、構成が変化している昨今ではそれも容易ではない。メインフレーム、オープンシステム、サーバー仮想化、クラウド、コンテナ・サーバーレスが常に変化しているようなシステムでは、ユーザーがストレスなく使えているかどうか監視する必要があるからだ。「ITシステムと技術の進化に伴い、監視環境も変化しています」と会澤氏は指摘する。
さらにシステムが基幹系システムのようなSoR(System of Record)から、アプリなどのSoE(System of Engagement)に変化することで、アジャイル開発を行うための内製化なども必要になる。
システム運用の課題とオブザーバビリティの必要性
「デジタルビジネスの加速を後押しするテクノロジーが進化することにより、開発・構築は速くなりました。その反面、システム構成は複雑化し、問題発生時の原因調査が高度化・長期化するようになりました」と会澤氏は話す。
これまでなら、サーバーが動いていれば、アプリケーションも動いているだろうと判断することもできたが、今ではユーザーから障害について問い合わせを受けても、どこが原因か分からないので責任の押し付け合いになりがちだ。調査は非効率で、インシデント対応は増加する。顧客満足度も低下してしまうだろう。
「そうならないために、システム全体の観測性を全員が持つことが必要不可欠です。そのカギになるのがオブザーバビリティという考え方です」
オブザーバビリティは、データをリアルタイムに取得し続け、それらを関連付け、常にシステム全容の把握と問題の予防・改善ができる状態である。システムの各コンポーネントの振る舞いや出力をチェックし続ける「監視」とは大きく異なる。
「繰り返しになりますが、New Relicは、インフラ、アプリ、ユーザー環境領域を1つのプラットフォームで可視化できるオブザーバビリティプラットフォームです。さまざまなデータを取り込み、システム全体を観測することができます」と、会澤氏は説明する。障害が発生した場合でも、その原因特定と解決が迅速にできるので、意思決定の遅れを短縮することができるだろう。
オブザーバビリティに取り組む金融機関の成功事例も生まれている。東京海上日動システムでは、基幹システムのクラウド移行に合わせ、New Relicを導入。ダッシュボードを基盤担当者とアプリ担当者で共有し、両者が同じ情報を見ながらシステム障害の調査・対応ができる仕組みを構築した。
SBI新生銀行ではNew Relicの導入によりコンテナの監視とダッシュボードによる状態の可視化を実現し、インタネットバンキングサービスの中核基盤である「API-Hub」に対する問題確認の作業が数秒でできるようになった。
ふくおかフィナンシャルグループでは、グループ全体で「標準オブザーバビリティ環境」を整備、クラウド利活用を高度化し、みんなの銀行では、前監視システムの利用料の上昇、内製メンバーの監視システムに関する経験・知識量のギャップ、サポートの体制不足などの課題をNew Relicを導入することで解決した。
会澤氏は「オブザーバビリティを実現し、ぜひ金融DXの推進を加速していただきたい」とセッションを結んだ。
特別講演Ⅱ:りそなグループCIOが語る、新たな価値創造に向けたアジャイル開発体制
 りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループCIO兼グループCPRO 野口 幹夫氏
りそなホールディングス 取締役兼執行役兼グループCIO兼グループCPRO 野口 幹夫氏
りそなグループは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の4行からなる金融サービスグループだ。多様なニーズに応え、「りそなグループアプリ」は利用者から利便性が高いと評価が高く、ダウンロード数は847万(グループ4行における総数)にも達している。
りそなホールディングス取締役兼執行役兼グループCIO兼グループCPROの野口幹夫氏は「当社グループのシステムの大きな特徴は『ワンプラットフォームマルチバンク』です」と紹介する。ハードウエア、ソフトウエア、店頭でのタブレット、さらに顧客向けアプリまでを共通化している。アプリケーションの監視ツールなども共通だ。
評価の高いグループアプリの開発体制は「オープン・イノベーション共創拠点『Resona Garage』を設置し、プロダクトオーナー、当社、エンジニアが三位一体となった開発を高速で行っています。また、アプリをリリースして6年になりますが、お客さまからの評価が下がらないよう、アジャイルでスピーディーなシステム開発を行っています」と、野口氏は語る。これまでのアップデート回数は180回、改善項目数は1200にも及ぶという。
「私たちが目指すのは、『顧客体験を変える』『お客さまに新たな価値を提供する』『我々のコスト構造そのものを変える』こと」と野口氏は話す。
実際に、アプリが顧客との接点を増やしたことで、業績の向上にも貢献し、新たな事業の柱も生まれているという。
「当社の金融デジタルプラットフォームを他の金融機関に提供するビジネスがスタートしています。そのための専門会社も立ち上げました」(野口氏)というから驚く。まさに、価値創造につながるDXが進みつつある。
特別対談:縦割り組織に横串を指し、知恵と人情の総合力でDXに挑む静岡銀行と常陽銀行
 ノンフィクションライター 酒井 真弓氏
ノンフィクションライター 酒井 真弓氏
特別対談として、いずれも経済産業省の「DX認定事業者」である静岡銀行経営企画部DX戦略推進グループ 担当部長 榎本裕己氏と、常陽銀行 経営企画部 副部長 兼DX戦略室長 丸岡政貴氏の2人の変革リーダーをお迎えした。ノンフィクションライター酒井真弓氏の進行のもと、地域に根差した金融機関がどのようにDXを進め、新たな価値を創出しているのかについてディスカッションが行われた。
 しずおかフィナンシャルグループ 経営企画部DX戦略推進室 室長/静岡銀行 経営企画部DX戦略推進グループ 担当部長 榎本 裕己氏
しずおかフィナンシャルグループ 経営企画部DX戦略推進室 室長/静岡銀行 経営企画部DX戦略推進グループ 担当部長 榎本 裕己氏
しずおかフィナンシャルグループは、静岡銀行(本店・静岡県静岡市)を中核とする銀行持ち株会社である。めぶきフィナンシャルグループは常陽銀行(本店・茨城県水戸市)と足利銀行(本店・栃木県宇都宮市)などを子会社とする金融グループだ。
銀行でDXを推進することについて、榎本氏は「楽ではない。周囲を巻き込むことが大切、みんなに当事者意識を持たせることが仕事だと考えている。DXのDよりも何を実現したいのかというXが大切」と語った。
丸岡氏も「DX部門に人を集めるだけでなく、全役職員の当事者意識が必要」と語った。その上でデジタルは特別なものではなく、表計算ソフトのように当たり前という文化にすべきだと指摘した。常陽銀行では300人ものDX人材を育成している。「資格取得だけでなく、実務と知識の両面から人材を育成している」と丸岡氏は紹介した。
 めぶきフィナンシャルグループ 経営企画部 DX統括グループ 担当部長/常陽銀行 経営企画部 副部長 兼DX戦略室長 丸岡 政貴氏
めぶきフィナンシャルグループ 経営企画部 DX統括グループ 担当部長/常陽銀行 経営企画部 副部長 兼DX戦略室長 丸岡 政貴氏
金融機関に限らず、DX推進にあたり、縦割り組織によるサイロ化が起こりがちだ。榎本氏は「それを横串にするために知恵と人情の総合力で取り組んでいる」と話した。経営陣の支持を得て、若手人材を巻き込むことが重要なようだ。
丸岡氏は「当行は風通しはいいと思うが、コミュニケーションは大切にしている」と語った。
新たな挑戦を始めたもののPoC(概念実証)で終わってしまうこともよくある。最後までやり切るためには「KPIをしっかりと決めてからスタートすることが大切」と丸岡氏はアドバイスした。
静岡銀行、常陽銀行ともに生成AIの活用も始めているという。行員の利用率を高めるために、榎本氏は「アクセスのしやすさと業務に組み込むことが大切」と語る。静岡銀行ではスマホからも利用できる環境を整備している。また、生成AIを活用したプロンプト、活用アイデアコンテストを実施し、優秀なアイデアを今後テンプレート化して共有していくという。
常陽銀行では行員約3,000人のうち1日平均1,500回のチャット利用を目指している。「便利になったことをAI利用喚起のきっかけとして活用するため、小出しで機能アップを行っている」(丸岡氏)と工夫を紹介した。
対談の最後にあたって榎本氏は「デジタルはゴールではなく手段。小さく失敗を繰り返すことで成果を出すことが重要」と話した。丸岡氏も「ビジネスとしての成果にこだわりたい。一過性のものでなく組織に浸透させたい」と抱負を語った。