 (写真左)キリンホールディングス デジタルICT 戦略部 DX 戦略推進室 室長 皆巳 祐一氏
(写真左)キリンホールディングス デジタルICT 戦略部 DX 戦略推進室 室長 皆巳 祐一氏(写真右)日本電気 ピープル&カルチャー部門 兼 コンサルティングサービス事業部門 ビジネスアプリケーションサービス統括部 カルチャー変革エバンジェリスト 森田 健氏
※どちらも肩書は2024年取材時点
多くの企業がビジネスモデルや組織構造の変革を模索している。変革の過程で必然的に求められるのが、社員のマインドセットの転換や新たな組織カルチャーの醸成だ。2000人以上のDX人材を育成してきたキリンホールディングスと、全社を挙げたカルチャー変革を断行して従来型のSIerから社会価値創造企業への転換を進めるNEC。両社はどう変革を実現してきたのか。キーパーソンが組織人材変革をテーマに語り合った。
デジタルの前に「どう変わりたいのか」
森田 健氏(以下敬称略)キリンでは、DXに注力するようになった背景にどんな経営課題があったのでしょうか。
皆巳 祐一氏(以下敬称略)キリンと言えばビールや飲料のイメージが強いと思いますが、近年は飲料だけでなくヘルスサイエンスや医療の領域でも事業展開しており、これらの事業が売り上げに占める割合も大きくなっています。
グループにおける事業ポートフォリオの変化や取り組みの多様化に伴い、その中で効率的に事業を立ち上げたり、バリューチェーンを最適化したりするにはデジタル技術の活用が重要になるとの観点から、2020年にDXを加速させる組織としてDX戦略推進室を発足しました。
森田 キリンのDXでは、DX人材の定義として「ビジネスアーキテクト人材」を重視していますね。この意図は何ですか。
皆巳 デジタルはあくまで手段に過ぎず、それ自体が何かをしてくれるわけではありません。まずは社員一人ひとりが「何を目指しているのか」「何をどう変えたいのか」というゴールを「自分ごと」として設定し、そのゴールに手段としてのデジタル技術をアジャストさせていく、という考え方を大事にしています。
課題発見力や企画構想力などのビジネススキルを底上げし、事業起点でデジタル活用を企画構想できる人材を増やせれば、経営人材の育成にもつながるとの考えから、このビジネスアーキテクト人材を定義しました。
森田 DX人材の育成においてどのくらいの成果が出ているのですか。
皆巳 現時点(2024年10月末)で2000人を超える社員が、従業員向けのDX人材育成プログラム「DX道場」を受講し、認定資格を取得しています。
森田 2000人というのは大きな成果ですね。どうやって社内に学びの気運を醸成したのですか。
皆巳 いきなり“デジタル”の看板を掲げてしまうと、中にはアレルギー反応を起こしてしまう社員もいるかもしれません。でも「何を変えたいか」というビジネスのアイデアは、みんな何かしら持っている。入口として、そのアイデアを引き出すトレーニングから始めるなど、とっつきやすさを意識しました。

キャッチーなネーミングもポイントです。DX道場では、一般に初級、中級、上級などと分類されるプログラムのレベルを、白帯、黒帯、師範と呼んでいます。社内で「いま、黒帯だよ」「まだ白帯なの?」といった雑談を耳にする機会が増えるだけでも、「私も受けてみようかな」という意識変容が生まれやすくなるはずです。カリキュラムの中身ももちろん大事ですが、そういった社員の心をくすぐるような仕掛けに腐心しました。
トップが本気度を示し変化を目に見える形にする
森田 NECのカルチャー変革の取り組みも、事業構造の大きな転換がきっかけでした。かつてのNECは携帯電話やPCを代表としたモノづくりの会社でしたが、今ではテクノロジーをベースとしたソフトウエア・サービスの会社へと生まれ変わっています。
とはいえ、社員からすれば「NECは社会価値創造企業になる」「お客さまに提供するのはサービスであり価値だ」と言われても、急に変わるのは容易ではありません。業態だけでなく、組織のカルチャーも含めてモノからコトへの転換を図る必要がありました。
特に大きな転換点は、“受託開発カルチャー”です。これまではお客さまが提示した仕様に沿って開発し、提供するビジネスモデルでした。これからは自ら課題を発見し、提案しなければいけない。いわばベクトルを180度逆にするくらいの転換が求められていました。
皆巳 どのようにカルチャー変革を進めていったのですか。
森田 さまざまな取り組みがありますが、一例を挙げると、新たに「Code of Values」という行動基準を策定しました。ただ、作っただけだとなかなか成果につながりません。そこで、人事部門と連携して人事評価制度の中に組み込みました。
皆巳 ある意味、強制力のあるアプローチですね。
森田 変革は社員の行動変容の積み重ねで実現されると考えています。行動変容は掛け声だけでは難しい。最初の切っ掛けづくりとして、強制力はある程度必要だと思っています。変革が軌道に乗った背景には、トップの本気度があったと思います。
トップダウンでの取り組みを始めるに当たり、当時の社長が「これは経営の責任だ」と認め、自社の現状を数字も含めてオープンにした上で「これからは経営も変わっていく。だからみんなも変わっていこう」と宣言したんです。そして、トップが社員の声と徹底的に向き合い、辛辣な意見にも耳を傾けていきました。
この過程で大事にしたのは、小さなことでも形にすること。例えば、本社ビルのオフィス環境も、この5年間大きく模様替えしました。
皆巳 トップが本気度を示し、変化を目に見えるようにした。社員にとっては会社が変わっているという実感が持てますね。
トップダウンとボトムアップ 2つを状況により使い分ける
皆巳 NECの場合は、トップが旗じるしを明確にして、カルチャー変革の施策を制度にしっかりと組み込んでいますね。変革を進める多くの企業が見習うべきポイントだと思います。
森田 キリンのDXはNECとは逆で、皆巳さんをはじめとするDX戦略推進室が旗振り役としてボトムアップで現場の意識醸成をうまく進めています。お互い、アプローチが対照的なのは興味深いです。
トップダウンとボトムアップは二者択一ではなく、その時々の状況により使い分けるのが大事なのだと思います。NECも、伝統的にはボトムが強く、現場の力が会社を支えてきたところがあります。ただ、現場主導だけでは遠心力が強くなり過ぎるので、時にはトップが求心力を働かせる。このバランスがうまく保たれると経営は長続きしますよね。
皆巳 確かに、当社もDX戦略推進室を立ち上げたときはトップダウンでしたが、今は現場がリードしていくものだと思います。トップは現場の進捗やタイミングを見ながら、投資や環境整備などの意思決定を打つカンフル剤の役割を果たしています。
森田 ところでDXにおいては、現段階ではボトムアップ主導が強いと思うのですが、そこに対するトップの関心やサポートという点ではいかがですか。
皆巳 基本的には現場に任せるスタンスですが、むしろこちら側から、経営層に対して、生成AIなど最新のテクノロジーに触って体感してもらうようにしています。少し前にも全役員のところを回って意見交換をしました。そういった場では、意外と新しいビジネスや効率化のアイデアが出たりするものです。そうした経験を通して、経営層もDXを、より応援してくれるようになっています。
森田 経営層にも関心を持って見守ってもらうのは、組織変革における大事なポイントの1つですね。
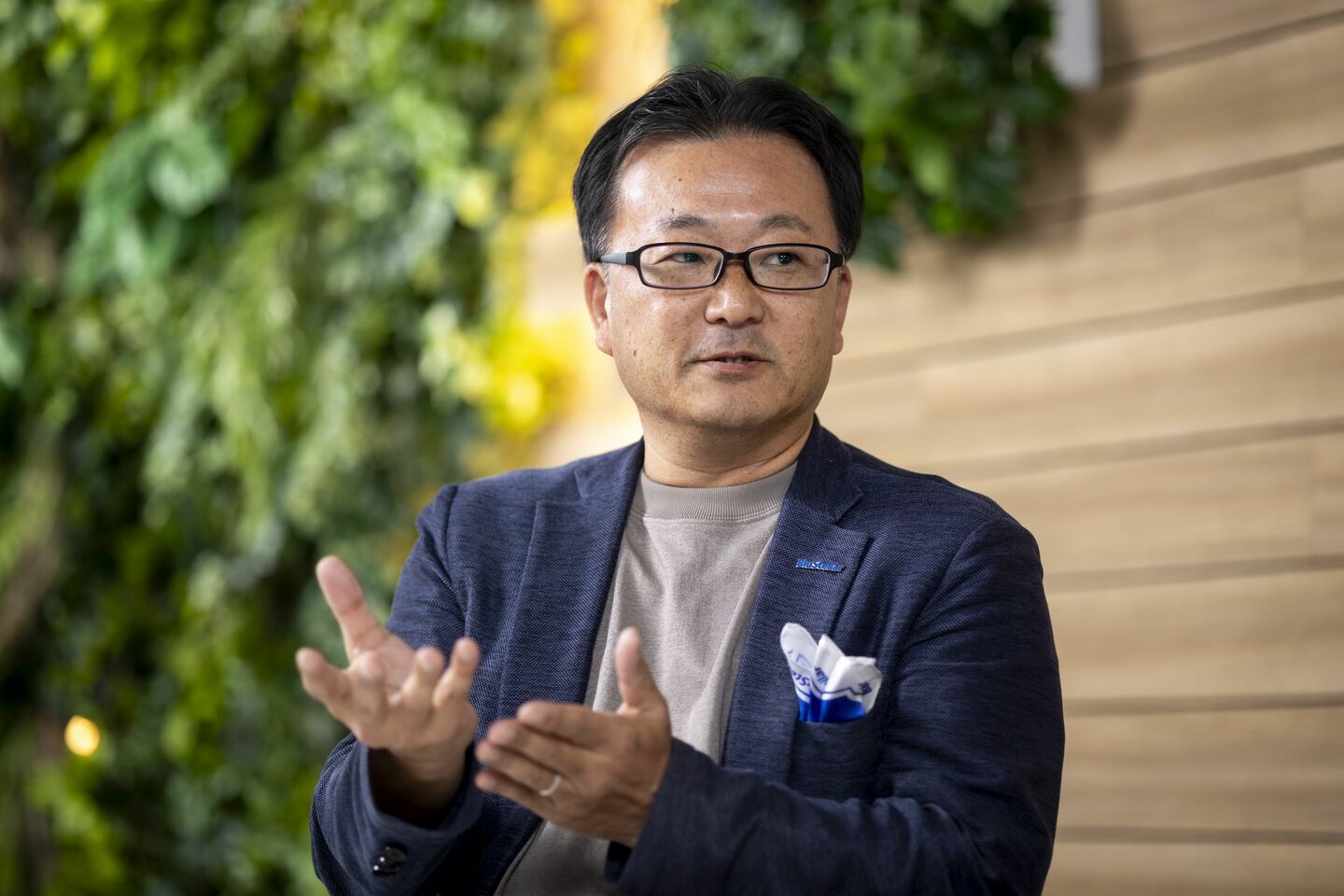
当社でも先日、似たような取り組みを行いました。リバースメンタリングセッションといって、役員と新入社員が2人ずつ4人のチームを作り、あるテーマに沿って解決策のアイデアを出し合うセッションです。
最終的にはアイデアを形にするのがゴールなのですが、いざやってみると新入社員がノーコードツールをどんどん使いこなし、あっという間にアプリができている。その様子を目の当たりにして、どの役員もあぜんとしていましたね(笑)。デジタルの有用性や若い社員のポテンシャルなど、多くの気づきを得てもらう機会になったと思います。
皆巳 その気づきから、若手社員を新たなプロジェクトに登用するような動きが生まれると、変革のスピードがさらに増していきそうですね。
従来型SIerの枠を超え「つながり」をつくる存在に
森田 キリンのDXは順調に進んでいる印象ですが、今後の課題はありますか。
皆巳 DX人材を育成した後の、各事業部門での実践をどう支援するかが目下の課題です。
現在、私たちDX戦略推進室が各部門でキーパーソンとなり得る社員を訪ねて、デジタル変革について直接意見を聴く取り組みを進めています。会話の中でデジタルへの感度が高いと感じたら、デジタルツールを実装させて、小さなプロジェクトを回してもらいます。
各部門のキーパーソンがツールを使いこなしているのを周りが見て、そこから自然に波紋が広がっていくことを期待しています。
森田 今のお話からも、キリンでは社員の「自分ごと化」をうまく促しながら、現場ドリブンでDXを進めていることがうかがえますね。現場での実践を支援する上で心掛けていることはありますか。
皆巳 これまでの情報部門の反省として、事業部門が相談に来た時に「何がやりたいんですか」と逆質問してしまうことがありました。患者が「頭が痛い」と言っているのに、医者が「どんな薬が欲しいですか」と返すようなものですよね。
そうではなく、まずはデジタルの素地がなくてもいいので、何に困っているのかを社員が安心して吐き出せる環境づくりを心掛けています。その上で「その悩みにはこの薬が効きますよ」と処方箋を出してあげれば、「次からはこの薬を使えばいいんだ」と事業部門は自走できるようになります。
森田 まさに、今日のコンサルに求められるスタンスそのものですね。
NECでは、これまで実践してきたビジネス変革・社会変革の知見・経験を体系化した「BluStellar(ブルーステラ)」でお客さまの価値創造を支援しています。私たちが提供したいサービスは、提案書を納品して終わり、ではなく、お客さまの悩みに寄り添い、社内で自走できるまでお付き合いすること。課題の発見からビジネスモデルの構築、仕組み化までハンズオンで支援することを目指しています。
皆巳 最近は多くの企業が、通り一遍のコンサルティングにはあまり価値を感じないようになっているのではないかと思います。それならむしろ「一緒に課題を解決しませんか」と言われる方が興味深い。NECに対しても、パートナーシップや共創に期待したいです。
森田 ありがとうございます。その点で、IT企業にはあらゆる業種を横断的に見られる強みがあります。その強みを生かして、共通する経営課題を持つ企業同士をつないでいくのは、これからのIT企業に求められる役割だと考えています。
従来型SIerの枠を超え、お客さまの成長を共にドライブするという想いで「Value Driver」を掲げるNECとしては、お客さまに寄り添い、「つながり」をつくりながら組織変革をリードできる存在になっていきたいですね。
<PR>

