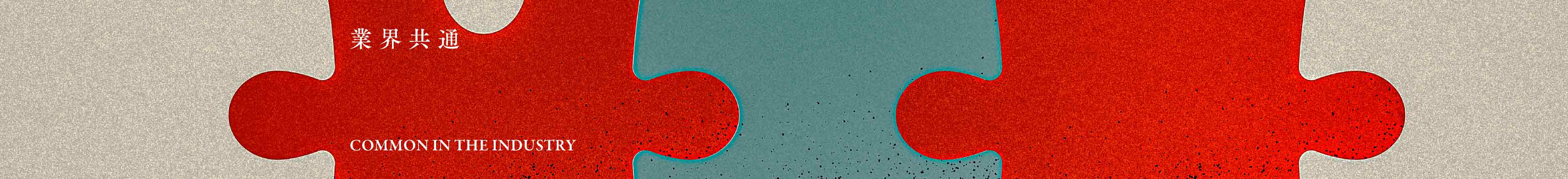関西大学 社会学部 教授 松下慶太氏
関西大学 社会学部 教授 松下慶太氏
テレワークやワーケーションなど、新たな働き方が急速に普及するなか、「働く環境」が企業価値を左右する時代に突入している。いまや事業の持続性を高めるためには、従業員の働きがいと向き合うことが欠かせないのだ。では、企業はどのように従業員の働き方をデザインすべきなのだろうか。関西大学 社会学部 教授で、書籍『ワークスタイル・アフターコロナ 「働きたいように働ける」社会へ』(イースト・プレス)の著者でもある、松下慶太氏に話を聞いた。
オフィスに求められる「機能性」以上の価値
――コロナ禍で在宅でのテレワークが急速に普及したなかで、オフィスの役割が変化しているといわれています。この変化をどのように捉えていますか。
松下 慶太 氏(以下、松下氏) 今後、オフィスには「機能性以上の付加価値」が求められると考えています。これまで企業がテレワークを導入したとしても、「本来は自宅ではなく、オフィスで仕事すべき」という前提のもとで運用されてきました。
しかし、今後は「オンラインで行える仕事もある」ことを前提としたうえで、オフィスや自宅、コワーキングスペースなど、さまざまな働く場所を組み合わせて運用することが求められます。こうした取り組みの先に、よりよい働き方の実現が位置づけられているのです。
そう考えると、オフィスの役割は「お寺や神社」のようなものに変化すると考えられます。お寺や神社は、多くの人にとって毎日通う場所ではありません。ですが、お正月やお盆、お祭りといった時節に合わせて人々が集まり、そこで象徴的な意味や精神性を感じたり、コミュニティ活動の拠点になったりしています。
 taka1022 /shutterstock
taka1022 /shutterstock
オンラインでの仕事が当たり前になると、従業員はオフィスへの出社に対して、「オンラインでのやりとり以上の付加価値」を求めるようになるのです。具体的には、社員同士のコミュニケーションや信頼関係の構築、チームワークの向上、組織への結束や愛着など、対面の価値をより活用した体験が挙げられます。逆に台風など自然災害のときに苦労して出社してオンラインでもできることをやっているとどうでしょう。オンラインでできることを対面でやっていると社員の士気低下や不満にもつながりかねません。
オフィスは、従来の機能である「作業ができる」ということよりも、そこでの交流や充足感が重視されるようになるのです。こうしたオフィスの付加価値をつくり、言語化することこそが企業に求められていることだと思います。
――松下先生は著書のなかで、オフィスの今後のあり方について『「焚き火」的オフィス』という表現を用いて説明されています。この点について、詳しく教えてください。
松下氏 従来のオフィスが「井戸的」であることに対して、これからのオフィスは「焚き火的」であると表現しています。井戸は水を汲むために行く場所で、その要件を満たすために出向きます。つまり「水を汲む」という機能性が求められているのです。従来のオフィスにも、こうした機能性が求められていました。
一方、「焚き火的」といえるのがこれからのオフィスです。焚き火は、何かを焼く、温めるといった機能よりも、それを囲んで話すといった行為自体が大きな目的となっています。これからのオフィスには、書類をつくったり、会議をしたりなど仕事をする機能性だけではなく、そこで社員同士が触れ合い、コミュニケーションを図り、関係性を深めるといった体験こそが重要になります。
例えば、携帯電話が登場する以前、「電話は、要件があって始めて使うもの」でした。しかし、携帯電話の普及に伴い、電話で他愛もないやりとりが生まれる機会も増えました。つまり、電話は「(要件を伝えるための)手段」であり「(電話すること自体が)目的」にもなっているのです。一見するとあまり意味のないメッセージを送り合っているだけのように思われますが、これはお互いの関係性を可視化する重要な営みといえます。昨今のオフィスでも、かつて電話で起きたことと同じような変化が起きているのではないでしょうか。
もちろんこれまでの井戸的オフィスにもタバコ室や給湯室での会話のような「焚き火的要素」はありましたし、焚き火的オフィスにもセキュリティや特殊機材が必要な作業をするための「井戸的要素」もあります。つまりゼロイチではなくどちらがメインなのか、オフラインで担うべき優先順位の問題なのです。
人材確保に向けて「働き方の充実」は待ったなし
――テレワークやワーケーション、サテライトオフィスなど、働き方にまつわるさまざまな選択肢が出てきています。企業はそれらをどのように捉え、ポートフォリオ化し、運用すればよいのでしょうか。
松下氏 企業は事業継続性の観点から、今後はより一層「働き方の充実」を図る必要に迫られます。いまや働き方を充実させないと、人材を確保できない状況になってきているともいえるでしょう。
労働人口が減少している状況下で事業を継続するためには、より少ない人数で仕事をこなせるようにする必要があります。加えて、時間を小分けにして柔軟に組み合わせることで、さまざまな事情を抱える人も働けるように、働き方を整備し直す必要もあるでしょう。ここで求められているのが「仕事の効率化」と「細分化」です。
 LightField Studios/shutterstock
LightField Studios/shutterstock
ノートパソコンやタブレットといったモバイルデバイスの登場により、働く場所と時間を柔軟に拡張できるようになりました。「仕事の効率化」や「細分化」は、技術的に可能となったといえます。
こうした状況だからこそ、今後、オンラインでできる部分があるにもかかわらずオンラインの活用を前提としない働き方をしていては、人材の採用が難しくなります。だからこそ、どの企業も柔軟な働き方の導入が求められるはずです。
ただし「つながらない権利」が注目されているようにオンライン化による「効率化」の名の下での仕事時間の過度な拡張は避けなければなりません。またテレワークによって仕事時間が増えたり、体調不良になったりしているという事例も見られるので自分をうまくコントロールするスキルが必要になってきます。
「仕事の効率化」や「細分化」は、世界的にも広まっています。日本の企業が柔軟な働き方を取り入れなかったとすると、外資系の企業に人材が流れるリスクも増えていきます。こうしたグローバルの観点からも、働き方の充実はますます加速していくと予想されます。
一方で、世界経済をリードする企業の中にも、コロナ禍以前のような「出社が当たり前」という働き方に戻している企業も存在します。これは決して消極的な動きではなく、あえて従業員を出社させる選択肢を選んでいるのです。
つまり、オンラインとオフィス出社のうち「どちらが正解か」ではなく、自社が実践する働き方にあった人材の確保や、それに応じた事業の展開こそが、いま企業には求められています。
――柔軟な働き方を実現するためには、どうしたらよいのでしょうか。
松下氏 働き方を充実させるにあたり、障壁となるのが「組織風土」や「マインドセット」です。例えば、何らかの理由でテレワークを実践できない社員が、テレワークを実践できる社員に対して「彼ら、彼女らはずるい」という感情を抱くことがあるかもしれません。
逆に、テレワークを実践できる社員が、そうでない社員に対して「自分ばかりテレワークをしていて、心苦しい」と感じることもあるでしょう。
こうした社員間に生じる不平等感は、あらゆる働き方の社員を同じ条件で採用していることから生じます。こうした軋轢が生じないように、働き方に応じた人事評価の制度設計や、人材と働き方のマッチングを意識した人事配置が求められます。これまでは就業選択において「仕事の内容」が重視されてきましたが、今後は「働き方」も重視されることを忘れてはなりません。
誰もが「働きたいように働ける」社会の実現を目指して
――ワーケーションやサテライトオフィスなど、多様なワークスタイルを実践する企業で、注目されている事例はありますか。
松下氏 例えば、フリマアプリを運営する「メルカリ」社では、2021年9月から新たな勤務制度「YOUR CHOICE」を実施しています。「YOUR CHOICE」の導入により、社員が出社とリモートワークを自由に選べるほか、日本国内であればどこからでも勤務できるようになりました。これにより、社員の会社に対するエンゲージメントは、向上しているといいます。
その他、プロジェクト管理ツールなどを提供する「ヌーラボ」社では、2018年からリゾートワーク制度を導入しています。リゾートワーク制度では、社員とその家族が会社の指定する地域に滞在し、リモート環境から就業しながら、地域での活動も行う教育研修制度です。福利厚生というよりも「学びの場」を提供することによる、社員の成長促進が目的となっています。また、日常でのコミュニケーションに対する施策も充実しており、1on1のほか、他部署の社員や新入社員との交流の機会も設けています。
 Song_about_summer/shutterstock
Song_about_summer/shutterstock
――今後、日本企業が模索すべき働き方の視点について、教えてください。
松下氏 これまでのお話と重なる部分もありますが、今後はますます「柔軟な働き方」の実践が必要になります。それに伴い、事業の持続性・継続性を高めるためにも企業の変革が求められるでしょう。オフィスへの出社は、オンラインを前提とした出社という意識改革も必要となります。
昨今、学生たちからは「働きたくない」という声をよく聞きます。しかし、よくよく聞いていくと「働くこと」が嫌なのではなく、「通勤が嫌」「定時で働けない」といった理由があるようです。このように「働きたいように働けない」という現状が垣間見えます。
働き方の柔軟性をテクノロジーによって変えられるようになった今、それの障壁になるものは「組織の風土」や「マインドセット」にあります。しかし、これらは前向きに変えていかねばなりません。働き方の充実には、働き手自身だけではなく、企業からの後押しも重要なのです。
<PR>