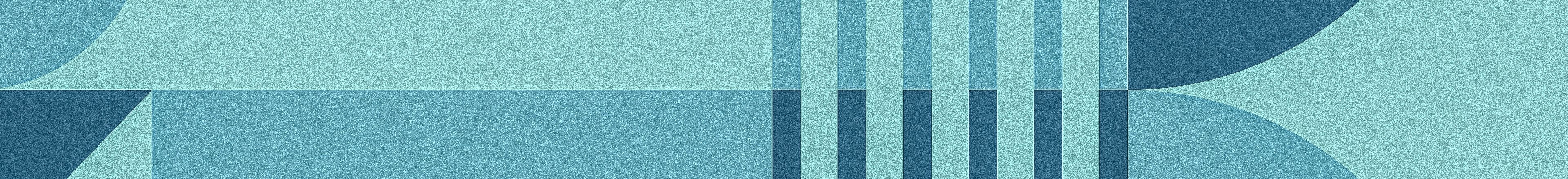株式会社精工 代表取締役社長 林 正規氏
株式会社精工 代表取締役社長 林 正規氏
デジタル化の波は今やどの産業にも訪れ、ここへの対応力が各社未来の事業の命運を握っているといっても過言ではない時代。特に印刷業界はこの変動が大きく減少する印刷ニーズをデジタル変革によってどのように新しいビジネスへと転換できるかが試されている。
またちょうど事業承継の時期とも重なり経営変革をも余技なくされる会社も多い。そんな中ぬぐいきれない不安を抱きながらも、事業承継を決断した若き社長たちがいる。
彼らは、目の前にある困難をいかに乗り越え、新しいフロンティアを切り拓こうとしているのか。これからの印刷業界の未来を担う社長たちの想いとは。第一回目は、株式会社精工 代表取締役社長 林正規氏に話を聞いた。
予想だにしなかった社長就任までの軌跡
——精工さんは明治44年(1911年)創業とのことですが、まずはその歴史から教えていただけますか。
林正規氏(以下、林氏) 私が4代目に当たるのですが、1代目は私の曽祖父。大阪証券取引所の株券や銀行の通帳など、活版印刷をしていた町の印刷工場でした。
そして、2代目のおじいさんのときに、第二次世界大戦が勃発した時代です。戦後、おじいさんが日本に帰還してみると、大阪大空襲で工場はすべて焼け落ちていた。そのような中でも、おじいさんは前向きな人だったので、近所の焼け残った印刷会社さんのお力を借りながら、戦後初の農業資材の問屋をスタートさせました。
それを3代目の父が継いだのですが、問屋業では、食の安心・安全といった自分たちがこだわりたいところに対して、何も決定権を持てないことを嘆き、1990年に再びメーカーとして始動することにしたんです。
——林社長は子どもの頃から会社を継ぐつもりはあったのですか。
林氏 いいえ、とんでもない。僕は、大阪芸術大学出身で、経営学などは専攻していませんでした。卒業後は、公共施設や都市公園のランドスケープデザインをやっている会社に入って、ゼネコンや役所に飛び込み営業をしていました。
しかし、公共事業費削減の流れで材料費が削られてしまうようになり、自分が思い描くものができなくなってきたので、3年で退職を決めました。
退職後、これからどうしようかと考えていた際に、父が「せっかくだから留学でもしてみたら」と声をかけてくれて、中国語を勉強するために台湾に1年間留学することにしました。兄と妹がいるのですが、二人も留学経験があったので、「子どもたちには、平等に教育を受けさせたい」と考えていた父が背中を押してくれました。今、機械の買い付けにひとりで行けるのは、そのとき勉強させてもらったおかげですね。
——ということは、留学に行かれる前には、お父様から将来の事業承継のお話はあったのでしょうか。
林氏 留学して1年が経ち、そろそろ帰ろうと思っていたら「就職先も決まってないのに、帰ってくるな」と言われてしまって。「帰ってくるなら、うちの工場へ行け。工場からやったら、入れてやる」と言われたんです。帰国した翌日には、仙台に行き、宮城工場で約1年間、グラビア印刷や製袋などの研修をしました。2000年のことです。
ちょうど研修が終わるころに、父がインディゴ社(当時、現HP Inc.)のロール対応デジタル印刷機「オムニアス」を購入したんです。これが僕のデジタル印刷との出会いでした。
うちのコアなビジネスは農産物の包装資材の印刷です。重量ベースでいくと25%くらいのシェアを持っている。本当はそれをデジタル印刷でやりたかったのですが、当時の機械は広幅が対応していなくて、軌道に乗るまでは相当長い年月がかかりましたね。
——工場から本社に戻られてからは、どのようなお仕事をされていましたか。
林氏 宮城工場で1年間の研修を経て、その後は約10年間、東京を拠点に全国のお客様を対象に営業をしていました。一般社員として、デジタル印刷の飛び込み営業を必死でやりました。それはもうありえないくらいの数を。僕が新規開拓したお客様だけでもかなりの数はあると思います。
事業承継の過程で意見がぶつかるのは当たり前

——現在会長であるお父様と意見がぶつかるのは、例えばどんなときですか。
林氏 意見がぶつかるというよりは、違いを感じた瞬間ではあるのですが、人との距離感の詰め方については、違いを感じる瞬間がありました。ある日、中途採用をしていた際に、一次面接の部屋にいきなり「こんにちは〜」と入って、自分の期待をその方に話していたことがありました。
一次面接の時点で、期待をちゃんと受け止めて活躍してくれる人だったらいいけれど、重荷と思って辞退されることもあるじゃないですか。情熱をぶつける場面・タイミングの違いなどで、意見がぶつかっているかもしれません。
——経営者としてお父様を尊敬しているところは、どこですか。
林氏 父は新しいことを起こすときに、必ず5つのオプションを用意しているんです。1つやってみて失敗しても、まだ4つのオプションが残されている。仮に、その1つが成功したら、もう1つオプションを付け足して、また新たなチャレンジをしていく。僕はまだ経験が浅いから、それだけのアイデアが出てこないんですよ。そこはすごく尊敬していますね。
あとは、信じられないくらいすべてのことが、スピーディー。メールの返信から大きな意思決定まで、何もかも。あまりにもはやすぎて、社内でまったく議論しないまま、モノを買ってくるのは困っているんですけど。でも、そのくらいスピード感がないと、今の時代は生き残っていけないんだなということは、常々感じています。
——歳をとって時代のスピードについていけなくなるという話は耳にしますが、御社の場合は逆なのですね。
林氏 はい。今までギリギリのところで舵を取り続けてきた会長は、経営の感覚が研ぎ澄まされているんですよね。だけど、経験のない僕は、まだその感覚がないので、今は様子を見て、次の挑戦に備えている段階です。
印刷技術によって畑と胃袋を最短距離でつなげたい
——現在御社の主流となっているビジネスを改めて教えてください。
林氏 デジタル印刷の技術を活用しながら、農産物や食品などの包装資材を中心に作っています。店頭で陳列がしやすい形状にすることはもちろんですが、農産物などの鮮度劣化の早い食材の鮮度を保持する技術を施すなど、包装するもの・目的などに応じた包装資材をご提供しています。
——なるほど。そういった食の業界で林社長が考えているビジョンはどんなものですか?
林氏 今はマイクロプラスチックの問題で、世の中からどんどんプラスチックが排除されようとしていますが、本当に目を向けるべきなのは、フードロスの問題だと思っています。
世界的には飢餓の国がたくさんあるのに、フードロスは日本国内だけで643万トン(農林水産省及び環境省「平成28年度推計」)もあるわけです。
これ以外にも、畑で捨てられる規格外の野菜や、流通の途中で傷んで捨てられる野菜もたくさんあって。この問題に対して、僕らが一生懸命やっている野菜の鮮度保持の技術が生かせるのではないかと思うんですね。

とはいえ、鮮度保持の技術が必要なのは売り手の都合です。流通にかかる日数を縮めたり、野菜の消費者を増やして売り場の回転率を上げたりすることができれば、鮮度保持の技術さえいらなくなるんですよね。
そこで考えたのが、デジタル印刷の技術を使って、野菜のパッケージにレシピを載せることで、一人でも多くの人に野菜を食べてもらう仕組みです。
——新しいコンセプトですね。
林氏 はい。農家の方の中には、野菜の包装資材を買うことがネックになることもあります。だから野菜の袋に広告枠を作って、スポンサーから包装資材代を払ってもらえたら、農家さんは助かるじゃないですか。
野菜はスーパーの入口付近の一番目立つところに並びますから、広告主さんにとってもメリットは大きい。野菜を買ったら、袋ごと家まで必ず持って帰りますから、“お茶の間まで届くDM”とも言えます。これも新しいビジネスモデルです。
——実際に、この取り組みを始めたのは、いつからですか。
林氏 本生産ができるようになったのは、2019年の年末ですよ。それでもここ1〜2月で、すでに20件以上の案件が決まっているので、滑り出しは順調です。

これまでデジタル印刷は単価が高くて、野菜の袋にはなかなか使えなかったんです。でもデジタル印刷で帯部分を印刷したものを袋に貼り付けた「オビパック」という技術を開発したことで、豊富なデザインで小ロットでの生産が可能になりました。
――すごい発想で、感心します。
林氏 すべては工夫次第だと思いますが、やはりこの仕事をやりながら食による幸せを人々にどうやって届けるかを常に考えています。そしてそれをどうやったら実現できるか。これが「畑と胃袋を最短距離でつなげたい」という私のビジョンです。

——では最後に、印刷業界で挑戦する次世代の若手社長に向けて、メッセージをお願いします。
林氏 印刷業界には、大手2トップが中心で動いておりそれは業界特性として代えがたい事実ではありますが、そこに依存しすぎているとなかなか自分たちでビジネスをコントロールできないと思います。
ブランドを持っている企業に直接提案する機会を作ろうと思えばいくらでも作れるはずなのに、でも自ら動こうとする会社はほとんどありません。そんな習慣に縛られていては、新しくて世の中に良いものは絶対に生まれないと私は思うんです。
あとは、競合とのコラボレーションを恐れないでほしい。僕が社長になってから進めているのは、最大のライバルとタッグを組むことなんです。これまで相手を打ち負かすために使っていた知恵を、お互いのビジネスを加速させるために使ったら、もっといいものができるはずでしょう。
僕はDscoop(HPデジタル印刷機のユーザーコミュニティ)のチェアマンをさせてもらっているのも、そんな理由からです。コラボレーションによって業界全体をよくしていきたい。
だから経営者や印刷会社の幹部のみなさんには、勇気を振り絞って、競合の社長と話をしてみてほしいんですよ。同じ悩みを共有できるかもしれないし、もしかしたら自分たちが勝手にライバル視していただけかもしれない。これまでなかった接点ができることによって、絶対に新しい何かが生まれるはずですから。