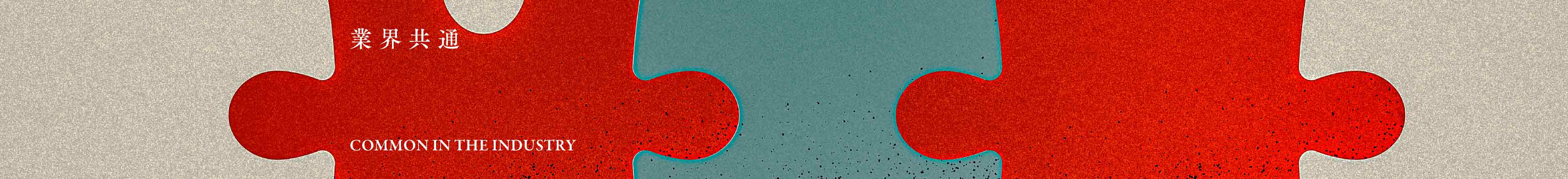"お手元商圏/エンゲージメント商圏"で
消費者はどうかわる?

IBM Future Design Lab.の活動は大きく4つに分けられる。1つ目はテーマ別の論点を提起すること。現在公開されている動画シリーズ がこれに当たる。2つ目は様々な事例やユースケースの発信。3つ目は専門家との対話から導かれる知見の発信と共有、そして4つ目は調査・ヒアリング活動だ。
今回催されたオンラインイベント「オニワラ」はIBM Future Design Lab.の3つ目の活動に該当する。「Vol.0」と銘打って開催された今回のテーマは、「“お手元商圏/エンゲージメント商圏”で消費者はどうかわる?」である。お手元商圏とはネットショピングを指し、エンゲージメント商圏とはロイヤリティの高い顧客によって形成される商圏と考えれば良いだろう。
IBM Future Design Lab.が独自に実施した「生活者動向・DX受容性調査」で明らかになった消費意識の変化を題材に、パルコのオムニチャネル戦略をリードしてきた株式会社パルコ執行役員 林直孝氏、日本の自治体でいち早くデジタル推進本部を設け新たな挑戦を続ける浜松市の瀧本陽一氏を招いた。
日本IBMからは、戦略コンサルティング&デザイン アソシエイトパートナーである髙荷力氏が議論に加わり、また、日本IBM出身で外資系ITベンダーやデジタル・クリエイティブ企業でマーケティングマネージャーやプロデューサーを歴任してきた株式会社HEART CATCH代表取締役プロデューサーの西村真里子氏が企画とモデレータを務めた。
演出面でも通常のオンラインイベントとは一味違った工夫が凝らされていた。審査員役で参加した藤森氏が両手に鬼のイラストをプリントした「オニワラ」のプレートを持って待ち構え、座談会の最中に未来を感じるポイントを発見したら「オニワラ!」と叫んでプレートを挙げて乱入するという趣向を取り入れ、場を盛り上げた。
エンゲージメント商圏では
大企業の優位性が通用しない
 イベントは西村氏の軽快なトークで進められ、8月末にインターネットで実施した「生活者動向・DX調査」を担当した髙荷氏から調査結果のプレゼンテーションから始まった。この調査は「生活価値観」「消費意識」「ITリテラシー」「DX意識」などの指標を基本軸にDXへの総合的な態度を診断したもので、顧客タイプの定式化、変化の予測にもチャレンジしている。
イベントは西村氏の軽快なトークで進められ、8月末にインターネットで実施した「生活者動向・DX調査」を担当した髙荷氏から調査結果のプレゼンテーションから始まった。この調査は「生活価値観」「消費意識」「ITリテラシー」「DX意識」などの指標を基本軸にDXへの総合的な態度を診断したもので、顧客タイプの定式化、変化の予測にもチャレンジしている。調査結果からわかったことは大きく4つ。1つ目は、DXによるサービスの高度化を重要するという許容層は43.1%あり、拒否層はわずかに12.5%しかいなかったことだ。「拒否層には男性20歳代と女性70歳代が多く見られました。これも発見です。意外にも若い男性に拒否層があるんです。テクノロジーの進化についていけないという警戒心がありそうです」(髙荷氏)。
2つ目は、ネットとリアルのいいところを使い分けたいという“良いとこ取り”を望んでいる人たちが73%と多いことだ。自動化、高度化への期待も高い。コロナ禍を経験したこともあって、こうした要望が高まっていると考えられる。
3つ目は、生活価値観として、健康や家族などへの意識が向上し、新たな価値観が生まれていること。元気で健康な暮らしが大切だという回答が87%を占めた。「次に多かったのは、将来が見通せないので、自ら備えることが大切という回答。これは決意表明とも読み取れます」と髙荷氏は語る。
最後は、必要なものは所有した方が安心と考える人が72%を占めている点だ。これまでのシェアリングエコノミーのトレンドとは真反対だ。「巣ごもりや他人に対する警戒感から所有へとシフトしているのかも知れません」と髙荷氏。藤森氏は「個人は所有にシフトし、企業は従業員のシェアにシフトしているという傾向があります」と最近のトレンドを解説した。
パルコの林氏は59%が自分にあった商品、サービスを提案してほしいと回答している点に注目し、「コロナ禍で好調なのは楽器。それと家具やインテリア」と話して「家にいる時間が増えただけに、自分が楽しむもの、自分にあったものを求めていることの象徴」だと指摘した。
また瀧本氏は半数の人が自分の地元に貢献したいと考えている点に触れ、「マイクロツーリズムなどを通して地元の魅力を再発見してもらい、地域への愛着を深めてもらうようにしたい」と話した。
髙荷氏は「全体に商圏が大きく変わっていく兆しを感じます。物理的な商圏がスマホからアクセスするお手元商圏のような仮想商圏が生まれました。今はその2つが合体した商圏ができてきていて、想いで左右されるエンゲージメント商圏になっていくのではないでしょうか。そこでは必ずしも大企業が優位に立てるわけではありません」と分析する。