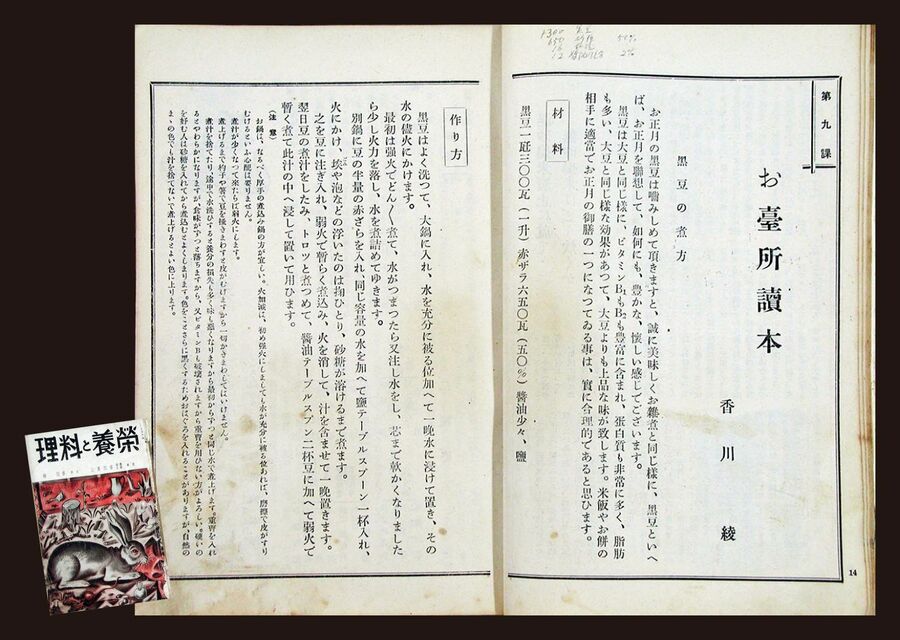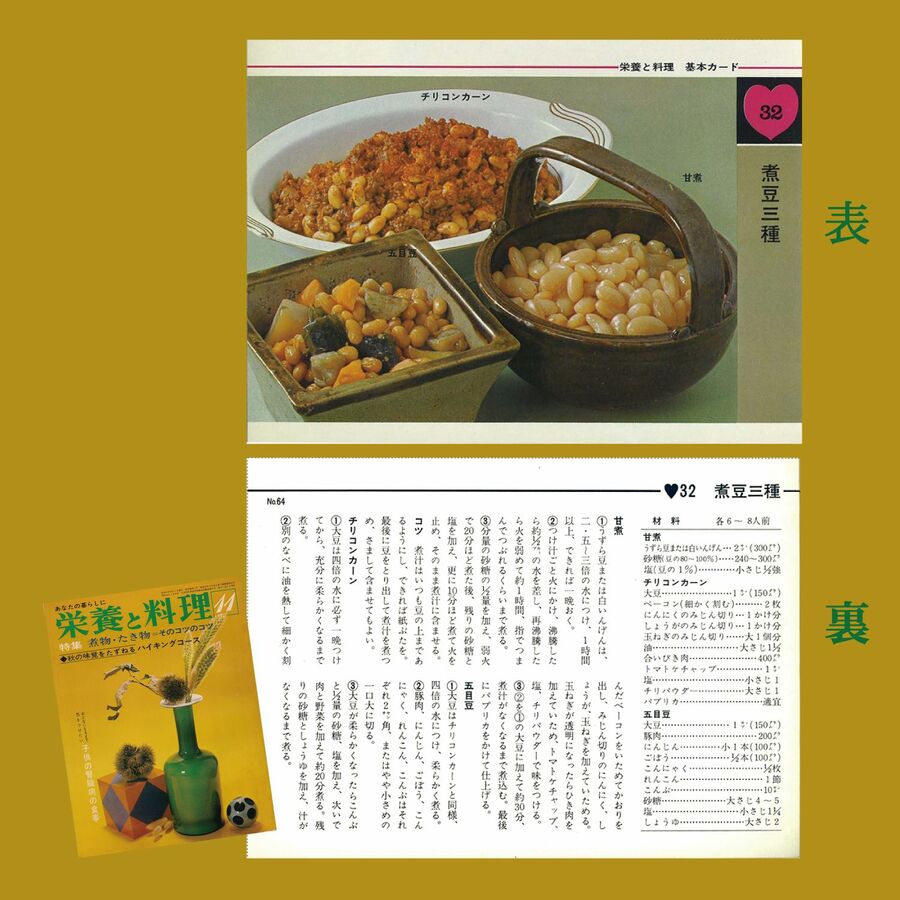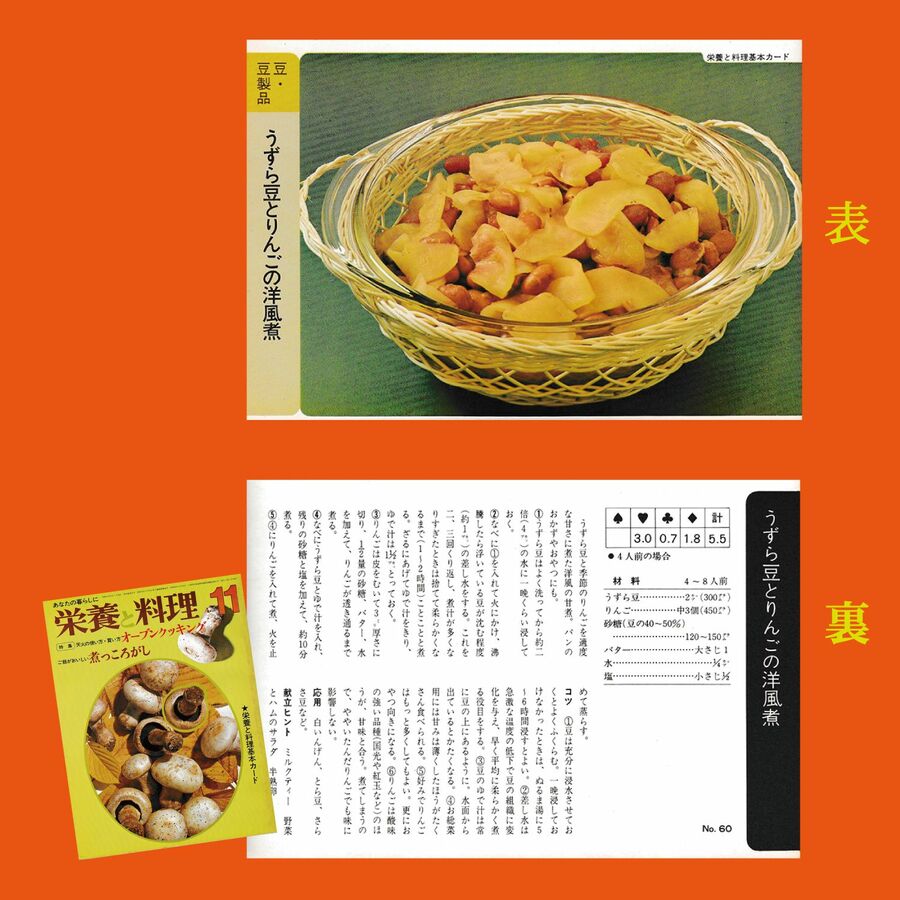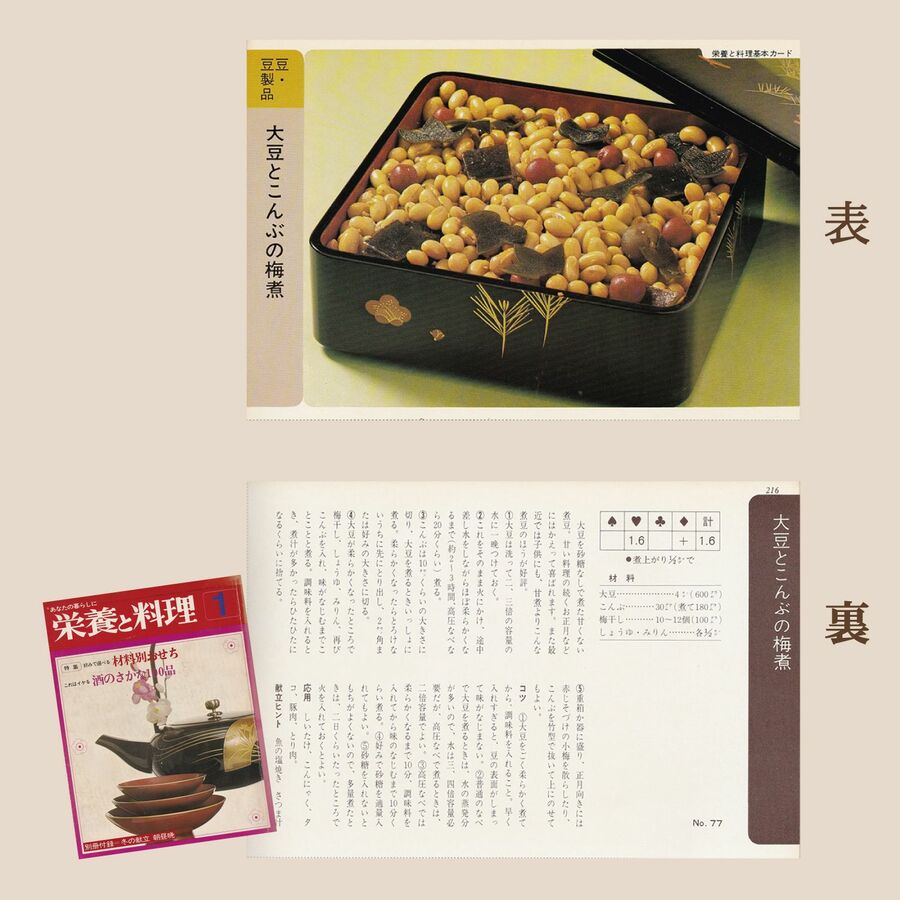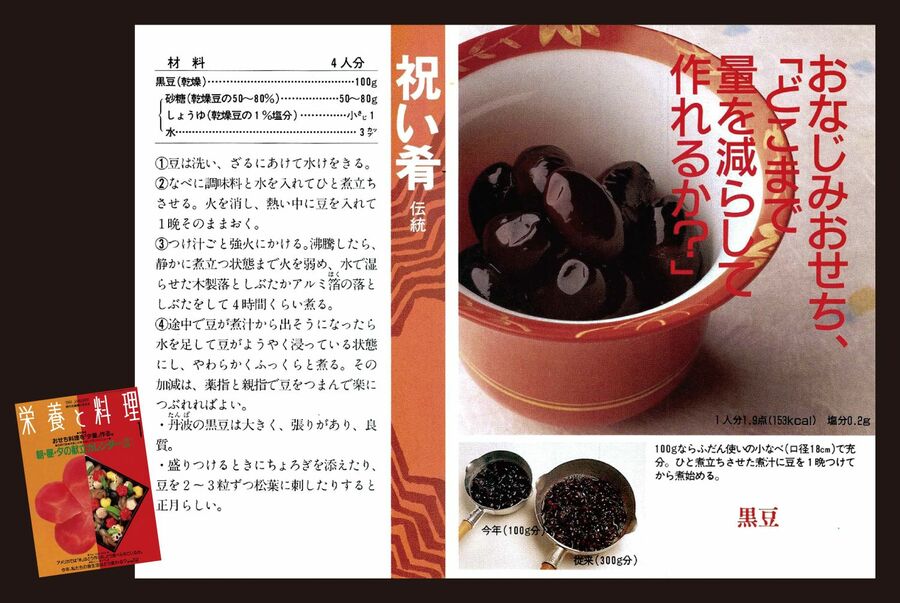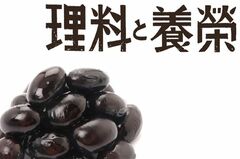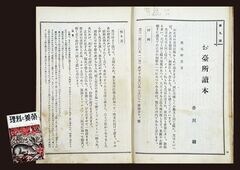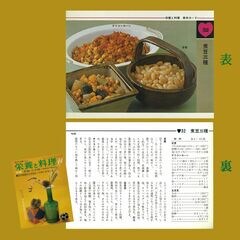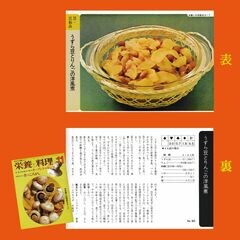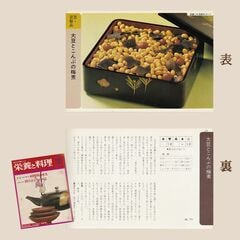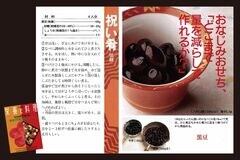次の記事へ
中国に奪われる可能性のある日本の食料
本日の新着

【日韓首脳会談】日本・中国の間で絶妙のバランス感覚を見せた李在明氏、中国が狙う「抗日共闘」に動かなかった理由
李 正宣

【Podcast】ベネズエラ、「延命」狙いの支配階級vsマドゥロ拘束に安堵する国民…ロドリゲス暫定大統領はどう出る?
耳で聴くJBpress《ちょっとクセになるニュース》
JBpress

シチリアワインはイタリアワイン? 変革者「ドンナフガータ」のはじまりの地へ
佐々木 ケイ

愛らしくも自分勝手なクソ野郎、実在する卓球選手をシャラメが演じた「マーティ・シュプリーム」が大ヒットする必然
【映像作家・元吉烈のシネマメリカ!】シャラメ以外に主人公が思い当たらないはまり役、豚とのキスをかけた最後の戦いはいかに?
元吉 烈