鷗外が小説を書かなくなった理由
 明治天皇 写真=Mary Evans Picture Library/アフロ
明治天皇 写真=Mary Evans Picture Library/アフロ
さて、1912年(明治45)7月30日、明治天皇が崩御します。
漱石は、喪失感はあるけれど「自分は自分、人は人」として、新しい時代を生きていこうじゃないかという姿勢で、『こころ(原題は『心』)』を発表します。
自分の抱えている問題は自分で考えて、解決していくための勉強が必要なのだというのが漱石の考えでした。この考えこそが、大正デモクラシーを生む力になるのです。
志賀直哉、武者小路実篤、芥川龍之介、鈴木三重吉などが登場する力は、「言文一致」にこそあったのです。
しかし、この大きな流れに、鷗外は乗ることはできません。
文語体を守り、桃さえ湯がいて食べていたというほど潔癖で、保守的な鷗外は、天皇や皇室の綺麗な世界や、軍の権威を絶対善とする精神的呪縛を振りほどくことができないからです。
こんな逸話が残っています。
天才女流文学者・樋口一葉の葬式に、鷗外は、軍服を着て白い馬に乗って行くのです。
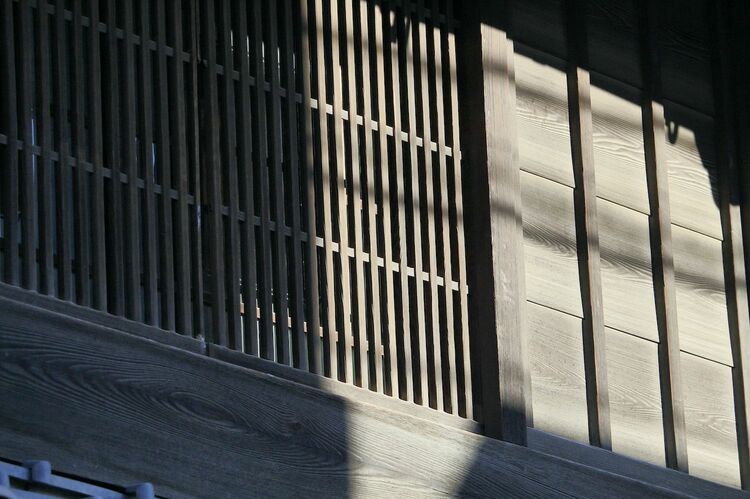 文京区、菊坂にある旧伊勢屋質店 写真=アフロ
文京区、菊坂にある旧伊勢屋質店 写真=アフロ
一葉が住んでいたところは、場末の女郎たちが住んでいた汚いところです。
一葉の母親から「こんなところに、そんな姿で来てくださるなんて、恥ずかしく、みっともないからやめてください」と言われてしまうのです。
白い馬で軍服を着て、権威を翳しているものに対して、江戸っ子は「みっともない」という感覚でしか見ていません。しかし、その「みっともない」という意識が、鷗外にはまったくわからないのです。
これは、小説『舞姫』にも言えることです。
鷗外にとって舞姫と恋に落ちたことは予想外だったに違いありません。「舞姫」と言っていますが、彼女は娼婦です。
鷗外は、触れてはいけないものに触って感染してしまった、という感じだったのではないかと思います。自分で自分をどうしていいかまったくわからない、助けることができないので、小説でも親友が救っています。誰かが言ってくれればそうする、伯爵という偉い人が誘ってくれたので従う、ということです。自分の意志をも押しつぶす「権威」に従うことが「善」であるという意識が、鷗外を動かしていたのです。


