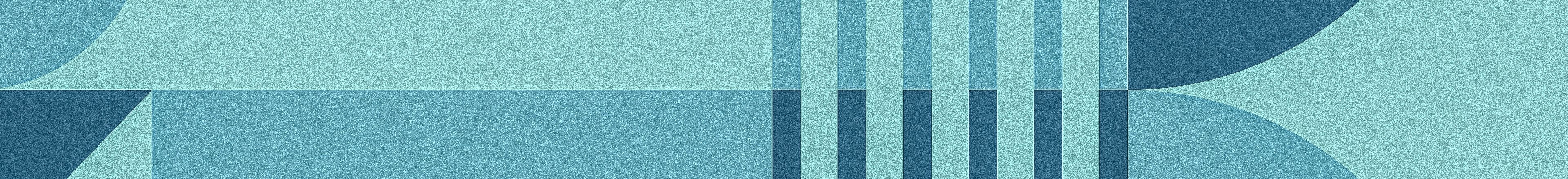デジタル変革の実行は小さい組織のほうが有利
――デジタルトランスフォーメーション(DX)は、日本の多くの経営者が意識する事柄となっていますが、実践事例は大手企業のものが目立ちます。中堅・中小企業ではまだ大きく進んでいるといえないと思いますが、その理由は何でしょうか。
多くの企業の経営者と話す機会がありますが、特に大企業だからDXが進んでいるとか、進めやすいとは思っていません。逆に、規模や構造を考えると、大手よりも中小の方が身軽に動ける分、新しいことを始めやすいとも言えます。中小企業だから不利だと思い込まないことです。
また大企業は、新規事業ではある程度大きな効果が見込めないとスタートできません。小さく始めて検証を繰り返しながら可能性を探る「アジャイル」なアプローチが求められるデジタルビジネスにおいては、むしろ小さな企業の方が有利とも言えます。つまり、DXの実行に関して、企業全体の規模の大小はあまり関係ないというのが、私の見方です。
 神岡 太郎/一橋大学 経営管理研究科 教授
神岡 太郎/一橋大学 経営管理研究科 教授1990北海道大学大学院博士課程(行動科学専攻) 単位取得退学、1990年 一橋大学商学部専任講師、助教授を経て、2004年より現職。2007-2008年 役員補佐(学生担当)、2009-2010年 役員補佐(社会連携他 担当)を兼務。学外では2010年より政府情報システム改革検討委員会委員(総務省)等も務める。研究領域としては、企業全体の規模で情報システムやマーケティングの機能をいかに実現するのか、またその仕組みに関心がある。例えば、それらの組織的機能のマネジメントや体制、CIO(Chief Information Officer)やCMO(Chief Marketing Officer)といったリーダーシップ、それらのガバナンスが含まれる。
確かに、デジタル化によって従来のビジネスが大きく変わり、それまでの商流が変革されて異業種企業にビジネスを奪われるような危機感を持っている中小企業の経営者の方もいらっしゃるでしょう。しかし、大きな環境変化は誰しも不安に感じます。しかし、環境が変化することは、中小企業が大手企業に対抗できるチャンスにもなり得ます。中小企業であろうが大企業であろうが、同じ環境変化を、脅威ではなく、それをチャンスにできるかどうかがポイントになるでしょう。
先日、日本を代表する大手ゼネコンの経営者とお話することがありましたが、「2025年には、東京の人口ですら減少に転じる。そうしたときに今までと同じビジネスは成り立たないだろう」と危機感をあらわにしながらも、人口減少の中で自分たちにできることは何かと、新しいビジネスの構想を練っていました。デジタルうんぬんというより、企業は常に事業環境の変化に備えなければいけないということです。そして、事業の変化をチャンスに変えるために必要なツールが、デジタルなのです。
デジタルの活用によって、もっと顧客が望むようなサービスを提供できる可能性が広がります。特に少量多品種でカスタマイゼーションによって付加価値が付くビジネスに注目しています。大企業では意思決定のプロセスが必要で短期間にできないようなことが、中小企業だからパッとできることがあるはずです。
古い業界でもDXは必要
どうやって進めるべきか
――印刷業界でも、二極化が進んでいると思います。一部の企業では危機感を鮮明にして、最新のデジタルによって事業の変革を図ろうとしている動きもあれば、数々の壁や不確実性から新しいことに踏み込めない企業もあります。印刷業界は日本に代表される製造業の一部です。大量印刷・大量配布時代の印刷装置もまだまだ現役であり、そこに受注を運び設備回転効率により利益を上げてきたのが従来のスタイルです。デジタル変革時代においては、どの業界も変革を迫られていますが、減少しながらもまだ売り上げの上がるスタイルから抜け出すことに抵抗があるという側面もあります。
この問題も、基本的なところでは、大企業も中小企業も全く同じです。大企業でも間接部門の業務などは、「今まで通り続けることになんの問題があるのか」という企業は多いです。よく言われて変革の阻害要因に「レジスタンス」と「イナーシャ」があります。レジスタンスは変わることに抵抗する勢力、イナーシャは惰性です。変革そのものに強く反対する前者は一部で、多くが後者、つまり新しいことをやることに抵抗はしないが、よほどの強制力がない限り今までのことを続ける人たちなのです。客観的に見て危機が目の前に迫っていても、惰性でそれまで通りのことを続ける人たちは、自分たちだけは何とかなるのではないかと、楽観的に物事を見てしまうのです。
これをどう突破するのか、一番大事なのは、トップが客観的に今を理解した上で未来へのビジョンを提示し、いま自社が置かれている環境がどうなのかを自らの口で具体的に語り、社員に理解してもらうことです。誰でも、何も刺激がない中で変わることは非常に難しい。必要性を感じなければ、自ら変わることはできません。
――経営者は、なぜ社員に自分の考えをうまく伝えられないのでしょうか。
一因は、トップが自分だけで考えているからだと思います。いろいろな意見を聞いて、自分の考えを上手くまとめていない。コンサルタントが持ち込む資料をアレンジした程度で、そのまま話しても、自分の言葉になっていないため、社員には刺さりません。
「いや、それは説明しているつもりだ」と社長は言うかもしれません。確かに必要性を一生懸命に語っているのですが、表面的なことが多いのではと懸念しています。経営者はともすると、すぐにお勉強したAIやIoTといった技術のことを話したがりますが、むしろ、デジタルテクノロジーのことを全く話さずに、自分たちはどういう価値を作らなければいけないのか、そのためにどう変わるべきなのかということを説明しなければいけません。デジタルは、その中で必然的に使いたくなってきます。
もう一つは、変革が避けて通れないことを社員に気づいてもらうことです。会社が今までの体制を続けていると、社員はそれに気づかない。例えば、新しい人を入れる、あるいは社員を外部の会社の人と接触させるなど外界と触れ合うことが有用です。しかも、可能であれば違う業界、印刷業界なら紙の媒体の取引先でなくてもいいじゃないですか。もちろん日本でなくてもいい。変化が激しい外部の業界を見ることで、自分たちも変わらなければいけないということが分かってきます。
それと、現場は変革に反対しているとトップは思っているかもしれませんが、それは思い込みということもあります。ある大手のエネルギー関連企業の社長は、自分は変革したいと思っているが、技術部門のマネジャーは保守的だと言っていました。ところがそのマネジャーたちにも話を聞くと、そうではなかったのです。現場は変化の重要性を肌で感じている場合もあるのですが、社長が社員とコミュニケーションを十分取らないと、社員の心は昔と同じままだと思い込んでしまうのです。今までと同じイメージと文脈で話をすると、社員は自分たちの意識が変わっているのに、DXに対してネガティブな反応を示してしまうものです。ですが別の人が間に入って説明すれば、あっさり分かり合えるようなこともあります。
――業界によっては、内部に閉じこもっていて、ほとんど外との交流がないところもあります。
そういう業界でも自社内でのデジタル化は進んでいると言うのですが、実際に見せてもらうと、単に数値を集めているだけに過ぎないこともあります。「見える化」とは、自分以外の人が見ても理解できるようにデータを見せることなので、データを共有する前に、誰にでも変わる形に加工する必要があります。

データ共有に関して私が関わった案件で、札幌市の産業振興財団が中心となって「オープンデータ推進協議会」(現在の「SARD」)というものをつくって、複数企業でデータを共有する取り組みがあります。自分の会社のデータと他社のデータを組み合わせると、今まで気が付かなかった気づきが得られて、データをビジネスに生かすことについて考え方が変わるのです。
現場リーダーと経営トップが両輪となってDXを進める
――経営トップがDXをリードするということは分かりました。では、逆に現場発のDXというのは起こせないのでしょうか。
DXは経営トップのコミットメント、リーダーシップがなければ起きません。もしトップが組織を動かすという意志を示さずに変わっていけるとすれば、それは相当時間がかかるはずです。DXの時代には現実的ではありません。
ただ、誤解してほしくないのは、トップが全てのことをやるという意味ではないのです。つまりボトムアップも絶対必要です。先ほども言いましたが、現場は世の中の変化を感じている可能性は高いのです。フロント部門が情報を入れて、内部に刺激を与えながら危機感を共有していくことが必要です。
急成長したある小売チェーンでは、トップがITを活用するという意志と大方針だけを示して、あとの一切を現場に任せています。現場が「これからの小売業はどうあるべきか」を真剣に考え、現場主導でデジタルを取り入れていくのを社長は承認し、耳を傾け、評価することを約束したのです。その結果、目覚ましい成果を上げることに成功しました。
――ところで、企業がDXを機に狙っていくべき領域、マーケットはどういうところでしょうか。
それは業界にもよると思いますが、私の考えではDXには2つの方向性があって、1つはデジタルを活用することで、今までのビジネスややり方をより良くしていくこと。これはこれで非常に重要です。そしてもう1つは、今まで業界ではやっていなかったサービスを生み出すことです。そのためには、自社のこれまでのビジネスにとらわれない発想をもった人材の採用が重要です。新しいスキルと、新しいマインドセットを持った人材が必要です。こうした人材は、自分の能力が発揮できて新しいことにチャンレンジできるなら、米国などでは小さい組織でも志望する例も増えていると聞きます。
間違いなく言えるのは、これからは仕事を待っているだけではジリ貧になるばかりだということ。何ができるのかが分かれば、その価値を誰に提供するのかも見えてきます。「顧客の開発」をすることが重要です。中小企業だからこそ、ターゲットを絞って顧客をよく理解し、例えば富裕層に付加価値の高いものを提供することができる可能性があるでしょうし、今までとは全く違う業界と取引できるかもしれません。
印刷業界で言えば、例えば「印刷×観光」とか「印刷×地方」のようなキーワードで、ビジネスや社会課題の解決について自社で何ができるのか、社内で議論してみるのもいいかもしれません。
デジタル化時代にこそ日本のチーム力は生かせる
――デジタル化のもう一つの側面としてグローバル化があります。今まで日本の国内に閉じていて、安泰に見えた市場にも、中国などの海外から突然競合が現れて、自分たちの市場を根こそぎ持っていってしまうようなことも、これからは起きるのでしょうか。
全くあり得ると思います。どのような業界でもグローバル化は避けられません。クラウドサービスの浸透を見れば分かるように、ビジネスの基盤は完全にグローバル化しています。
その中で重要なのは、新しいチャンスに飛び込むというマインドです。海外と比較して、日本はすでにかなり遅れてしまった感があります。チャンスがあれば人材が必要、そして人材を採用するためには成長が必要という好循環が生まれている国が大きく伸びています。
日本にも世界に誇れる力があります。例えば、日本人はチームみんなで取り組みを成し遂げ、それに喜びを感じるのがすごくうまい。データは、個人やチームを超えて共有されることで大きな価値を生み出します。また、イノベーションは異質のものの組み合わせから生まれることはすでに証明されているわけですから、多様性を入れながら日本のチームワークの精神を生かす方法を模索するのは、一つの方向性だと思います。2019年に開かれたラグビーワールドカップでの日本チームの健闘はヒントになると思います。日本にはチームで勝負をするという文化や土台がすでにあるわけですから、それをDX時代に合った現代風にアレンジすることを考えるべきでしょう。まさに、日本の良さが発揮できるところです。ただし、チーム力を昔ながらの忖度やウェットな人間関係だと勘違いしてはいけません(笑)。
――最後に、現場で自社の変革を目指すリーダーにメッセージをお願いします。
日本がこれまで経済大国として成長してきた中での基本的な価値観は、勤勉さや忠誠心、効率化にありました。いくつかの危機を、同じ方向性を貫いて乗り越えてきました。その過去の成功体験に縛られてしまうのは宿命と言ってもいいでしょう。またその価値観自体が間違っているわけではありません。しかしその価値観だけに固執するのでは生き残れそうにありません。そのためマインドセットを変えるのは非常に難しいのですが、やるしかありません。
企業の変革リーダーの方に会うと、その変化を楽しんでいるところがあります。もちろん仕事はラクではなく、未知の領域の仕事は不安ですが、その不安を抱えながらももっといいものにしようという意欲や熱意にあふれ、今のリーダーがやっていないことをやるチャンスだと感じているようです。
変化の時代のリーダーには、「自分たちの道を切り拓いていけるこのチャンスを、ぜひ楽しんでください」とエールを送りたいですね。