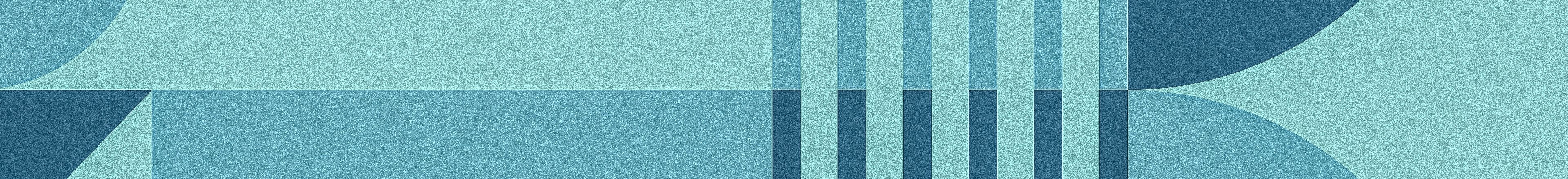短時間労働が理想なのではなく、むしろ質の高い仕事がしたい。そのためのムダをなくす「働き方改革」を
-逆に印刷業界ならではの問題点のようなものはどうでしょう? 日々感じているストレスなどありませんか?
佐藤:ストレスというわけではありませんけれど、私は以前、印刷のことがまったくわかっていない頃に、技術部門の人に「この色を変更してください」というような注文を結構気軽につけていたんです。でも、それなりに印刷のことがわかってきたら、色を変更する作業がどんなに大変なのかを知って(苦笑)、「ああ、今までの私はなんてわがままだったんだろう」と後悔したことはあります。
島田:そうですね(笑)、特にグラビア印刷の場合、色を微妙に変えるのは大変です。でも、それは自分たちの仕事にはつきものという感覚で私は捉えています。

藤江:そうそう、こういうストレスはむしろ「どうやって解決してやろうか」という考え方で、私も面白さに変換しちゃうクセがついています(笑)。そのへん、色彩の勉強をしてきた平田さんあたりはどうですか?
平田:私自身は営業職なので直接苦労をするわけではありませんが、当社はデジタル印刷を積極的に活用していることもあり、現場が微妙な色合いの再現に苦心していることは知っています。その大変さを知っているだけに、営業としてお客様のコンセプトやご要望を現場へ正確に伝えることが難しいと感じています。ですから、見本をお持ちした時、お客様から「なんとなく好きじゃないから変えてほしい」なんて言われてしまうと、自分の無力さを感じてしまいますね。
鹿野:お客様とその質に対する理解を共有するのって難しいですよね。

佐藤:私の場合、鮮度保持の技術を包装材に施していくようなチームにいるので、印刷とは直接関係ないかもしれないんですが、やはりお客様が我々の仕事を褒めてくださると、とても前向きな気持ちになります。社内もそうですが、社外の方々とも、そういうやりとりがあるからこそ頑張れるのだなと感じます。
島田:私としてはモノ作りのプロセスの中で自分たちが抱えているムダに対して、ストレスを感じることがあります。今私には2歳の娘がいて時短勤務なのですが、それでも仕事の質はきっちり高く維持したいわけです。日々、効率的に改善できる点が無いかを考えながら業務を行っています。そんな状況の中で、企画前段階において完成カンプ複数種の提出を求められたりすると、どうしても時間の工面に苦心してしまいます。
藤江:すごく共感します。カンプはデザインの方針を決めるための見本ですから、もちろん完成像をイメージできなければいけない。でも「今この段階でそこまで細かくやる必要あるの?」という場合のほうが圧倒的に多い。「働き方改革」の時代だから労働時間を減らそう、という風潮はウエルカムですが、短時間で今までと同様のクオリティを出そうとするなら、古い慣習に囚われないで、作業の見直しをしていくような「意識改革」も同時進行していかないといけませんよね
鹿野:いわゆる「働き方改革」の方向で労働時間を減らしていこうという気運はあるし、事実、それを進めているとは思うんです。でも、皆さんがおっしゃる通り、私たちは「早く帰れたらそれでいい」とは思っていない。短い時間で相応のクオリティを出すのなら業務プロセスの見直しもしていかないと、という気持ちを抱いている社員は少なくないと思います。
藤江:また性別の話を出してしまいますが(笑)、別の業界から来た私の目には、やっぱり印刷業界には昔ながらの男性文化みたいなものがあるように映るケースはまだあるかもしれません。
佐藤:「男性社会」というよりはやはり人数的に男性が多いのは事実ですね。印刷業界に限った話ではないかもしれませんが。
藤江:自分のことはさておき(笑)、世間一般の「上の年代の男性たち」を総称して「昭和島(しょうわじま)」って呼ぶことがあります。変化を望まない思考を称した昭和島カルチャーはやっかいですよね。たまに社内でそんな場面に出くわした時は、「その発想、変えましょうよ」と結構主張しています(笑)。
一同:たのもしい!(笑)
古いカルチャーを変え、新技術の導入やダイバーシティを目指そうというムードはある。
藤江:既得権にこだわる世代の男性だけを責める気はないので、「昭和島」なんて言い方はひどいんですけどね。別の見方をすれば、女性という立場でもかつての良さを多少理解できる私としては、一部の若い男性に見られる「上から言われたこと」「お客様から言われたこと」には無条件で従うのが当たり前、というカルチャーに少し不安を覚えることもあります。
佐藤:私も本当に性別で差別するつもりはないけれど、たしかにコミュニケーションの中で言いたいことが言えずにモジモジしているのは男性社員が多いと思っています(笑)。
平田:たしかに、女性社員のほうが言いたいことをストレートに口にしています(笑)。
藤江:よかった、私だけじゃなかったんだ(笑)。

鹿野:ウチの会社でも同じですよ(笑)。一部の社員はコミュニケーションだけでなく、新しい業務ツールやデバイスにも疎かったりします。ただ、変な表現ですけれど可愛いところもあって、そういう新しい技術を私たち若い社員が使い始めたりすると、気にはなるみたいでチラチラ見ていたりもします(笑)。
島田:当社は何しろ組織そのものが大きいので、年代や性別によるコミュニケーションギャップとか、テクノロジーについてのリテラシーのギャップというよりも、部門によってカルチャーやリテラシーが全然違う、というのが実感です。DXなども、おそらく業界をリードするくらいのレベルで進行していると思うのですが、今後の課題はそれをどうやってこの大きな組織全体に浸透させていくか、ということではないかと思っています。
鹿野:なるほど、大企業には大企業の課題があるんですね。当社は規模が小さいぶん、経営陣が「うちもDXを進めるぞ」と声を上げれば、それは全社員に届くのですが、いざ具体的に自分たちが使う業務システムを刷新する、となっても全体が動きだすのはそんなに簡単ではなかったりしています。
佐藤:当社も鹿野さんのところと同様、決して巨大な組織ではないのですが、島田さんのところのように部門ごとにやることが異なっていたりもするので、全社一丸になって新しいチャレンジに取り組もうとなった場合、足並みを揃えるのが大変だったりします。ただ、少し前にデジタル印刷について新しい取り組みを始める時には、技術分野のパートナーである日本HPが協力態勢を整えてくれたおかげもあって、一部のメンバーの活動ではなく、全体の取組みと意識されるようになったと感じます。ですから、局面によってケースバイケースだとは思いますけれども、ゴールを明確にし、誰でも取組みたくなるような情報を発信しながら動いていくと、藤江さんの言う「昭和島」世代の皆さんも含め(笑)、自分自身の行動も改革できるんではないかと思ってもいます。
藤江:すごくわかります(笑)。「そうやって、ちゃんとお膳立てをしてくれれば、俺にだってできるんだよ」みたいなところ、ありますよね。鹿野さんもおっしゃっていた通り、可愛いところがあるのも「昭和島」世代の皆さん(笑)。だから、私のように思ったことをすぐに口に出してしまう女性社員のほうも、単に性別や世代の違いで批判するのではなく、どうすれば一緒に頑張れるかを考えないといけないなと、心がけています。
平田:なんだか母性愛の世界ですね。勉強になります。
島田:うまい(笑)。でも、そういう女性の柔らかさを私たちはうまく活用するべきなんだよなあ、と私も思うことが多いです。
藤江:性別には関係なく個人それぞれ得意、不得意があるし、ベテランの経験が重要な局面もあれば、若い者だからこそ核心を突くような事が言える時もある。結局、なにより大切なのは多様性を活かしていくこと。
佐藤:ダイバーシティですね。私もそれに激しく同感です。
印刷業界の未来を私たちが変えていく。そのために今、考えていること
-最後に印刷業界の未来と、皆さんご自身の将来について、思うところを語ってもらえますか?
藤江:今私がありがたいのは、私のようにどんどん主張するタイプの人間を会社がむしろうまく使ってくれようとしている点です。関西にある女性のビジネスリーダーのためのコミュニティにも参加をさせてもらっていて、そこで出会う様々な業界、様々な立場の女性たちが実に刺激的で、たくさん気づきをもらっています。そうして外で手に入れた発想や姿勢を社内に持ち帰るのが、当面の私のテーマかなと思っています。
鹿野:私もいわゆる営業職から企画営業のような仕事に変わったタイミングから、社外にあるノウハウや知見を貪欲に吸収して、それを社内にフィードバックするような働き方をするようになりました。例えば社内では「初の試み」へのチャレンジであっても、社外にはすでにそれを始めているところもあるのだから、だったら大いに参考にさせてもらおう、という感覚。当社ではグループウェアを導入して、現在は活用の幅を広げているところ ですが、外部の導入企業から情報を集めて視野を広げていくプロセスが役に立ちました。
平田:私はまだまだ営業の仕事を学びながらやっているところですが、今日こうして皆さんのダイバーシティに関するお話などを聞いて大いに刺激になりました。当社ではまだ女性の営業職が少数派ですから、徐々にでもいいから増えて欲しいと思いますし、そのためにも私自身が結果を出していきたい。女性も男性も若い人もベテランもそれぞれの良さが出せる組織ができてこそ、ダイバーシティですね。
佐藤:私は前職では飲食産業で働いていたんですが、今ふり返ると「男性に負けないように」と力んで仕事をしていたところがありました。でも、今の会社に移ってきて感じたのは、ダイバーシティの話にも通じますけれど「性別には関係なく人それぞれの頑張り方がある」という点です。平田が言うように現時点での当社は男性よりも女性の数が少ないわけですが、できれば私たちらしい頑張り方で多様性の一端を担えるようになれば、組織のカルチャーはもっと面白くなるはずだと思います。
島田:当社ではおそらく業界のどこよりもDXや働き方改革が進展しているように感じています。他社さんの実情まではわかりませんが、きっと良い意味での仕事の効率化は進んでいて、時間的な余裕を私たち社員は今後どんどん手に入れていけると思ってもいます。ただ、それだけを喜んで終わるのではなく、「浮いた時間でどこまで仕事の質を上げられるか」、「どこまで私たちの大好きなクリエイティブな部分で価値を出していけるか」、が問われているのだと、自分に言い聞かせてもいます。印刷業界の多くの企業も当社の動向は見ているはず。ですから、今日のような同じ業界の皆さんと対話できる場にも顔を出しながら、この面白い仕事をもっと広げてさらに面白い業界にしていけたら良いな、と思います。

[取材を終えて]
今回の座談会で何より印象深かったのは、参加者全員の印刷ビジネスへの当事者意識。「男性だけの組織はダメ」「女性の地位を向上させるべき」という一方的な否定や要求ではなく「ダイバーシティにこそ価値があるのだから、性別による議論はやめて個人それぞれが持っている強みを発揮できるように」という考えのもとで「自分にできること」を見つめていた点で共通していた。
DXについても、デジタル印刷という一面に偏ることなく、業務変革や新規事業開拓などがデジタル変革の意味であることをしっかり自分事化してとらえており、そのリテラシーや意識の高さがハッキリ見えた。
また正直なところ意外だったのは印刷という領域特有の「匂い」や「色」や「手ざわり」という感性的な部分に強い愛情を抱いているという点だ。今後、デジタル技術は印刷領域においてもビジネスモデルを変革し、働き方も最適化されていくに違いないが、このような五感で感じる価値があることはこの業界の財産だと思われる。彼女たちの当事者意識、多様性の許容や懐の深さ、そして新しい挑戦を楽しむ姿勢が業界全体の発展に大きく作用していくだろうことを期待せずにはいられない。