データドリブンなビジネス開発には
まず「継続性」を担保せよ
2022.1.6
DXで本来目指すべきは、ITの導入による業務の効率化といった目に見えやすいゴールだけではなく、継続的なデータ活用による新たなビジネスの開発だ。日本ではなかなかうまく進まないことも多いデータドリブン経営の極意を、インフォマティカ・ジャパンの森本卓也氏に聞く。
データドリブンジャーニーを描く

セールスコンサルティング本部
CoE ソリューションアーキテクト &
エバンジェリスト
森本 卓也 氏
前回の記事「データ活用に成功する企業と失敗する企業。何が明暗を分けるのか」に見たとおり、DXに成功している企業はまだまだ少ない。その理由の1つは、DXを一過性のプロジェクトと同じ感覚で取り組んでいるからではないかと森本氏は考えている。
まず、DXに成功しているかどうかを分ける基準は、端的には、その取り組みによって大きなビジネス上の価値を上げていること。たとえば、DXの結果として企業の収益が増えただけではなく、ビジネスプロセスの改善につながる、あるいは新たなプロダクトやサービスが実現したなど、データから何らかの価値を上げている企業がDXに成功した企業といえる。特に海外ではそういった企業が顕著に増えてきている。
森本たとえば、海外のお客様例だと、ユニオンバンクという会社ではDXの結果がお客様の顧客体験の品質向上にしっかりとつながっています。業務フローの改善でこれまで1か月以上かかっていた新規ローンの承認が3分で完了するようになったり、従来は一人の顧客に対して証券部門、銀行部門など事業単位の観点でしか顧客行動を理解することができなかったものを、データを一元的に統合することで、より顧客のニーズに沿ったワン・トゥ・ワンのマーケティングが実現したりと、一歩踏み込んだ営業活動が可能となりました。
データ統合によって顧客の理解を深め、新たなビジネスに展開していく。これはDX、データ活用の文脈でよく言われていることだが、注目したいのは、業務フローの改善のように一見内部的な話に見える要素が、間接的にしろ、直接的にしろ、最終的には顧客の利便性につながっているという点だ。ビジネスプロセス全体を踏まえて、何のための業務フロー改善なのか、何のためのデータ統合なのか、そもそもデータから価値を得るとはどういうことなのか、ということをDXでは常に意識する必要がある。
もちろん、日本企業においてよく言われるカンパニー制の弊害もDXがうまくいかない要因だ。事業が縦割りになっているため、組織構造だけではなくそれぞれの組織が持つシステム自体がバラバラで、いざデータ分析をしようとなっても、データ基盤の統合がうまく進まない。しかし、海外の企業ではデータ活用がうまくいっていて国内の企業ではそれが思うように進んでいかない背景は、このような日本的組織文化に尽きるわけではない。ここで森本氏が重要なキーポイントとして指摘するのは「継続性を持ってデータドリブンに業務の改善を進められるかどうか」だ。
森本たとえば、DXに向けてデータの統合基盤を作るとなった場合、その後は稟議を通す、プロジェクト化するという社内プロセスが走ります。こういったケースでは、まず構築するシステムの要件定義をし、納期を定め、完結した計画として遂行していくことになります。そして、予定通りに終結したかどうかでプロジェクトの成功の可否といったものが判断されます。
しかし、データ統合基盤は一度作ってしまったら終わりという話ではなく、むしろ構築してからの方が肝心です。データ利活用の取り組みというとデータ基盤やシステムをいかに構築するか、いかにデータを貯めるかといったところに目線が行きがちですが、そうではありません。データの中から価値あるデータの組み合わせを見つけ出す、新たなインサイトを生み出す、それこそがデータの価値です。データから仮説を立て、その仮説を元に分析してモデル化し、実際に業務に組み込んでいく。つまり、現状のデータから、たとえば「次はこういう売上げになりそうだ」とか「こういった商品を準備しておくとよさそうだ」というふうに業務を作っていく。そうやってデータドリブンな業務への変革をなしとげるということがまず重要だと思っています。
しかし、実際にやってみたら想定通りの効果が出ない。仮説が間違っているかもしれない。あるいは、今回のコロナパンデミックのように、大きな変化が起きたことによって状況が一気に変わることも我々は経験している。データ利活用は「一度構築すれば終わり」というものではなく、常にPDCAを回し、アップデートし続けることが必須の取り組みなのだ。これを森本氏は「データドリブンジャーニー」という言葉で表現するが、継続性を持ってデータに向き合い、状況に合わせて絶えず変化をしながらビジネスを進めていく、永遠に続く旅路といったイメージだ。ジャーニーとして自分たちが進むべき旅路を描き、取り組むことが非常に重要となる。
何がDXを阻む壁になるのか
継続性を持ってデータとビジネスの間をいったり来たりしながら仮説検証を繰り返す、ビジネスの変化に応じて絶えず改善を繰り返し続けていく必要があるのは理解できるが、実際にはそれがうまくいかない。その理由は何か。ここでキーになるのが開発組織と事業部門の間の壁だ。データの根幹はシステムを握る開発組織にある場合が多い。一方で、データの活用に必要なビジネスへの理解は事業部門にある。このデータとビジネスの距離をうまくつなぐことが、継続性を持ったデータ利活用の鍵となる。
図1:システムの中に眠っているデータを
いかに活用するか

森本図1上部はアジャイル開発手法の1つである「DevOps」の概念を示したものです。プロダクトのライフサイクル全体にわたって、開発と運用が緊密に協調し、顧客に質の高いサービスを提供し続けることを可能とする、いわば開発におけるベストプラクティスです。
この手法はデータドリブン経営の考え方にも適用できると我々は捉えています。それが図1下部で示すフローです。どのデータの組み合わせがどのようにビジネスに貢献できるかというインサイトを見つけ、ビジネスに落とし込みます。そこから生まれた新たなデータにまた違うデータを組み合わせ、さらに変化を加えていくというサイクルです。このときに重要なのは次の3つのポイントです。1つ目は、データそしてビジネスに対し、開発部門と事業部門に関わらず同じ共通の認識を持つこと。また、2つ目は、データをいかにすばやくビジネスの世界に組み込むことができるかというスピード感です。そして3つ目は、事業部ごとのデータのサイロ化を解きほぐし、データの品質を一定に揃え、データの組み合わせができる状態を担保することです。
前述のように、日本企業の多くは、縦割り組織の中で、事業部単位でシステムを持ち、各々でデータを管理している。しかしデータの価値をビジネスの価値に転じるためには、単体のデータが意味を持つことはほぼないといっていい。さまざまなデータの組み合わせによって、はじめてビジネス的に価値を持つデータが生まれる。ところが、実際に起きているのは、たとえば事業部Aのデータと事業部Bのデータを組み合わせるとよさそうだと思いついたとしても、いざそれを組み合わせようとするとデータの中身もサイロ化していて使えないという状況なのだ。
図2:データドリブンなアプリケーション開発の3つの壁
(「データの透明性」「サイロ化」「アジリティ」)

こうした状況を打破するために、まずは開発部門とビジネス部門の間で、データとビジネスに対する共通理解を進め、データとその周囲の透明性を担保することが重要になってくる。そして、アジリティ。データをビジネスにスピーディに組み込んでいくためには、開発部門のあり方も大きく関わってくる。受け身のシステム開発ではなく、自社のビジネスを理解した上で、データの利活用を推進するためのシステム作りに能動的に関わっていくマインドが求められるのだ。
森本ビジネスの勘所を持ってITを語れるメンバーを社内に揃えていくことも大切なポイントです。事業会社のシステム部門でシステム開発業務を経験し、基幹業務データの意味付けを充分理解した上で、データ活用する部署に異動させ、データ分析やデジタルマーケティングを行う。それにより、ITとビジネスが分かる要員を育成するような施策が有効であることは、前回の記事でアクセンチュアの森さんも触れていました。さらに森さんは、「組織が縦割りのサイロ型で各部門からなかなかデータが上がってこないという企業もあるため、横の連携ができるような風通しの良い組織体になることが不可欠であり、そのためには、まずシステム部門からデータの活用部門に寄り添っていくような関係性が大事」とお話されています。
また、サイロ化されたデータを解くための解決策として、単純に1つのデータ基盤に統合するのがいいのかというとそれは現実的ではないと森本氏は指摘する。既存の業務がある中で、たとえば一つの巨大のERPに入れて解決しようとすると移行プロジェクトが大規模になりすぎてしまう。では、DWH(データウェアハウス)やデータレイクといったデータをためる場として必ずしも一つに統一する形がいいかというと、それもまたうまくいかないケースが多いようだ。
森本データを単一のドラム缶のようなところにまとめていくという話ではありません。便利なテクノロジーをうまく組み合わせ、データがシステム横断的に使える状態を整え、最終的にはビジネスにアジャイルに組み込んでいけるような環境をクラウドの中で作ってあげることが必要と考えています。
水の流れに喩えて話をすることが多いのですが、いろいろなところから集めてきたデータを1つの流れとして使えるようにしたい時、データを一定の基準に整える、きれいな状態にすることが重要となります。いわゆる“データの浄水場”と考えていただければいいでしょうか。そうすることでデータの品質が担保され、同じデータで物事を考え、同じデータでビジネスを動かすことにつながります。
これは同時に、データとビジネスが互いに透明性を担保することにもつながる話だ。開発部門は、データとして何が存在しているかをビジネス部門でも簡単にわかる状態を作る。逆にビジネス部門は、ビジネス的なニーズがどこにあるのかがわかるようにする。データとビジネス、双方が理解し合った上で連携することがポイントになる。
一人ひとりがデータに向き合う世界
データの利活用において、もう1つ重要なポイントがある。データの活用方法のナレッジを全社でいかに共有するか、だ。従来ではビジネススキルに長けた、あるいはベテランの社員の経験や勘に頼ってきた部分を、データ利活用によって、広く、誰でも実現可能にするという世界。それがDX、データドリブン経営の本質ということになる。
森本データとデータの関連性を考える、データ活用のノウハウの共有、これ自体も継続性を持って、データドリブン経営を進めていく上で非常に重要になってくると思います。
データとデータの組み合わせでこの商品の売上がわかるというような、それまで個々人の力量による職人的な発想に留まっていたことが、データの交換性などを加味することで、また違うインサイトが得られます。アクセンチュアさんも仰っていたように、得られたインサイトを実際のビジネスに組み込むことは大きなメリットですし、その考え方自体をノウハウ化して社内で共有していくことによって、別の人がちょっと真似るということもできるようになります。
そうして、データを使おうという文化が醸成されると、次々に生産的な発想が生まれるようになる。この連鎖はまさに、企業が継続的に、全社的にDXをやっていく上で重要ではないかと思います。
データに対するリテラシーを持ち合わせていない人たちでも、やってみようと思える環境を用意できれば、自ずと継続的かつ全社的なDXの推進が実現する。今までちょっと遠い存在だったデータをより身近な存在に変えるトリガーになるような仕組みが必要になってくる。
森本データに基づくビジネス戦略は企業としての根幹です。さらにそこに直接に関わってくるアプリケーションはまさに今後の自社ビジネスを支える基盤です。その開発をアウトソース化するのは、自社の事業の根幹を外に委ねるという話になってくると思います。そういったやり方では競争社会の中で勝っていくのは非常に難しい。かといって、卓越したエンジニアをすべての企業が抱えられるかと言うとそうではないわけですよね。
継続性という観点でも「誰でも簡単に理解ができて変更しやすい」という発想は重要だ。属人性を持ったプログラムに支えられたDXでは、将来にわたって、継続的にデータとビジネスを絶えず見守りながら改善を続けていくことはできなさそうだ。
森本アジリティ、サイロ化、透明性、やはりこの3つの課題をまずは解いていかないといけません。そのどれか1つが欠けても、データをビジネスに組み込んで継続的に活用していくという状態にはなかなかたどり着けないと思っています。データとビジネスをより密接に連携させ、セットで改善していく、業務に組み込んでいくことが重要です。
日本でも各企業の中で、DXは全社で実施するべきという風潮になっていると思います。実際に、その為に新たに部署を設ける企業も増えてきています。こうした動きはここ1年で顕著になってきたように思いますし、従来型の各事業部門にサイロ化されている世界で動くのではなく、事業横断で誰もが使えるようなデータ基盤を整えたり、文化を整えたりというところを目指しているのですが、日本の現状はまだそこには及んでいないのではないかという見解は通説になりつつあると思います。
海外に比べるとまだまだ遅いのかなと感じることもありますが、そういった人たちが自社でDXをやるためにこれだけの基盤、こういう組織が必要ですと稟議を上げたときに、スピード感をもって踏み出せる企業が増えてきているのは確かです。我々としては、日本企業が海外の企業と渡り合っていけるように、この流れをぜひ盛り上げていきたいと考えています。
 コロナ禍で露呈したDXの課題
コロナ禍で露呈したDXの課題企業は今、いかにデータ活用に
取り組むべきか
DXという言葉はさほど新しい言葉ではない。このムーブメントはこれまでも緩やかに、ある程度は進んでいた。しかし、…

 継続的なデータドリブン経営に必要なデータガバナンスとは
継続的なデータドリブン経営に必要なデータガバナンスとは
データドリブン経営を推進するにあたって忘れてはならないのがデータガバナンスだ。データを利活用するための枠組みを策定し…

 データドリブンなビジネス開発には
データドリブンなビジネス開発にはまず「継続性」を担保せよ
DXで本来目指すべきは、ITの導入による業務の効率化といった目に見えやすいゴールだけではなく、継続的なデータ活用による…

 データ活用に成功する企業と
データ活用に成功する企業と失敗する企業。
何が明暗を分けるのか
データ活用が企業経営・戦略立案に欠かせないと言わるようになって久しい。多くの企業が取り組みを進めているが…

成長戦略を描くには?

世界中が不安定な現在において、企業が生き残るため、また今後の成長に向けた準備のために、情報とアナリティクスから、…

 ビジネス成功のカギを握る
ビジネス成功のカギを握る「データ」を活用する方法
総合コンサルティング企業のアクセンチュアとデータ統合ソリューションを提供するインフォマティカがパートナーシップを強化…

正しいデータ活用方法とは!?

コロナウイルスの影響により、ビジネスの在り方や働き方が大きく変化している今、企業や社会におけるデジタルトランス…

新たな価値を見出すための
最適な方法とは!?

日本では年々深刻化する少子高齢化と人口減少に伴い、あらゆる業種・業界で人手不足の問題が発生している。そこで期待されて…

 新しいビジネスリーダーとしての
新しいビジネスリーダーとしての最高データ責任者(CDO)とは
インフォマティカが委託して実施したIDCの最高データ責任者(CDO)の調査によると、CDOが新しいビジネスリーダー…

 Capture, Curate, Consume.
Capture, Curate, Consume.~ データを使って競争力を高める ~
“スマート”で称されるスマートツール、スマートカー、スマートフォン、スマートビルディングなどのデジタル化されたデバイス…

 インフォマティカの
インフォマティカのデータガバナンスフレームワーク
「十分な」データガバナンスは、戦略的な領域において早期に信頼性を構築し、それをさらなる成功への足掛かりとして活用する…

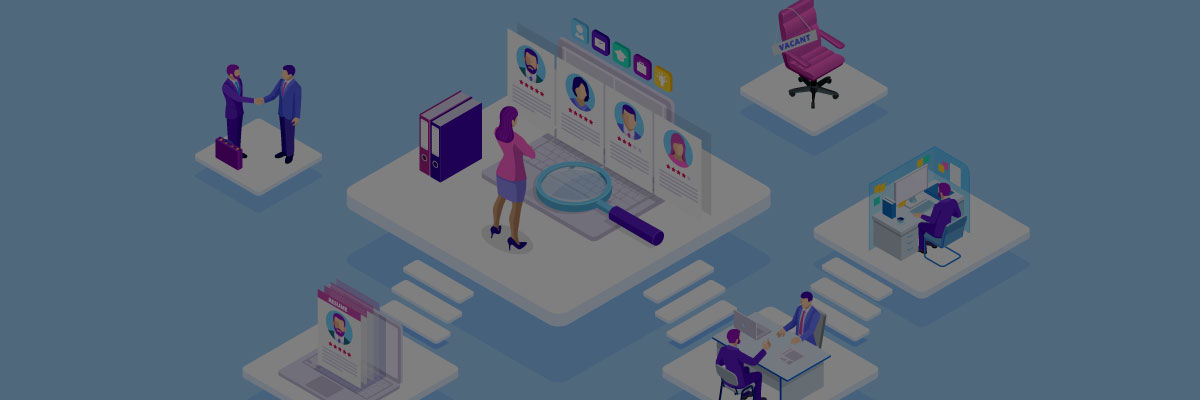 Data is the new capital
Data is the new capital ~ データは新しい資本 ~
過去数世紀にわたって、企業は成長し競争するために、人的、財政的、知的資本に依存してきました。 現在、新しい形態の資本と…

 AIを活用し、
AIを活用し、顧客との距離を縮める
皆さん、こんにちは。インフォマティカ編集部です。今回のブログはAXA XL社でCDO(Chief Data Office)を務める…

 Boost Data Veracity,
Boost Data Veracity,Bring Your ‘A’ Game
~ データの信憑性向上による
ビジネスの実現 ~
AI(人工知能)の源泉は間違いなくデータに他なりません。AIが貧弱なデータを利用していれば、望ましい結果が得られないかも…
